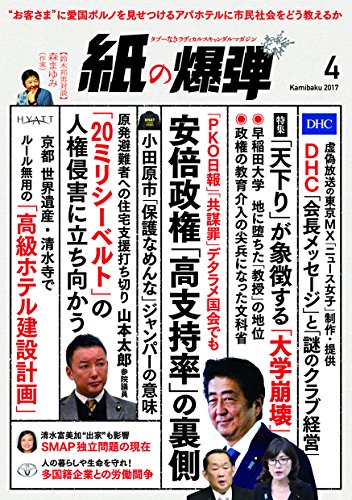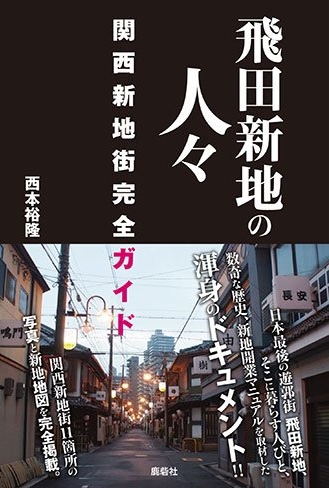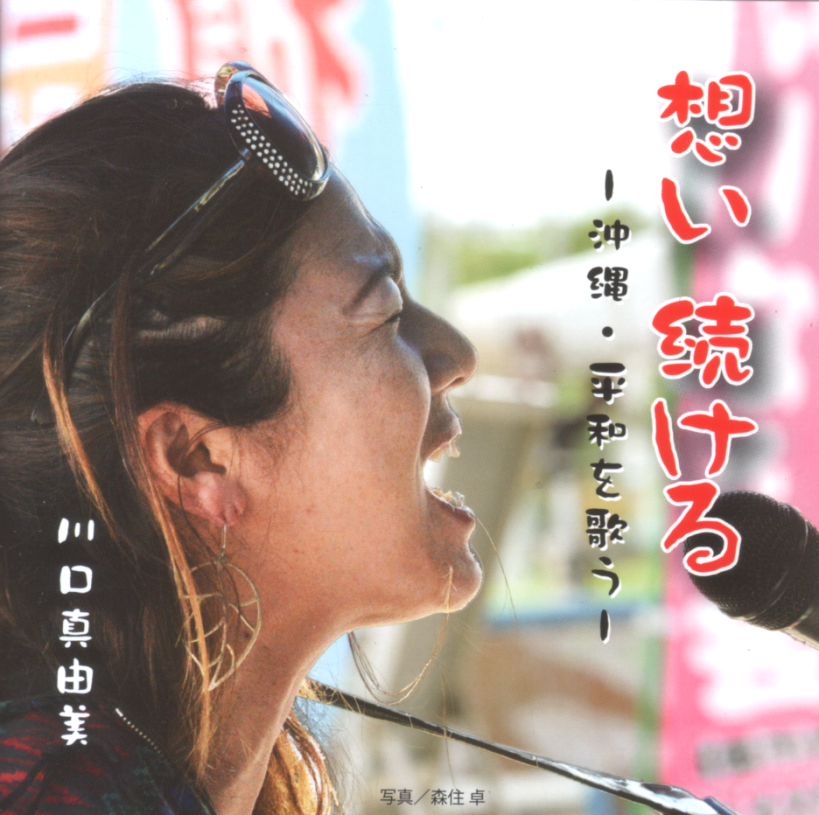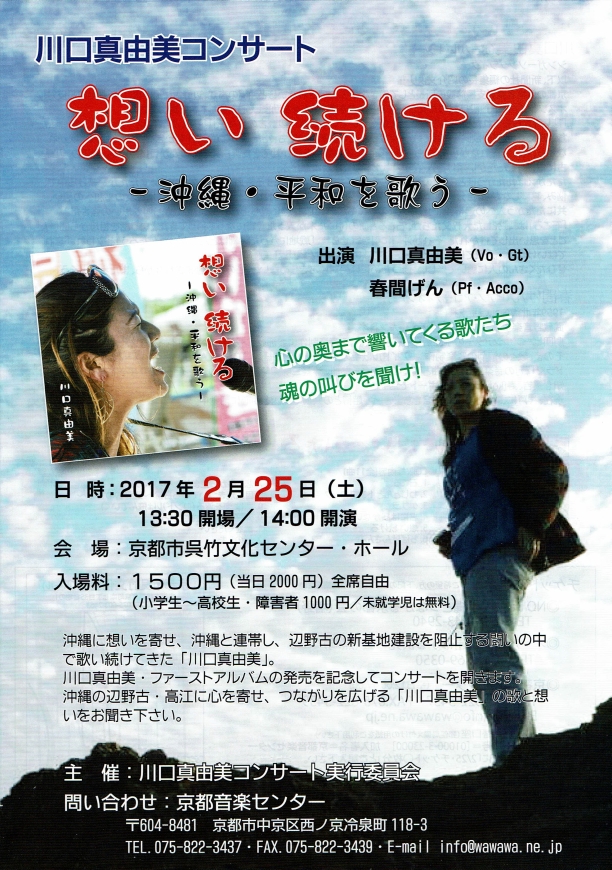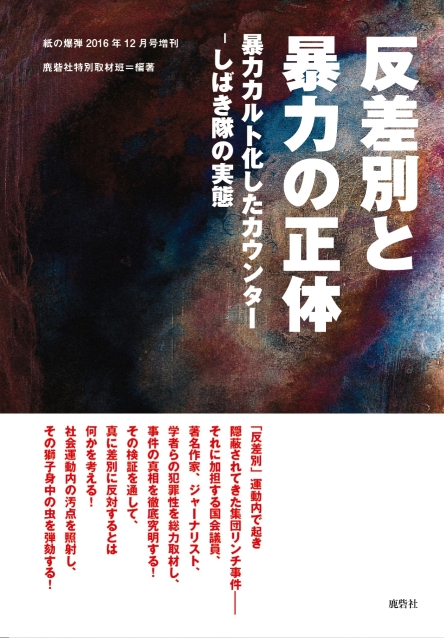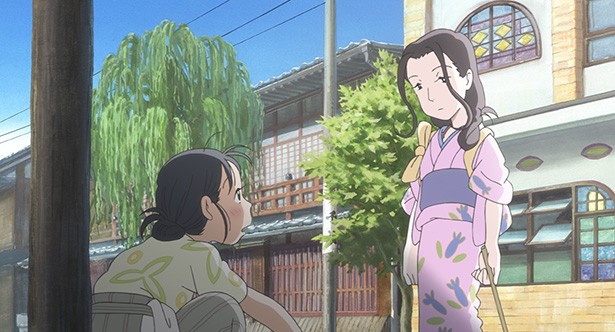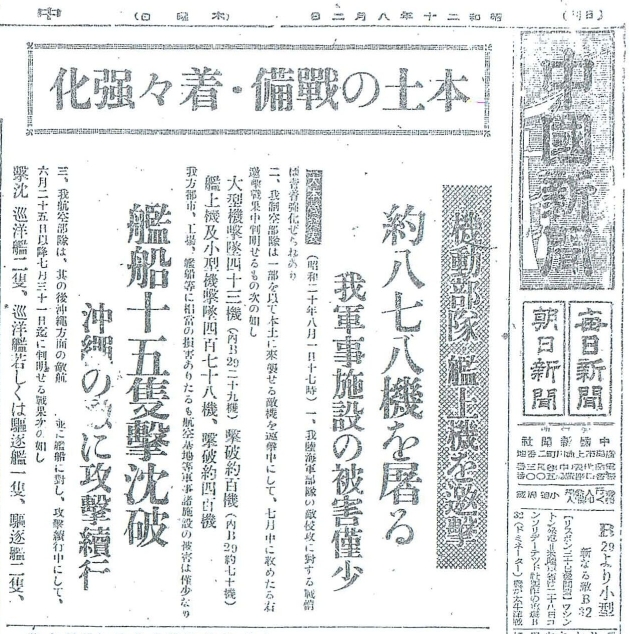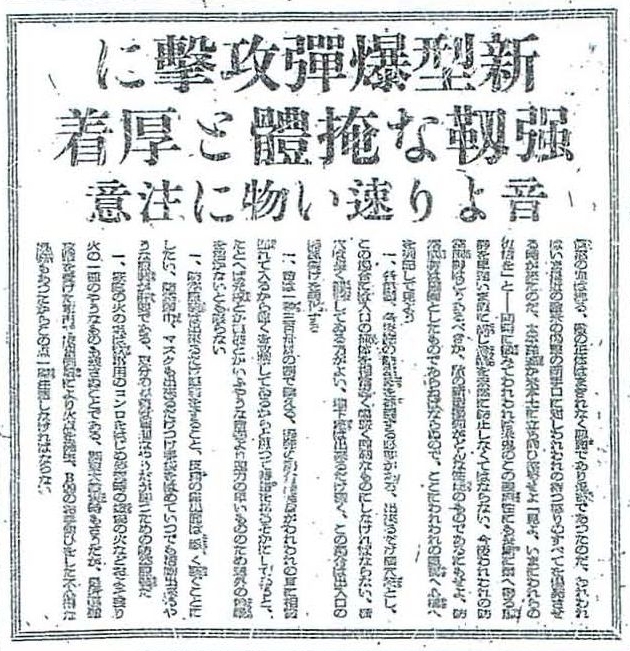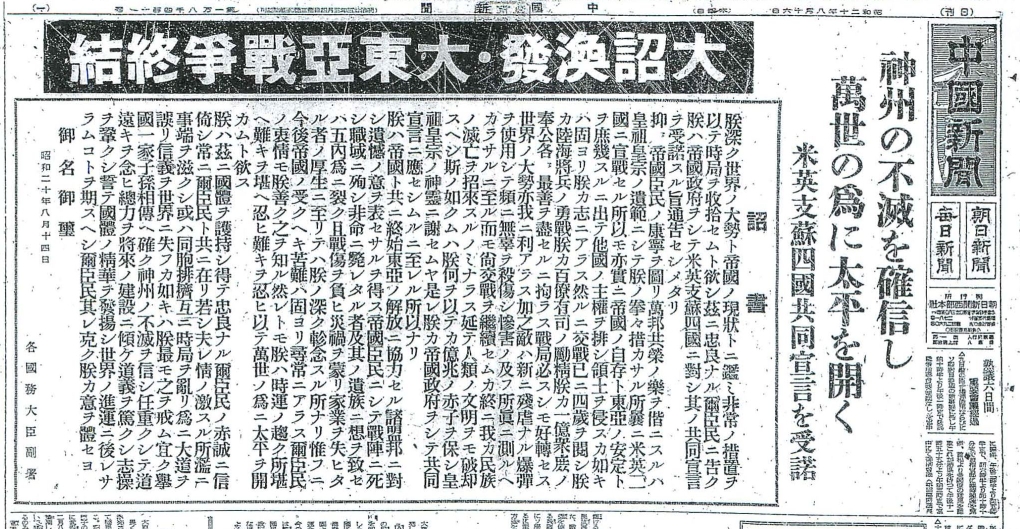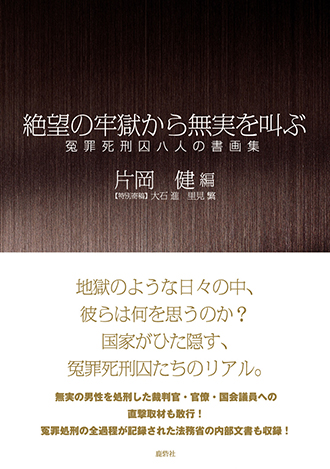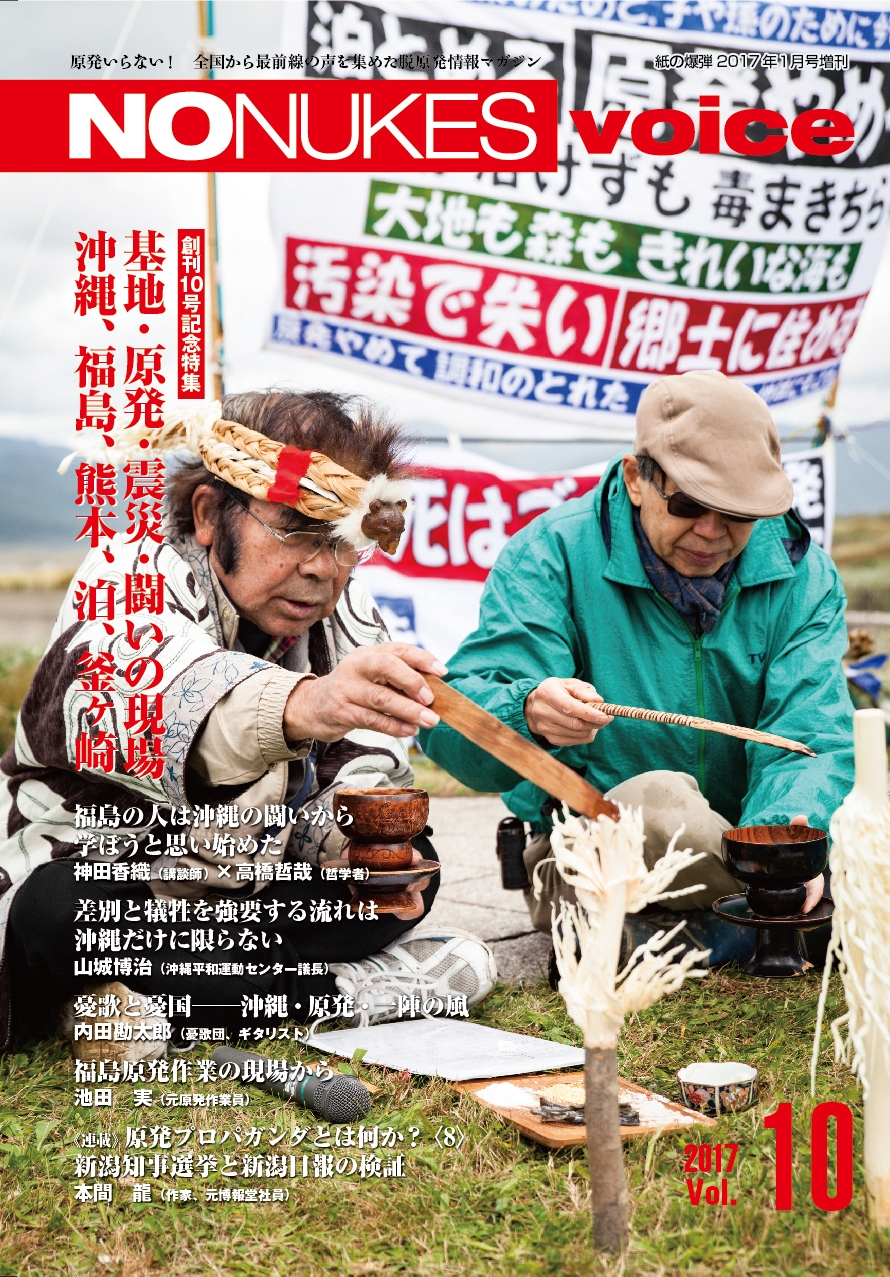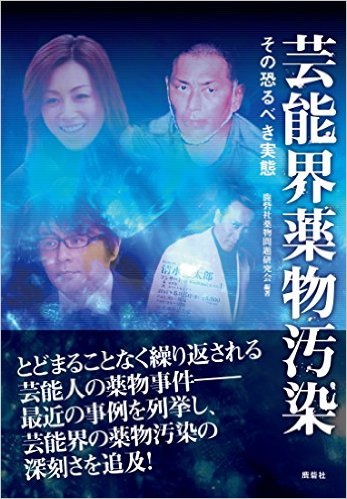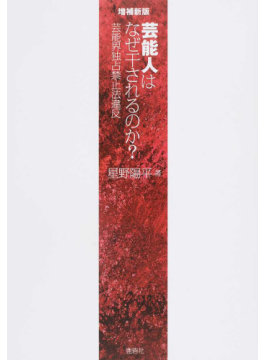社会人になり、編集プロダクションに入ったときの最初の先輩が、のちにミステリー作家になる北森鴻氏だった。1991年3月に入社して数日後、「呑みに行こう」と連れて行ってもらった先は、なんと路上の屋台だった。
「好きなもの、食っていいぞ」という北森先輩はその夜はとても饒舌で、「俺はいつか作家になる。おまえが先に売れれば俺はだいぶ楽になるなあ」と酔いがまわり、いくぶん上機嫌でいくつかのミステリー小説のプロットを語ってくれた(もちろんのちに作品になるものがたくさんあった)。
雑誌やスポーツ新聞や受験雑誌にスポーツや芸能、受験情報やイベント情報などの記事を書き散らしている編集プロダクションにあって、北森氏の才能は群を抜いていた。
北森氏は原稿を当時、シャープペンで書いていたが、400字10枚を20分足らずで書き上げる速さ。僕はひそかに「ジェットの執筆」と呼んで尊敬していた。だがお互いの信頼関係は少しずつヒビが入り始める。
なぜかといえば、「作家になる」と宣言していた北森先生は編集者としてもライターとしても恐ろしいほど才能がありながらも、編プロでの仕事を少しずつ減らしつつあり、嘱託のような生活をし始めた。会社も「作家になりたいのだ」と主張する北森氏に配慮して、仕事量を調節していた。
いっぽうで僕は編集プロダクションで手前みそだが、のしあがりつつあり、中心的存在へと確実にステップアップしていった。この編プロは編集と執筆が同時に求められるタイプの会社で、読者がおもに小学生や中学生の雑誌だったから、とにかく「わかりやすく書く」ことが求められていた。北森氏ものちに「編プロ時代のライター修行が作家になってから役にたった」となにかで書いていた。今、小説の文体を読み返していて、僕もそう思う。
「会社からフェイドアウトしていくのに、北森氏は優遇されすぎている」と感じた僕は、ことあるごとに北森氏とぶつかり合い、ある日を境にそれきり北森氏の飲み会にはまったく誘われなくなった。
心が狭い僕は、会社が行う北森氏の送別会にわざと長時間の取材を入れて、 これみよがしに送別会に欠席した。今から思えば、やっていることはまるでガキで、これから何年も出席しておけばよかったと悔いることになる。それが95年のことだ。
このとき、明らかに僕は北森氏が「狂乱廿四孝」で第6回鮎川哲也賞を受賞した現実に打ちのめされていた。
北森氏は、それまでつちかった取材でのデータエッセンスを執筆につぎこんで、何度読み返してもおもしろい話を書き上げていた。仕事は受賞して2年ほどがスケジュールが埋まり、明らかに僕より何十歩も先をいっていた。
「朝型」で朝7時ごろ出社して夕方5時には帰るという生活をしていた北森氏は、「夜型」の僕とはよく仕事がゆきちがい、何度も北森氏の自宅に電話して取材をどう進めるかという指示をあおいだ。その電話番号を、僕はいまだに忘れることができない。
これは今年になってはじめて知ることになるのだが、北森氏は、僕が要領が悪くて、なかなか仕事ができない時代に、よく僕のことをかばってくれたそうだ。そうした状況を無頓着ながら知らず、何度もできが悪い原稿でよく北森氏に罵倒されていたものだから、とっくに嫌われていると思っていた。
北森氏とつぎに話したのは、だいぶ間があいて、2005年。その編プロが20周年のパーティを開いたときだ。
相変わらず饒舌に過去のライター時代の話をおもしろおかしく周囲にしている北森氏に挨拶しつつ、当時、編集者として竹書房という会社に流れ着いた僕は、過去のことを一切忘れて挨拶するや否や反射的に「うちにも書いてください」と言ってしまった。
北森氏はビールをつぐ手を震わせていた。うまくつげなくてジョッキから泡がこぼれ出てきた。ビール瓶をテーブルに置くと北森氏は口を開いた。
「お前とはまだ早いだろう」
それが上下関係にあったとはいえ、過去に同じ会社でしのぎを削った元編集者兼ライターだからしばらく「編集者ー作家」という関係になるのは時間をおこう、という意味だったのか、それとも「時間がたったからもう少しお互いを理解してからにしょう。だいぶ間があいたことだし」という意味で言っていたのかは今となってはわからない。
北森氏は2010年1月25日、山口市内の病院であまりにも唐突に亡くなってしまったからだ。享年48歳。
北森氏が言ったことで忘れられない言葉がある。
「ばれなければ何やってもいい。ただし、ばれたときの責任はお前がぜんぶとれ」と。仕事上のアドバイスだ。北森氏は、会社をやめ際に僕がかけた言葉をきちんと覚えていた。
「おまえ『食えなくなったら出版社に営業して、仕事をとってあげる』って俺に言ってくれたよな」
北森氏は、僕のこの何気ない一言に、最後まで感謝していたそうだ。もちろん、北森氏が食えないとなれば、さんざんぱら出版社を秘書的にまわって営業する覚悟が僕にはあった。だが、悲しいかな、もう伝えることはできない。

北森氏が急に旅立たれてから、もう7年がすぎようとしている。
僕らがいた編プロは「中二時代」「中一時代」「中学三年生」という旺文社の雑誌を作っていた。そこのモデルだった女性がプロゴルファーになったときに、「もと雑誌モデルだった美人ゴルファー」として写真を週刊誌にもちこんだことがある。もちろん、本人に了承を得て、だ。
このとき「昔お世話になったモデルの過去の写真を週刊誌に売るのはどうか」とスタッフの中でただひとり反対したのが北森氏だ。
北森氏はよく「僕らは情報の被害者だ。僕らは情報の〝加害者〟にならないといけない。発信する側になって、その場所に居続けないとならないんだ」と強く言ってた。今僕は「記者」という立場でさまざまな取材をしているが、北森氏に見せても恥ずかしくない原稿を書きたいと思う。
そして今、北森氏に原稿のアドバイスをもらっていた僕は「僥倖」としかいえない時代をすごしていたのだとせつに思う。
北森氏にこう謝罪したい。
「嫉妬からあなたと距離をとってしまい、すみませんでした」と。
そして僕は、北森氏が学生時代からバイトしていたおいしい三軒茶屋の名店「味とめ」にこれからも何度も行き、北森氏の「生き証人」である女将さんから何度も彼の話を聞いて、うまい酒を呑むだろう。
それが僕にできる贖罪ですよ、北森先輩。先輩、またどこかで会いましょう。
生まれかわって、また仕事で組むことがあったら、今度は必ず「送別会」に出ますから(笑)。あのときの心が矮小だった僕を許してくださいね。
▼小林俊之(こばやし・としゆき)
裏社会、事件、政治に精通。自称「ペンのテロリスト」の末筆にして中道主義者。師匠は「自分以外すべて」で座右の銘は「肉を斬らせて骨を断つ」