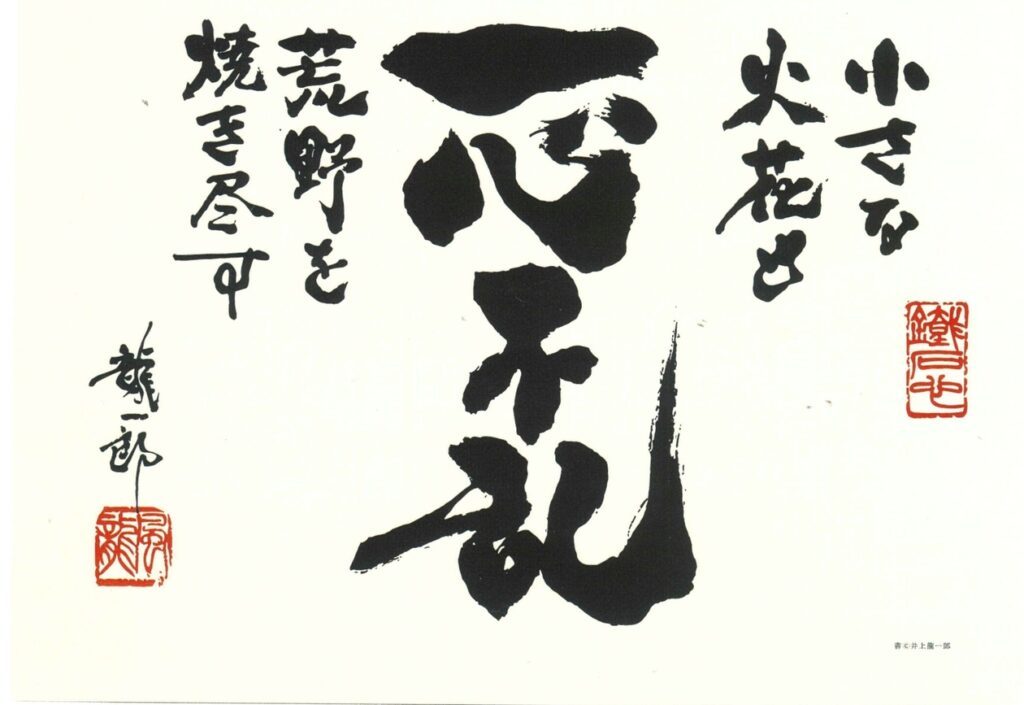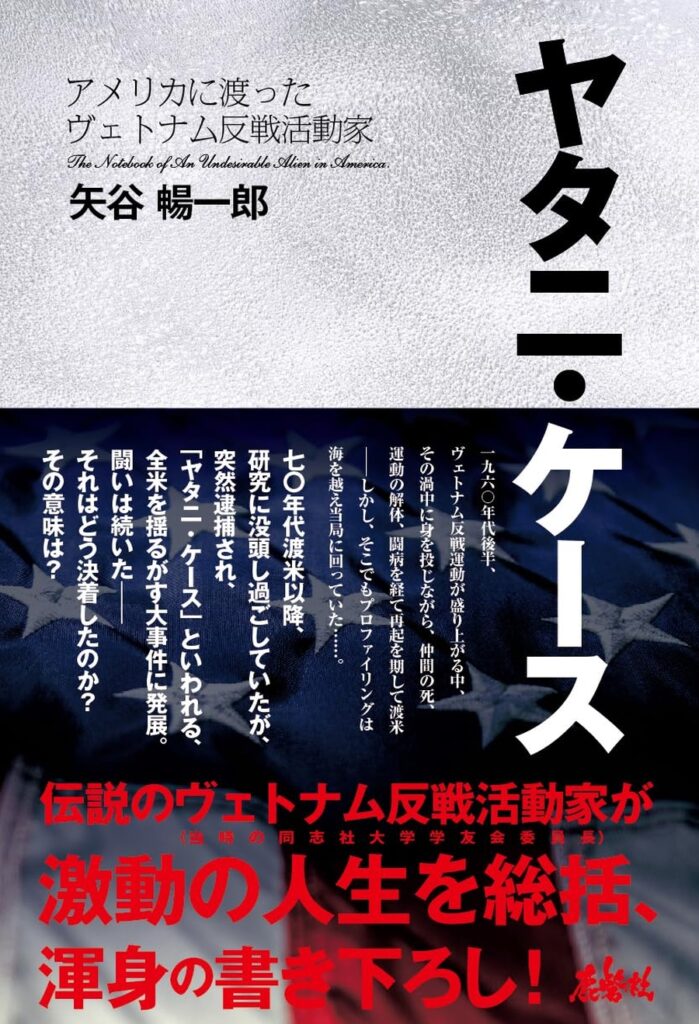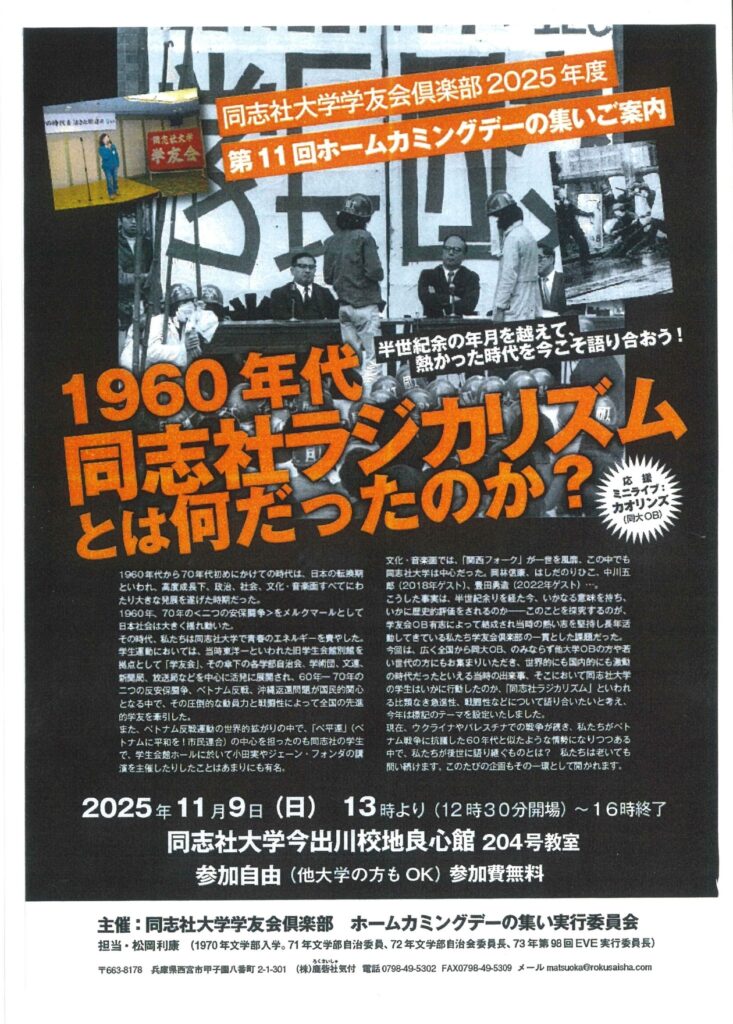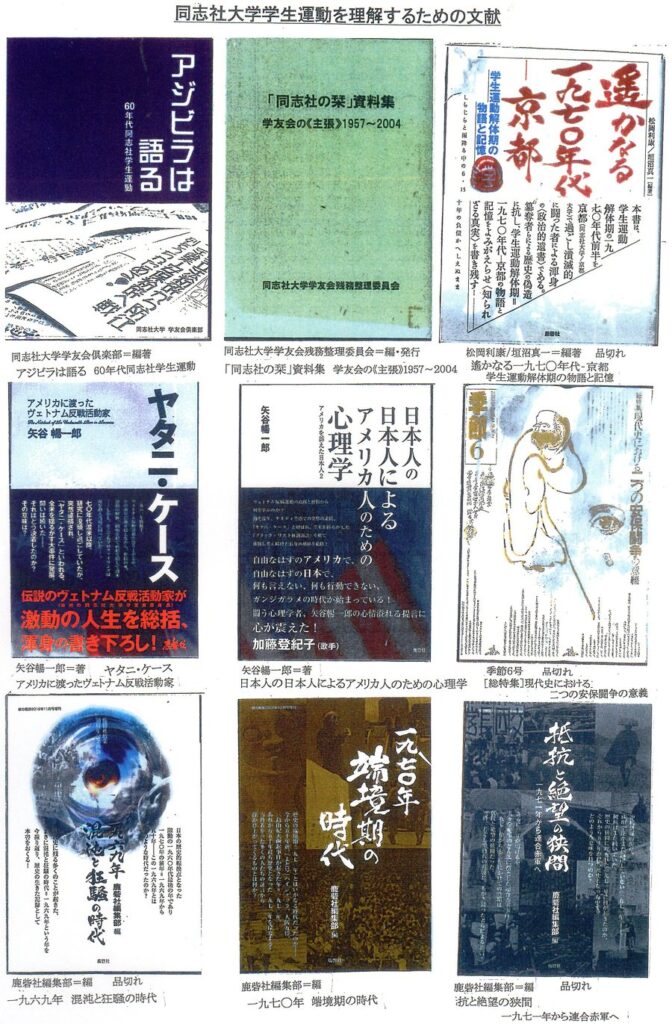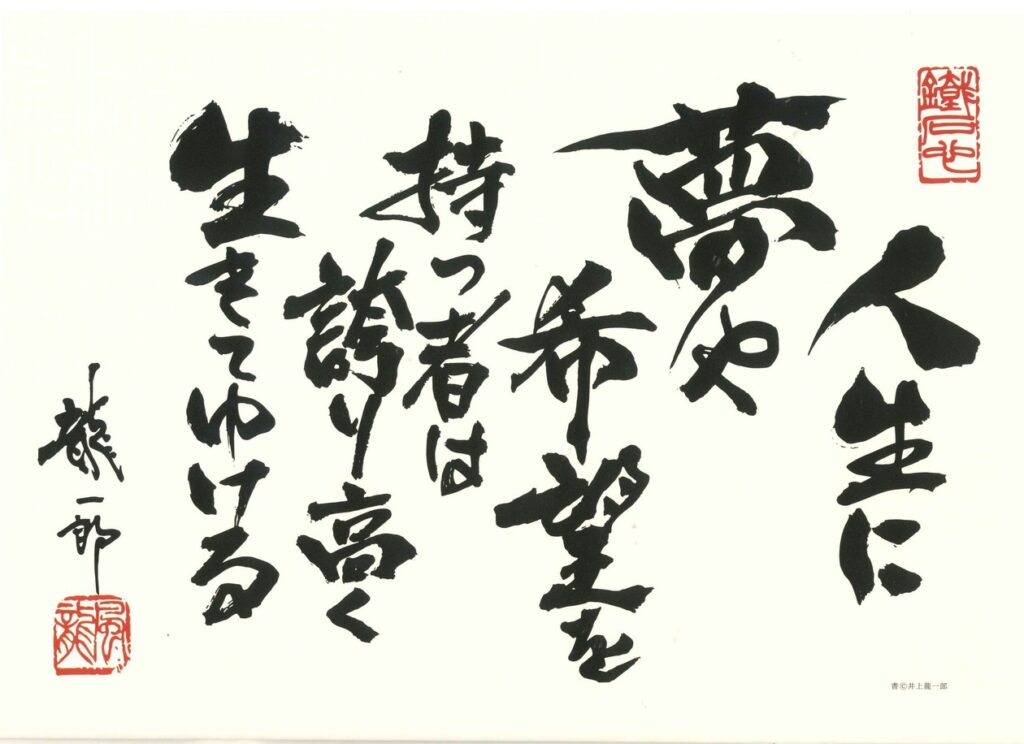私たちは『季節』の旗を守りたい!
『季節』を脱(反)原発言論の強固な拠点にしたい!
『季節』編集長 小島卓 鹿砦社代表 松岡利康
『季節』を愛し、また鹿砦社の言論・出版活動を支持される皆様!
『季節』2025冬号をお届けいたします。実際に寄稿や取材にご協力賜った皆様方、熱心な読者の皆様方、本誌『季節』は創刊10年(いわば“親誌”の『紙の爆弾』は20年)を経過し、発行継続困難な情況に直面しています。今号も発行が危ぶまれましたが、何とか発行に漕ぎ着けました。コロナ禍以降は、毎号発行が困難な中で、『紙の爆弾』もそうですが、心ある方々のご支援を仰ぎ資金を工面しつつ一号一号発行してきました。
私たち鹿砦社は、時代の転換点・1969年の創業以来半世紀余り、当初は時代を反映し裏切られたロシア革命史、また知られざる革命運動史(左翼エスエル、クロンシュタット叛乱、マフの運動など)、社会運動史の発掘に努め、80年代後半、松岡が経営を引き継いでからは社会問題全般、ジャニーズ問題(一昨年の英国BBCによるジャニー喜多川告発には、数年前から水面下で秘密裡に協力)などの芸能関係にまでウイングを拡げ(このことで前経営者からは「俺の顔にクソを塗った」と非難されました)、さらには2005年の親誌『紙の爆弾』創刊以来20年間、「名誉毀損」に名を借りた言論・出版弾圧(実際に松岡が逮捕、長期勾留されています)にも屈することなく、〈タブーなき言論〉の旗を掲げ続けてきました。
そうして、『紙の爆弾』が軌道に乗り経営が安定した2014年、本誌前身の『NO NUKES voice』(31号より『季節』に改題)を創刊し、常に一号一号3・11で被災、原発事故で被ばくされた方々に寄り添い発行を続け、この継続を図るために苦闘してきました。この年末がノルかソルかの正念場です!
本誌のみならず『紙の爆弾』も、あるいは当社の出版物全般もそうですが、コロナ禍を大きな契機として出版業界の情況が大きく変わり、これまでのやり方ではやって行けないことを実感させられました。しかし、いくつか新たな試行錯誤をしながらも、私たちがいまだに苦境から抜け出せずにいるのは、その本質と、想像以上の深度に気づくことができず、よって方途を見失い、具体的な出版企画に結びつけることができないからだと認識はしています。この5年間、突破口を探し模索と試行錯誤を続けています。皆様方に妙案があれば、ぜひお寄せください。
本誌『季節』も、『紙の爆弾』も、幾多の苦難(この最たるものは「名誉毀損」に名を借りた言論・出版弾圧)を乗り越え本誌は昨年10周年、『紙の爆弾』は本年4月で20周年に至り、多くの皆様方に祝っていただき、また厳しい叱咤激励も受けました。多くの雑誌が権力のポチと化し、『季節』や『紙爆』のようにタブーを恐れない雑誌がなくなったからでしょう。以後私たちは、次の10年に向けて歩み始めていますが、遺憾ながらなかなか苦境を打開できずにいます。
そうは言っても、師走に入り、ノルかソルかの勝負所、ここを断固突破しなくてはなりません! 先に発行し送付した『紙の爆弾』の定期購読者、会員の皆様方らにも申し上げましたが、断固突破する決意ですので、ぜひ皆様方のご支援をお願い申し上げます。そして、年を越し、東日本大震災から15年の来年3・11には新たな『季節』を発行し共に迎えようではありませんか!
季節2025年冬号
『NO NUKES voice』改題 通巻44号
紙の爆弾2026年1月増刊
2025年12月11日発行
定価770円(税込み)
《グラビア》キオクとキロク(鈴木邦弘)
小出裕章(元京都大学原子炉実験所助教)
《報告》生命体の世界と原子核の世界
樋口英明(元福井地裁裁判長)
《報告》未来の人々から裁かれないために
井戸謙一(311子ども甲状腺がん裁判弁護団長)
《報告》311子ども甲状腺がん裁判にご支援を
《特集》福島の汚染土と汚染水の行方
山川剛史(東京新聞編集委員)
《報告》被災地の現実はどれほど報道と違うのか
鈴木邦弘(絵本作家/イラストレーター)
《報告》キオクとキロク
まさのあつこ(ジャーナリスト)
《報告》汚染土政策の変遷 「最終処分」から「復興再生利用」
和田央子(放射能ゴミ焼却を考えるふくしま連絡会)
《報告》放射能汚染土の核心的問題
平井 玄(新宿御苑への放射能汚染土持ち込みに反対する会)
《報告》放射能のない新宿「御苑」をコモンズに
門馬好春(「三〇年中間貯蔵施設地権者会」会長)
《報告》中間貯蔵施設の汚染土の行方
菅野みずえ(「ALPS処理汚染水差止訴訟」原告)
《報告》ALPS処理汚染水を海に流すな
吉澤正巳(「希望の牧場・よしざわ」代表)
《インタビュー》原発事故の暴虐に「いのち」を対峙
被爆した牛たちを飼い続けて闘う
水戸喜世子(「子ども脱被ばく裁判の会」共同代表)
《インタビュー》『3・11の彼方から』を読む
村田三郎(医師)
《インタビュー》弱者の側に立ち、反核・反原発を闘う《後編》
末田一秀(『はんげんぱつ新聞』編集長)
《講演》エネルギー基本計画 暮らしへの影響
山崎久隆(たんぽぽ舎共同代表)
《報告》柏崎刈羽原発の再稼働に異議あり!!
後藤政志(元東芝・原子力プラント設計技術者)
《報告》原発の技術的特性と裁判の論理〔2〕
古居みずえ(映画監督)
《報告》パレスチナと福島に通い続けて
森松明希子(原発賠償関西訴訟原告団代表)
《報告》福島から広島へ 「核被害者の権利宣言2025」が灯した希望と連帯
木村三浩(一水会代表)×板坂 剛(作家/舞踊家)
《対談》民族派と左翼の融合は可能か《前編》
三上 治(「経産省前テントひろば」スタッフ)
《報告》今、我々の置かれた場所から
原田弘三(翻訳者)
《報告》「脱炭素」の不都合な真実
再稼働阻止全国ネットワーク
《報告》危険な東海第二原発を阻止!
「原発依存社会」へと暴走する高市政権を批判する!
瀬尾英幸(北海道泊村在住)
志田文広(とめよう!東海第二原発首都圏連絡会世話人)
けしば誠一(反原発自治体議員・市民連盟事務局長)
藤岡彰弘(廃原発watchers能登・富山)
木原壯林(老朽原発うごかすな!実行委員会)
木村雅英(再稼働阻止全国ネットワーク)
天野恵一(再稼働阻止全国ネットワーク)
《反原発川柳》乱鬼龍 選