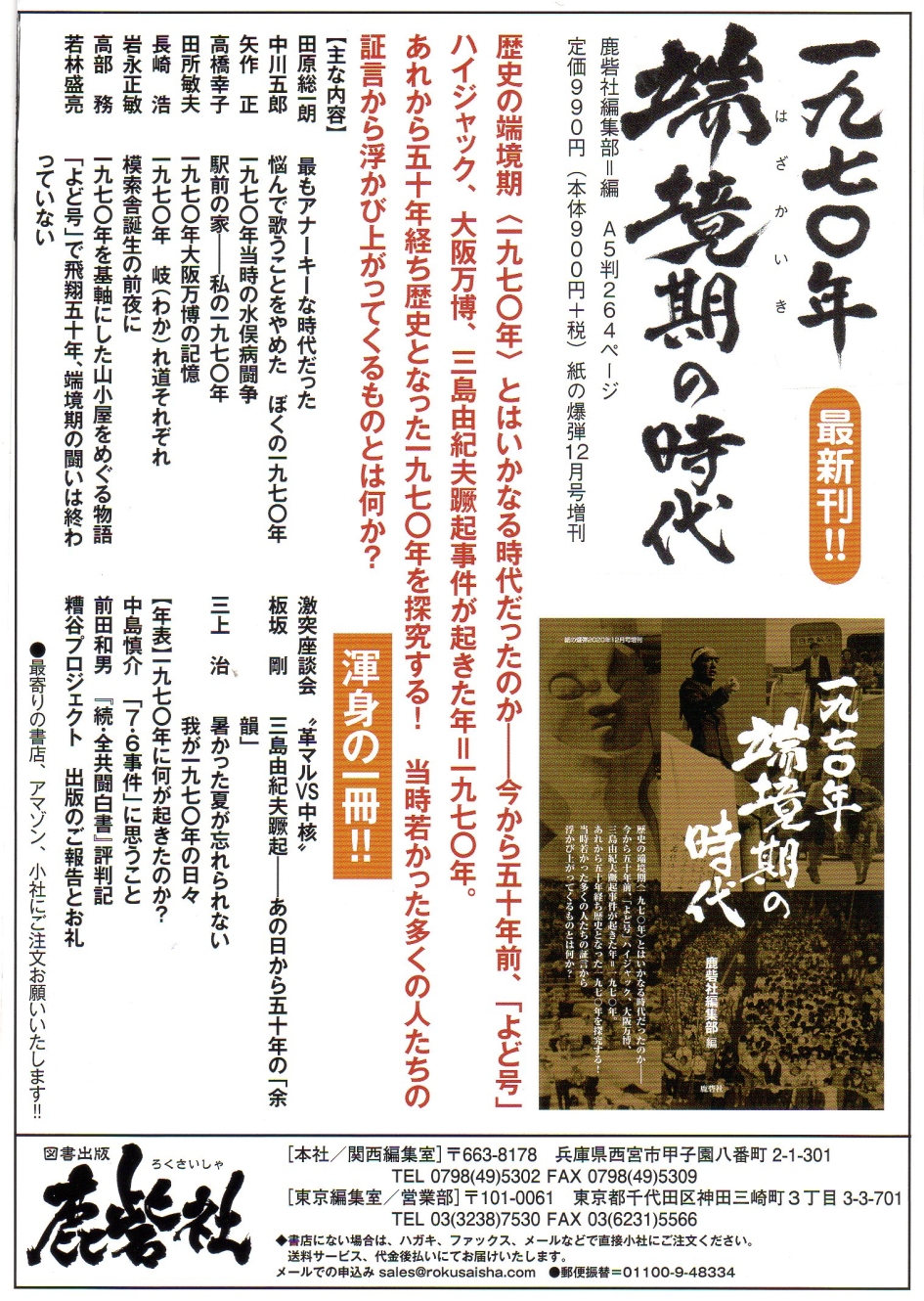昨年10月7日パレスチナ自治区であるガザを支配するハマス(「イスラム抵抗運動」)がイスラエルを侵攻してから1周年を迎えた。周知のように、イスラエルは「自衛権の行使」だとしガザ地区に連日、空爆を行い、ガザ地区の占領をおこなった。この一年で4万2千人のパレスチナ人が犠牲になった。主に女性、子供たちだ。さらに1万余りの人々が収容所に拘束されている。生き延びた人々は飢餓と薬不足に苦しんでいる。
また、戦禍はレバノンにもおよびイスラエルの空爆により数千名が犠牲になっている。イスラエルはイラン滞在中のハマス最高指導者ハニヤ氏をミサイルで殺害し、レバノンのヒスボラ指導者ナスララ師ら幹部20名も地下施設を破壊する強力な爆弾で犠牲にした。その報復として、イランが180発の弾道ミサイルでイスラエルを攻撃した。イスラエルはヨルダンにたいする地上侵攻をすすめる一方、イランにたいする報復をいかにおこなうかについてアメリカと協議したうえ、原油施設を攻撃した。
こうして、この一年の間にイスラエルは侵略戦争を拡大させている。世界はいつイスラエルの侵略をやめさせることができるかを憂いている。日本政府はイスラエルの空爆に憂慮を示しているが、アメリカのイスラエル支援を容認したままだ。
◆ハマスの攻撃はパレスチナ人民の総意であり、衰退するアメリカ覇権勢力にたいする先制的な打撃を与えるもの
ここでハマスの攻撃の意義をよく見ることが重要だと思う。ハマスを「テロ組織」、ハマスを支持するパレスチナ人をテロ分子だとする考え方がアメリカをはじめG7諸国で基調となっている。1年前のハマスのイスラエル攻撃をその最大のテロ行為だと声を上げて非難している。
しかし、イスラエルが英米の支援のもとで1948年パレスチナの地に国家を建て、450万人ものパレスチナ人が追放され、ガザ地区と西岸地区に壁で囲まれた青空だけがある天井のない監獄のような場所に閉じこめられ、シリア、レバノン、ヨルダンなどアラブ諸国の難民キャンプで流浪生活を余儀なくされてきた。
一方、イスラエルは四次に亘る中東戦争とたえざる植民を通じて領土を拡大してきた。イスラエルは侵略と略奪のなかに生まれ肥え太ってきたが、そのイスラエルは英米が中東地域を抑えるための覇権主義の拠点であるということができる。
抑圧があるところに反抗と戦いが生まれるものだ。それゆえ、ハマスのイスラエルにたいする抵抗と攻撃はパレスチナ国家創建をめざすパレスチナ人民の正義の戦いであるといえる。その戦いのなかでハマスが生まれ、ガザを支配するまで強化された。
自己の主権国家の創建をめざすパレスチナ人民の戦いは単にイスラエル国家にたいする戦いだけではなく、イスラエルを軍事経済的に支援するアメリカをはじめとする欧米覇権勢力との熾烈な戦いが伴っている。2国間共存を謳ったオスロ合意は、イスラエルのラビン首相の暗殺とシャロン政権により踏みにじられた。欧米諸国は「二国間共存」を言ってきたが、イスラエルの植民地主義を庇護、支援してきたので、パレスチナ国家が創建されないどころからパレスチナ人民はいっそう悲惨な奴隷の境遇におかれてきた。
それゆえ、ハマスのイスラエル侵攻はパレスチナ人民の正義の戦いであるといえる。かつ、ウクライナ戦争が長期化し、NATO側の敗色が濃くロシア側が攻勢を強めている時期にあって、しかもサウジアラビアがイスラエルとの国交交渉がおこなわれパレスチナ問題が忘れかけられようとした時、ハマスは果敢な攻撃をしかけた。それはアメリカの対ロシア、対中国の戦線を対パレスチナという3正面作戦に引きずりだすという意義をもち、衰退するアメリカ覇権主義をさらに危機に追いつめるものだった。
かつてイスラエルとパレスチナの戦いはイスラエル(ユダヤ)の大義とアラブの大義の対立だと言われ、アラブ民族主義を掲げたエジプト、シリアなどが中東戦争の前面に立ったが、今は反米自主をかかげるハマスとともにイランとヒスボラ、イエメンのフーシ派が「抵抗の枢軸」を結成し反イスラエル戦争の前面にたち、覇権主義と反覇権主義の鋭い対立の場をなしている。
◆イスラエル侵攻拡大は反イスラエルの戦いを起こすだけ
イスラエルはこの一年間、「自衛権」を掲げ、ガザにたいする無差別空爆と地上侵攻をおこない、レバノンにたいする無差別爆撃と地上作戦をおこなってきた。ハマスの侵攻を許してしまった「汚名」の雪ぎであり、「復讐」だ。イスラエルは「目には目、歯には歯」どころか、イスラエル人1名が殺されれば100人、1000人殺していく悪鬼と化している。イスラエル国内ではパレスチナ人をすべて殺せという世論が支配しているという。その戦火を拡大していく姿は、あたかもかつて反日勢力にたいし懲罰を加えるという口実で侵略戦争を拡大していった日本軍国主義やナチスドイツを想起させる。それを後ろから支え、督促しているのがアメリカ覇権帝国だ。
しかし、イスラエルが無差別爆撃と地上侵攻を拡大していけばいくほど、人々の反イスラエル感情を燃え立たせ反イスラエル勢力を強化していくことになり、世界からイスラエルは孤立を深めることになる。それゆえ、ハマスやヒスボラの壊滅はありえない。イスラエルは侵攻するたびに反イスラエル戦士を生み出しているからだ。
言うまでもなく、パレスチナ問題の解決はパレスチナ人民が望み、国連をはじめ圧倒的大多数の諸国が求めているパレスチナ国家の創建だ。しかし、それを妨害しているのは覇権主義国家であるイスラエルであり、パレスチナの国連加盟に唯一反対しているアメリカだ。アメリカは口先でパレスチナ国家を認めるが、実際にはパレスチナ国家を認めないイスラエルを支援することによってパレスチナを犠牲にしている。
パレスチナ国家の創建は、これまでの暫定自治政府(西岸地区、ガザ地区)だけではなく、イスラエルが植民化したパレスチナ領土を回復した国家の建設であり、それをイスラエルが認め、不当に占領した地域(ゴラン高原など)から撤退し、パレスチナ国家との友好平和協定を締結することだと思う。そのためには、イスラエル自体が覇権主義を放棄し、平和国家に転換しなければならないだろう。それはユダヤ人自身が決める問題だ。イスラエルが侵略と占領を放棄しないかぎり、パレスチナの抵抗と戦争が終わることがないだろう。
イスラエルはイランをはじめ戦争を拡大していけば、中東情勢は極度に不安定になる。アメリカは中国を最大の戦略的競争相手と位置づけ、その包囲と弱化に集中させようとしており、中東での戦乱拡大を望まず収拾しようとしている。アメリカ主導の停戦の動きがはじまっている。しかし、戦乱の根源であるイスラエルが覇権主義をやめないかぎり、反イスラエルの戦いが起こりつづけ戦乱が収まることはないし、アメメリカは中東での戦乱の泥沼から抜け出ることができないだろう。
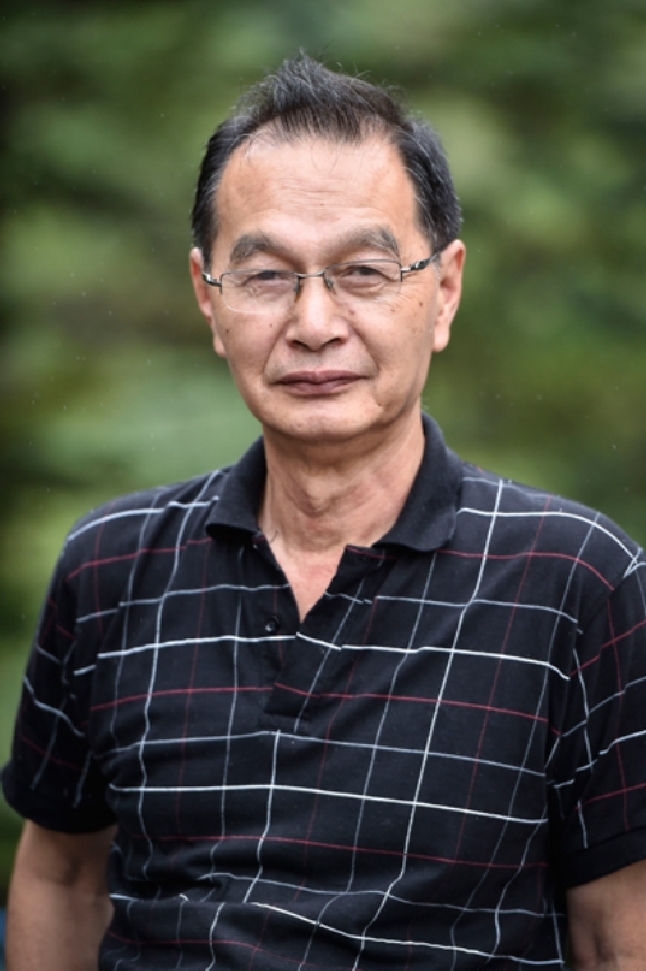
◆問われる日本の対米追随
日本にとって中東情勢の緊迫は、たんに石油やスエズ運河の物流問題だけではない。覇権主義と反覇権主義の戦いでアメリカの覇権主義勢力につくのか、世界の潮流をなしている反覇権主義、自国第一主義勢力の側に立つのか、するどく問われている。いいかれば、日米同盟機軸で覇権の側にたちこのまますすむのか、アジア諸国、とりわけ中朝露との平和的友好関係を構築して日本の非覇権の新しい道を拓いていくのかだ。
アメリカはウクライナ、パレスチナ、中国で三正面対決を迫られ、米覇権の崩壊に直面している。アメリカに従っていくことは、対中代理戦争国家として崩れゆく覇権主義を支える無駄な抵抗でしかなく、日本の滅亡しかない。世界の趨勢である反覇権、脱覇権の自国第一主義の道に進んでこそ、日本の恒久的な平和と繁栄があるだろう。
しかし、岸田政権以降、わが国は「日米同盟新時代」をかかげ対中代理戦争をになうべくミサイル基地の建設、弾薬庫拡充、港湾空港の戦時利用態勢、さらに核ミサイル配備まで容認しようとしている。アメリカの代理戦争の先には、アジア人同士で戦い日本の滅亡があるということは目に見えている。
アメリカに従い戦争の道に進むのか、それとも非戦平和の自国第一の道にすすむのか、その岐路あって脱覇権の根本的な新たな転換をめざしていくことではないだろうか。
▼赤木志郎(あかぎ・しろう)さん
大阪市立大学法学部中退。高校生の時は民青、大学生のときに社学同。70年赤軍派としてハイジャックで朝鮮に渡る。以来、平壌市に滞在。現在、「アジアの内の日本の会」会員