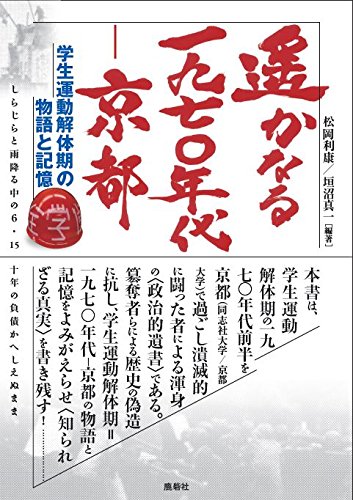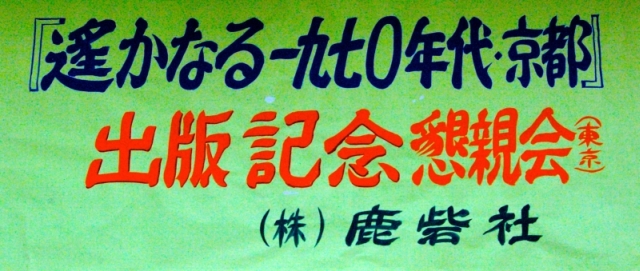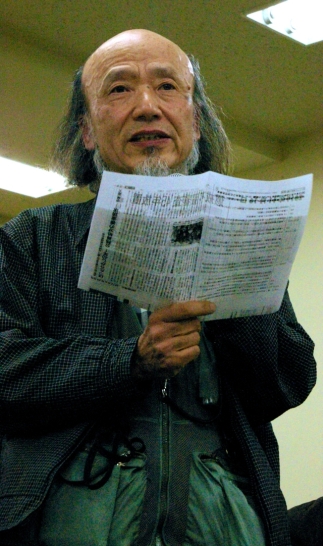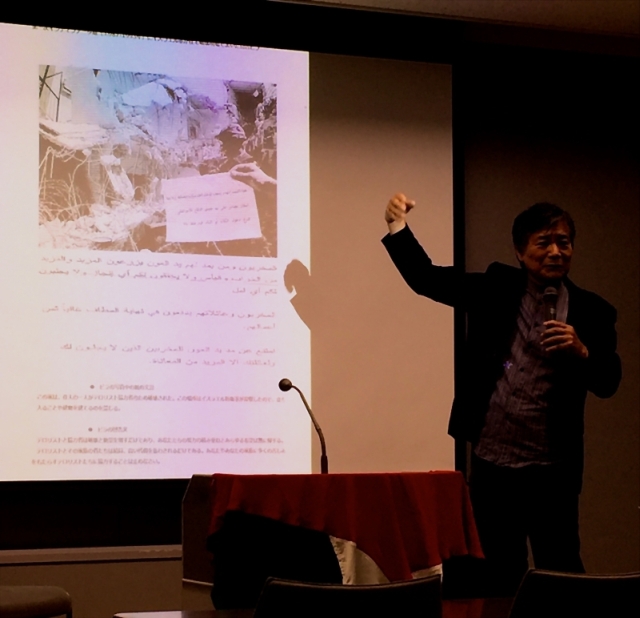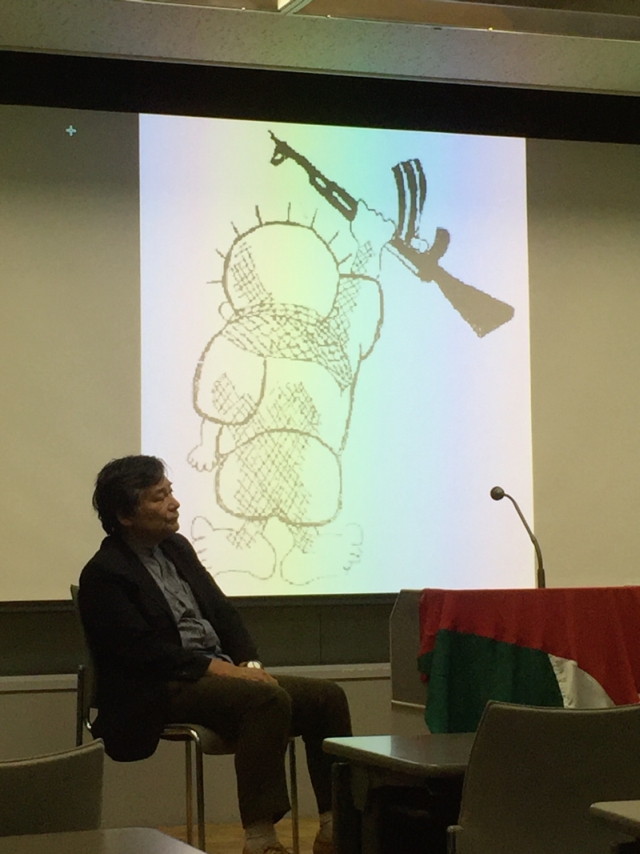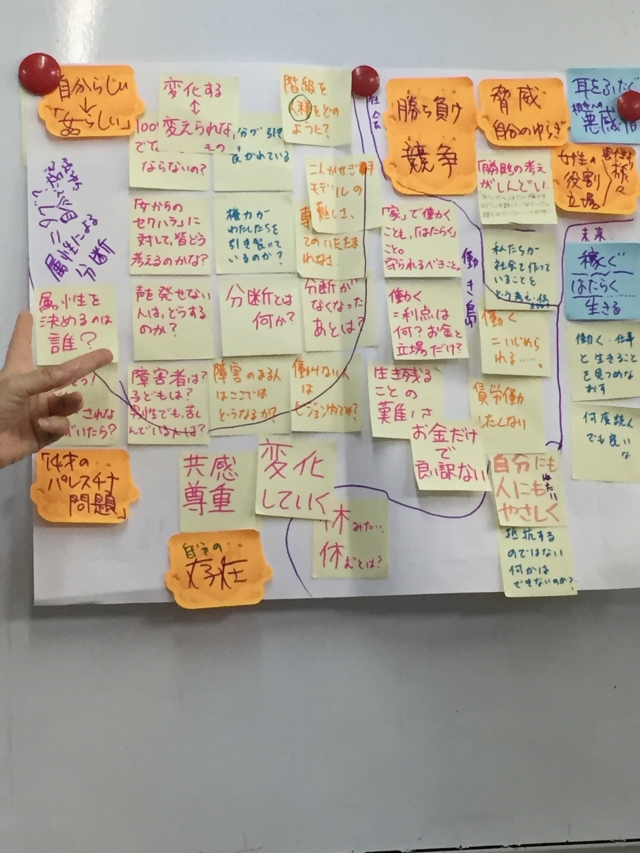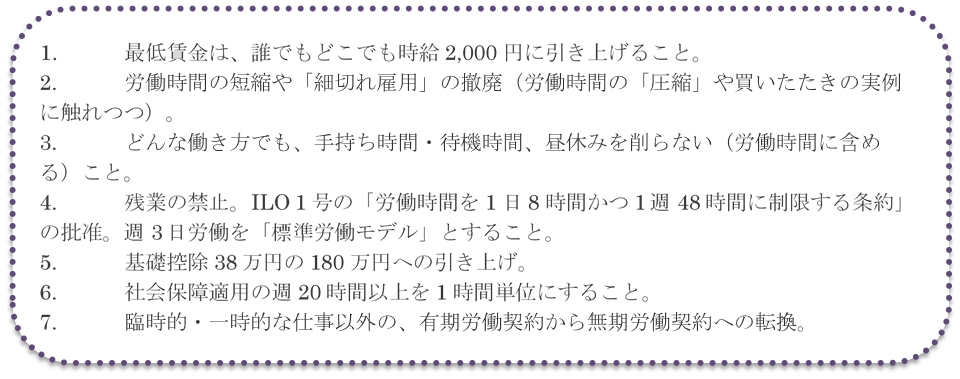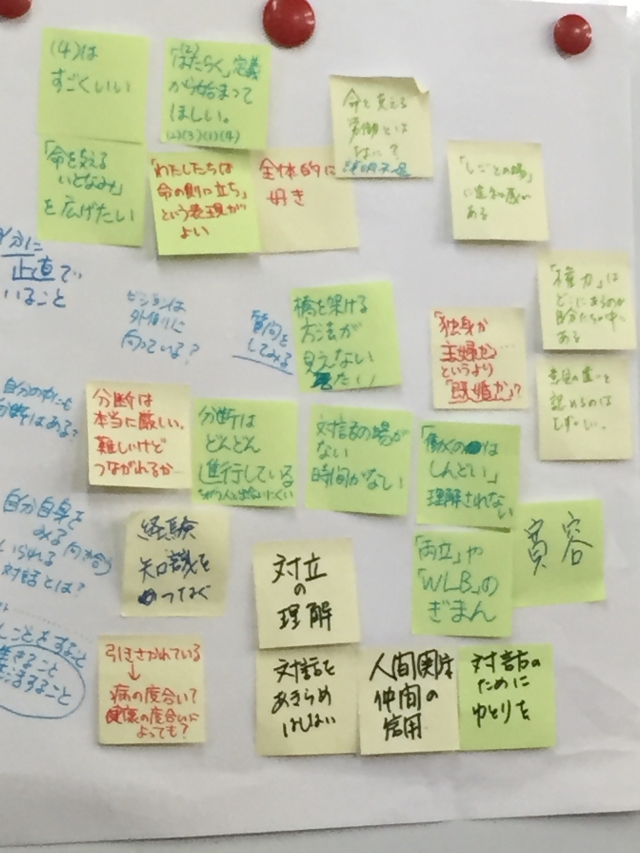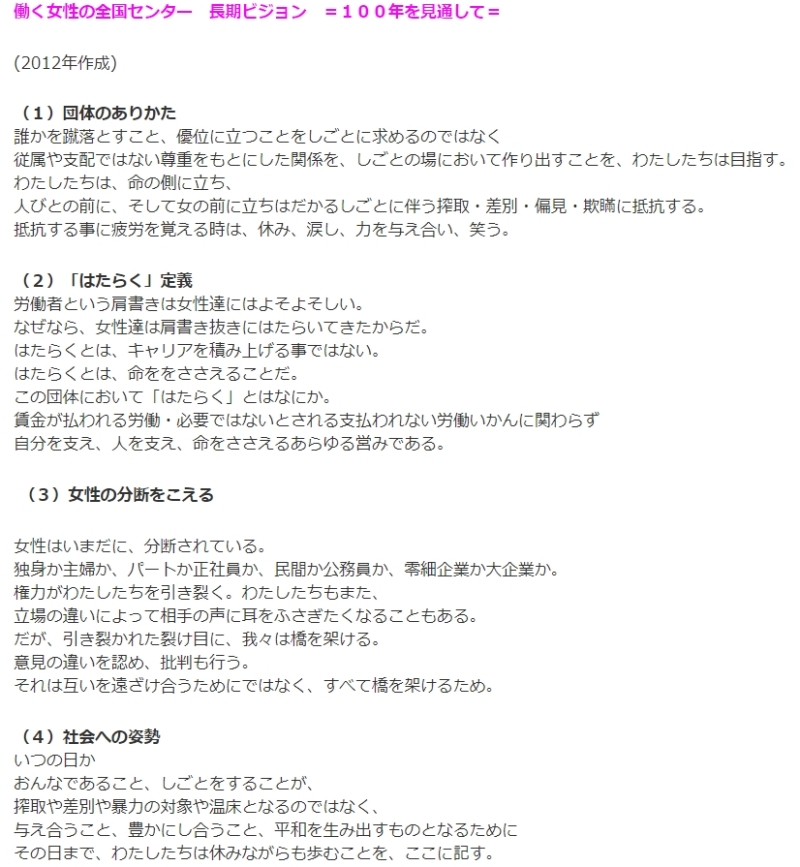本年も、よろしくお願いいたします。今年こそ、社会の問題に対し、現実的に一矢報いるところから始める所存。
さて最近、書籍の話題を取り上げてきたが、今回は新年の話題としてもっともふさわしくない「人間の悪魔的な部分」「毒気」について考えざるを得ないような、韓国の劇映画を紹介したい。

◆韓国と日本の「強制入院」
作品は、2016年に韓国で実際に起きた拉致監禁事件をモチーフとした『消された女』。プレスシートによれば、「韓国では、精神保健法第24条を悪用し、財産や個人の利益のために、合法的に健康な人(親族)を誘拐し、精神病院に強制入院させる事件が頻繁に起こり、社会問題になっていた」という。たとえば、医師が自らの息子を、資産を守るために夫が元妻を、離婚のために夫が妻を強制入院させた。「精神保健法第24条」とは、「保護者2人の合意と精神科専門医1人の診断があれば、患者本人の同意なしに『保護入院』という名のもと、強制入院を実行できる」ものだそう。韓国公開後の16年9月、憲法裁で精神疾患患者の強制入院は、本人の同意がなければ憲法違反という判決がくだった。
調べると、日本の措置入院も、都道府県知事への通報等があること・調査の上措置診察の必要があると認めること(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律27条1項)、診察の通知(28条)を経て、指定医2名以上の診察の結果が「精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認める」ことで一致すること(29条2項)などによって措置入院が可能となっているようだ。
ただし、「自傷他害のおそれがある」という文言を拡大解釈して常習犯や「触法(犯罪を起こした)精神障害者」などによる犯罪その他の触法行為の予防のための拘禁の代用としてこの制度が使われる危険性があり、犯罪として処罰するためには立法府が制定する法令において犯罪とされる行為の内容・刑罰を規定しておかなければならないとする罪刑法定主義の原則との兼ね合いが問題になっているという。
また、措置入院以前でも、医療保護入院(33条)の家族等による悪用があるようだ。権力が強まり、「中世」とすらいわれる現在の社会状況をかんがみても、また監禁事件などの報道をよく目にすることを考えても、背筋が寒くなる話であり、本作のテーマを対岸の火事と思っている場合ではないかもしれない。

プレスシートには、精神疾患者たちの平均入院期間は韓国が極端に長期にわたっていると説明されていた。なぜか日本が取り上げられていなかったので、気になり、これも調べてみた。すると、「第8回 精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針等に関する検討会」(2014年3月28日)の参考資料が見つかった。そこに示されている「精神病床の平均在院日数推移の国際比較」グラフのたとえば2010年のデータを見ると、諸外国が50日程度までにおさまっているのに対し、韓国が100日を超えており、ここ20年間なんと日本がダントツで500日からようやく300日程度まで下がってきたということだ。強制入院に限ればまた異なるのかもしれないが、まったくいったいこれはどういうことなのかと考えなければならない。資料に続けて目を通せば、通常の身体的な病気同様、退院を促すというスタンスはあるようだが、精神的な負担が多い社会なのか、それとも入院させ続けがちな社会なのか、その両方なのか、ほかにも原因があるのかなど、不勉強な筆者には気になることばかりだ。
だが、再びプレスシートを読んでいくと、「1日10件を超える強制入院が発生している韓国の現実」などと書かれている。そこでまた日本のデータを調べ、厚生労働省のデータを見る。「精神障害者申請通報届出数、措置入院患者数及び医療保護入院届出数の年次推移」の2014年度では申請通報届出数24,729件、措置入院患者数1,479人、医療保護入院届出数170,079件(一部を改正する法律の施行により、保護者制度が廃止され、医療保護入院の同意者が従来の保護者又は扶養義務者から、家族等のうちいずれかの者となった)で、全体としては措置入院患者数が減っているが、医療保護入院届出数が増えている。別の「医療保護入院患者数の推移(年齢階級別内訳)」の資料を見れば、131,924人となっている。単純に比較できるデータが出て来ないのでなんともいえないが。

◆「真実に基づいた映画は、世間の注目を集めるために必要であると信じている」
本映画作品に戻ると、そのあらすじは、こうだ。白昼、都市で、カン・スアという女性が誘拐され、「精神病院」に監禁される。彼女が強制的に薬物を投与され、暴力をふるわれる日常を書き留めた手帳は、ナ・ナムスというTVプロデューサーの男性に届けられた。彼は、殺人事件の容疑者として収監されていた彼女と出会うことになるが……。
韓国でも、実際の殺人事件を取り上げた『殺人の追憶』『殺人の告白』、暴行事件を取り上げた『トガニ 幼き瞳の告発』『ハン・ゴンジュ 17歳の涙』などの作品があり、いずれも評価が高い。
ところで最近、長女を両親が監禁したと思われる「寝屋川監禁事件」、金銭トラブルが原因とされ4人目が逮捕された「茨城・牛久の切断遺体事件」、宮司殺害など3人が死亡した「富岡八幡宮」の事件、アパートで9人の遺体が見つかった「座間殺害事件」など、以前であればもっと騒がれていたようにも思われる凄惨な事件の報道がいくつかあった。筆者は先日、「北九州監禁殺人事件」についてのネットの記述を一晩中読んでしまった。
イ・チョルハ監督は、「いくつもの私設精神科病院にはびこる悪行について語りたかった」「物語を展開することによって、社会から保護されていない犠牲者たちについて語りたいと思った」「真実に基づいた映画は、世間の注目を集めるために必要であると私は信じている」という。ちなみにナ・ナムス役のイ・サンユンは最新ドラマ『二度目の二十歳』などではソフトな魅力を打ち出しており、ファンの方も本作の緊張感あふれる演技を新鮮に楽しめるだろう。ほかにも人気俳優たちがキャストに名を連ねている。
人間には、自らを守るためなのか、悪魔というか毒気にとりつかれるような性質があったり、ある環境や関係性に追いこまれればそのような性質があらわとなるような面があったりするのではないだろうか。生きながらにして互いに地獄に陥らないために、たとえば制度の問題があればそれを是正し、極力オープンな状態を保てるような仕組みをつくったり、対立する利害を対話で解決できる仕組みもどんどんつくったりそれがきちんと用いられたりするようにみんなでし続ける必要があるのかもしれない。
まずは本作をご覧になってみては、いかがだろう。
◎『消された女』公式サイト http://www.insane-movie.com/
原題:날, 보러와요(『私に会いに来て』) 英題:INSANE
監督:イ・チョルハ 出演:カン・イェウォン、イ・サンユン、チェ・ジノ ほか
字幕翻訳:金 仁恵 提供:キングレコード 配給・宣伝:太秦
【2016年/韓国/カラー/91分/シネマスコープサイズ/5.1ch/DCP】
2018年1月20日(土)より、シネマート新宿・シネマート心斎橋ほか全国順次公開
◎[参考動画]映画『消された女』予告編(uzumasafilm 2017/12/22公開)
▼小林蓮実(こばやし・はすみ)[文]
1972年生まれ。フリーライター。労働・女性運動等アクティビスト。『現代用語の基礎知識』『情況』『週刊金曜日』『現代の理論』『neoneo』『救援』『教育と文化』『労働情報』ほかに寄稿・執筆。
『紙の爆弾』
●〈2月号〉【特集】2018年、状況を変える8「『よど号』メンバーに聞く 日米安保路線見直しで 日朝国交正常化へ」
●〈1月号〉決死の覚悟と不屈の精神をもつ従軍慰安婦とされた女性たち 寄稿
●〈1月号〉対米従属「永久化」今こそ日米関係を根本的に見直せ! 天木直人さんインタビュー 構成
『NO NUKES voice vol.14』
●[報告]「生業を返せ! 地域を返せ!」福島原発被害原告団・弁護団「正義の判断」寄稿
●[インタビュー]淵上太郎さん(「経産省前テントひろば」共同代表)
〈反原発の声〉を結集させ続ける 不当逮捕を経たテントひろば 淵上さんの「想い」 取材・構成・撮影
●[インタビュー]松原保さん(『被ばく牛と生きる』映画監督)
福島は〈復興〉の「食い物」にされている 取材・構成・撮影