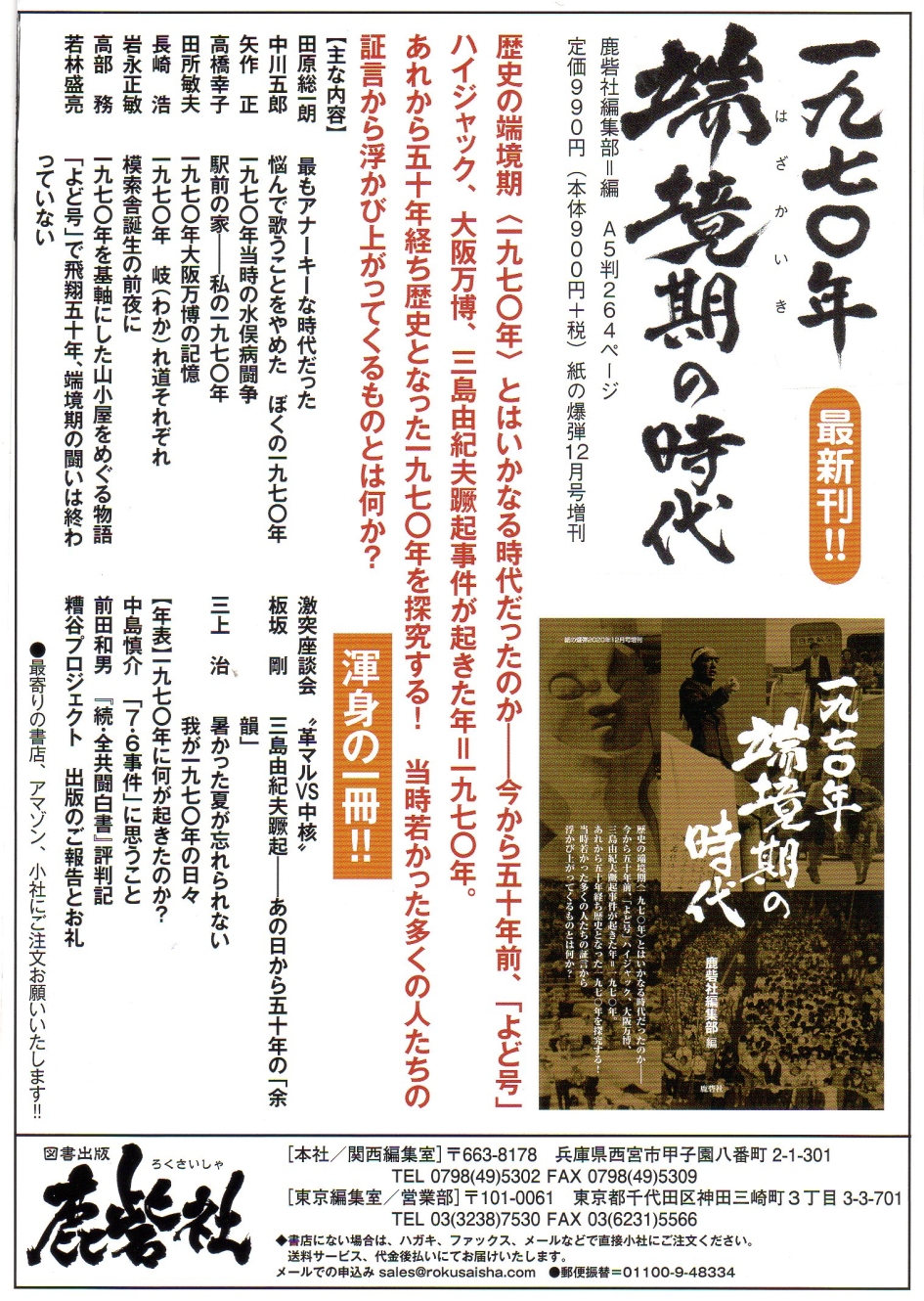今、世界的な物価高騰が起きている。とりわけ、「ウクライナ事態」発生以降、ロシアに対して経済制裁する国々では、ロシアからの石油、ガスの供給が滞り、それによってガソリン価格や電気料金が高騰を続けており、まさに「返り血を浴びる」状況になっている。
こうした状況の中で、日本では、「サハリン2」の問題が起きている。
6月30日、プーチンは「サハリン2」の経営会社である「サハリン・エナジー社」の資産を新設するロシア企業に無償で引き渡すよう命令する大統領令に署名した。「サハリン2」は英石油メジャーのシェルが27%を出資して経営を握っており、日本も三井物産が12.5%、三菱商事が10%の出資をしていた。日本は、これを通じて全LNGガス輸入量の約10%、年間600万トンを得ていた。ロシアの措置は、それが得られなくなる可能性があるというので緊張が走った。
その後、ロシアは8月2日に新会社(会社名は「サハリンスカヤ・エネルギヤ」、本社所在地はサハリン州のユジノサハリンスク)を設立した。8月18日には、供給を受けている九州電力、東京ガス、西部ガスなどに以前と同じ価格や調達量で再契約を結ぶという通達を行った。これによって、日本の2商社も同様の条件になることが予想され、西村経産相は、「日本の権益を守りLNGの安定供給が図られるよう官民一体で対応したい」と述べ、9月4日の期限までに、2商社に株式保有をロシア側に通知するよう要請した。これを受けて、8月25日、三井物産、三菱商事は出資継続をロシア側に通知することを表明した。今後、数ヶ月間に渡って再契約の中身をつめる交渉が行われる見通しだ。
問題は米国である。米国はロシア制裁のために、シェルの撤退を歓迎し、日本にも同様の措置を採るように要請していた。そうした米国にとって、今回の日本の措置は不愉快なものであり、再契約の交渉過程でも「サハリン2」から撤退するように様々な圧力を掛けてくることが予想される。
今後、日本政府は、国益を守るのか、それとも米国の圧力に屈するのかの選択を迫られることになる。すでにマスコミは、「権益を守れるかどうかは不透明」などと米国を利するかのような論調を張るが、「サハリン2」からの撤退こそ国益放棄なのであり、日本は「撤退せず国益を守る」という立場で、ロシアとの交渉に臨めばよい話しである。
ロシアは、そうしたことを見越して、今回、穏やかに「以前通りの契約で」という措置をしたのであり、それは、日本に「あくまでも米国について行きますか、どうしますか」を問うものになっていると言える。その問いかけは、本質的に「日本はあくまでも米国に従い、米国覇権の下で生きていくのですか」という問いかけである。
そのことを知るためには、「サハリン2」とはどのようなものであったかを分かる必要がある。
「サハリン2」は、1994年に作られた。当時は、ソ連崩壊という大混乱の中で、市民生活が極度の貧困にさらされたロシアの試練の時代であった。そうした混乱の中で、作られたものが「サハリン2」である。こうして英国の石油メジャーであるシェルが27%を出資して、サハリンのガスを掌握した。シェルはロシアのガスを安く買い叩いたばかりでなく、100万BTU(英国熱量単位)当たり2ドルに満たない額で買うというポート・フォリオ枠の特典を得て、これを40ドル前後のスポット価格で売るなどして暴利を貪ってきた。本社は、タックス・ヘイブン(税の優遇措置)で有名な英領バミューダ諸島に置かれており、ロシアは、これに課税することもできなかった。
まさに、「サハリン2」は、米国覇権秩序の下で欧米の大企業が他国の資源を収奪するという典型例であり、ロシアにとっては屈辱的なものであった。それを「ウクライナ事態」が発生し、ロシアへの制裁が発動される中、2月にシェルが自ら撤退を表明したのを機にロシアが取り戻したのであり、それは、誰もが文句を付けることのできないロシアの主権行為であり、屈辱の遺物を清算し、自国の資源をロシアに取り戻すための極めて正当な措置である。
そればかりではない。ロシアは、米覇権秩序に反対し、「平等で民主的な新しい世界秩序」の形成を主張しており、新会社設立の措置は、その象徴であり、そのための武器としてあるということである。
すなわち、こうして作られた新「サハリン2」は、日本に「米覇権の下で生きる」という生き方に対して、それをいつまでも続けるのか、それでいいのか、を問いかけるものになっているということなのだ。
日本は、ロシアの穏やかな問いかけに、冷静に、その答えを模索して行かなければならないだろう。
その基準は、国益であり、国民益でなければならない。どうすれば、国益、国民益を守り、国民の命と暮らしを守っていくのか、国家の使命とは、それに尽きるからである。
米国覇権の下で生きて行く、そのためにロシア制裁の先頭に立つということは、逆に「返り血」を浴び、それを国民に転化するだけではないのか。まさに、それが故に、多くの国が国益、国民益を第一にして、ロシア制裁に反対し、それを無視している。バイデンが多くの国際会合や会議で、ロシア制裁を呼びかけても、それに応じるのはG7の欧米日だけである。G20でも、ロシア制裁を行っているのは10カ国に過ぎない。
こうした動きについてエジプトの元外務次官のフセイン・ハリディ氏が「どちらにも、つかない」と題する朝日新聞への寄稿で要旨次のように言っている。「我々は欧米の言うようにウクライナの独立と民主主義を守る戦いだとは見ていない。そういう中でエジプトなど『第三世界』の国々は自らの立ち位置を決めなければならない。それは『非同盟』だ。非同盟はバンドン会議で始まり、インドのネール、中国の周恩来、エジプトのナセルなどが主導した。非同盟は自国の独立を守るための盾である」と。
バンドン会議は、1955年、東西冷戦が激化する中で、アジア、アフリカ諸国が、インドネシアのバンドンに会して、東西どちらにも付かず、各国の主権尊重を最高原則として互いに協力して平和と繁栄を追求していくことを合意した会議である。
その「主権尊重」の原則は、今日の自国第一主義にも通じる。それが、米国主導の「ロシア制裁」による「返り血」として国民生活を直撃する中で、制裁は正しいのか、そもそも「ウクライナ事態」を招いたのは米国によるウクライナへのNATO拡大、ウクライナのネオナチ化にあったのではないかという声の高まりとなり、米国ノー、米国覇権ノーとして、「主権尊重」「国民益第一」としての自国第一主義が支持を伸ばしている。
フランスでは4月に行われた大統領選で自国第一主義のマリーヌ・ルペンが前回の18%を42%に伸ばし、6月の総選挙では、マクロン与党が100議席を失う大敗北を喫する反面、ルペンの国民連合は8議席から89議席に躍進した。市民生活第一の左派連合「人民環境社会市民連合」も73から131に議席を伸ばした。ドイツでもシュルツ政権への不満が高まっており、他の諸国でも現政権への不満の声が高まっている。
戦争が終わったとしても、「ウクライナ事態」の基本構造、米国覇権とそれを打破しようとするロシアなどの諸国という基本構造は変わらないのであり、今後、数年間で欧米世界にも国益第一、自国第一の新しい政権が生まれ、世界は大きく変わるのではないか。
日本も変わらなければならない。これまでのように米国覇権の下で生きていけば良い、ではなくなっている。事実、米国覇権維持・強化のために、日本は対中国の最前線に立たされ、敵基地攻撃能力の保有や軍事費倍増や果ては、核の共同保有までが言われるようになっている。そればかりではない。エマニュエル駐日大使が就任承認を得るために開かれた米上院外交委員会で「日米の経済統合を目指す」と言ったように、日米経済の統合一体化も進んでおり、日本は、「国」としての体裁を失い、「米国51番目の州」にされようとしている。
反面、世界に目を転じれば、米国中心の覇権秩序に反対し脱覇権で主権尊重の「平等で民主的な新しい世界秩序」を作ろうとする動きは強まっている。日本は、あくまでも米国覇権の下で生きて行くことを続けるのか。それとも、こうした新しい動き、時代の流れに合流していくのか。新「サハリン2」は、それを問いかけている。

ちなみに、日本はバンドン会議の正式参加国であり締結国である。当時の日本は、戦犯国として国連加盟もできず国際孤児の境遇に置かれており、悲願の国連加盟のために、アジア・アフリカの票を得ようとしての参加であったとされる。しかし、一方で、敗戦後の日本は、これから、どう生きて行くのかということが問われており、米国一辺倒ではなく、アジア・アフリカなどとも協力して生きて行こうという道も模索していたということである。この日本の隠された「レガシー」、それを今、受け継ぐこと、それが、新「サハリン2」が問いかけることへの答えにもなるということを付け加えたいと思う。
▼魚本公博(うおもと・きみひろ)さん
1948年、大分県別府市生まれ。1966年、関西大学入学。1968年にブントに属し学生運動に参加。ブント分裂後、赤軍派に属し、1970年よど号ハイジャック闘争で朝鮮に渡る。現在「アジアの内の日本の会」会員。