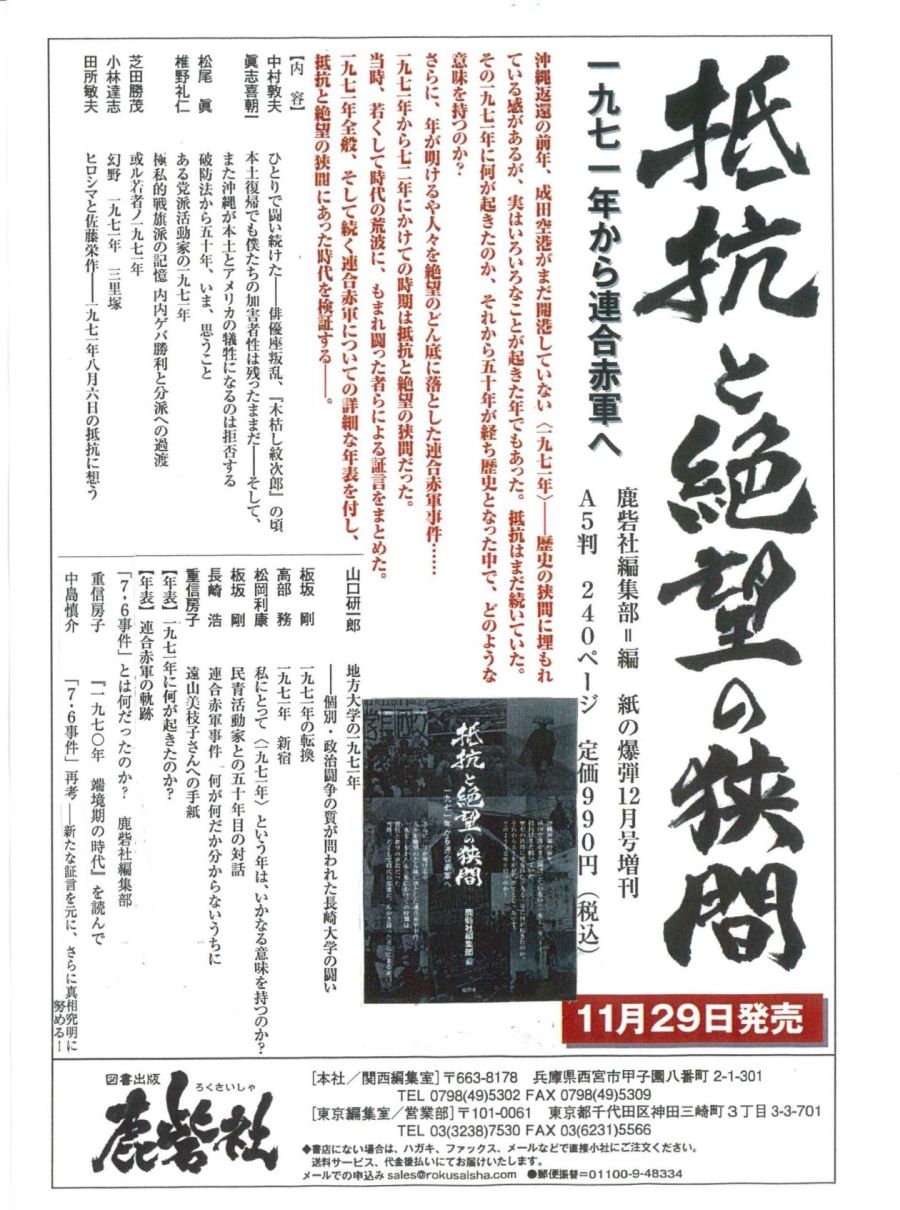生きた。生き抜いた。それだけで充分価値があった。生き抜いた「生命」はもちろんのこと、残念ながら生物的には終焉を迎えた人々の「精神」にすら、それが輝いていた日々を思い起こせば「充分価値があった」のだ。
希薄で触感に乏しく、手で触っても質感・凹凸すらを感じない。色は不明確で、匂いもしない。それがこの時代の主流派(メインストリーム)の共通項だ。地球温暖化のために「脱炭素社会」を目指す一団であったり、「SDGs」とかなんとかいう国際的欺瞞を堂々と掲げている連中は全員その一味だと考えていい。
「新自由主義」は金融資本がやりたい放題狼藉を働くために、「米国流」と称する基準の世界への押し付けじゃないのか、と目星をつけていたが、「新自由主義」もどうやら質的変化を遂げたようだ。その正体、曖昧ながら反論を封じる回答が「SDGs」ということのようである。
近年耳にしなくなったが、「南北問題」という設問(あるいは課題)があった。地球の北側に裕福な国が集まり、おしなべて南側のひとびとは貧しいこと、を指す言葉だ。「南北問題」は解決したわけではまったくない。問題の位相が南北だけではなく、東西にも広がり尽くし「北側」の国の中にも貧困がどんどん拡大しつつある。「グローバル化」を慶事の枕詞のように乱発した連中は、相変わらず同じ題目を唱え続けているのだろうか。「南北問題」つまり「階級格差」の世界的拡大こそが、今日の困難を端的に指し示すひとつのキーワードであろう
その端では「国連」をはじめとする国際機関が、中立性や科学を放棄し、目前の銭勘定や政治に翻弄される姿も顕在化する。ほかならぬ「災禍の祭典」東京五輪を控えて、「わたしは五輪終了まで一切五輪についてコメントしない」と勝手にみずからを律した。
ここで多言を要せずとも、「東京五輪」がもたらした「返済不能」な負債は、財政問題だけではないことはご理解いただけよう。コロナウイルス猛烈な感染拡大の中、開催された「東京五輪」は、開催直前にIOCの会議にWHOの事務局長が出席するという、わたしの語彙では説明ができない狼藉・混乱の極みと、価値の喪失を堂々と演じた。ここでバッハであったり、テドロス・アダノムといった個人名を取り上げてもあまり意味はない。「五輪」をめぐる利益構造への洞察と徹底的な批判だけが言説としては有効だと思う。
「東京五輪」は単に災禍であった。あれを「それでもアスリートの姿に感動した」などと評する人がいるが、社会を俯瞰する視野をまったく持たない悲しい輩である。
選手村の食事が大量に捨てられたことが報道されたようだが、そんなことは当然予想された些末な出来事の「かけら」に過ぎず、小中学校の運動会が規制され、修学旅行が取りやめになるなかでも「世界的な大運動会」を恥じることなく行ったのが、「日本という国」であり、「東京という都市」だ。「レガシー」という言葉を開催のキーワードに使っていたようだが、資本の論理で巨大化したIOCと称するマフィアは、健康や感染症の爆発的拡大と関係なく「五輪」を今後も開きつづける、と「東京五輪」開催で高らかに宣言をしたのだ。それが連中の「レガシー」だ。
WHOもIOC、国連。一切が利権により不思議な律動を奏でる今日の世界。液晶の向こうには何でもありそうで、本当はなにもない日常。「繋がっていないと不安」な精神は逆効果として個人の精神をますます蝕み「繋がること」と「疎外」が同時に成立する不可思議。なにかの「終焉」が足音を早めると感じるのはわたしだけだろうか。
生きた。生き抜いた。それだけで充分価値があった。生き抜いた「生命」はもちろんのこと、残念ながら生物的には終焉を迎えた人々の「精神」にすら、それが輝いていた日々を思い起こせば「充分価値があった」のだ。
本年も「デジタル鹿砦社通信」をご愛読いただき、誠にありがとうございました。2022年が読者の皆様にとって幸多き年となりますよう、祈念いたします。
▼田所敏夫(たどころ としお)
兵庫県生まれ、会社員、大学職員を経て現在は著述業。大手メディアの追求しないテーマを追い、アジアをはじめとする国際問題、教育問題などに関心を持つ。※本コラムへのご意見ご感想はメールアドレスtadokoro_toshio@yahoo.co.jpまでお寄せください。