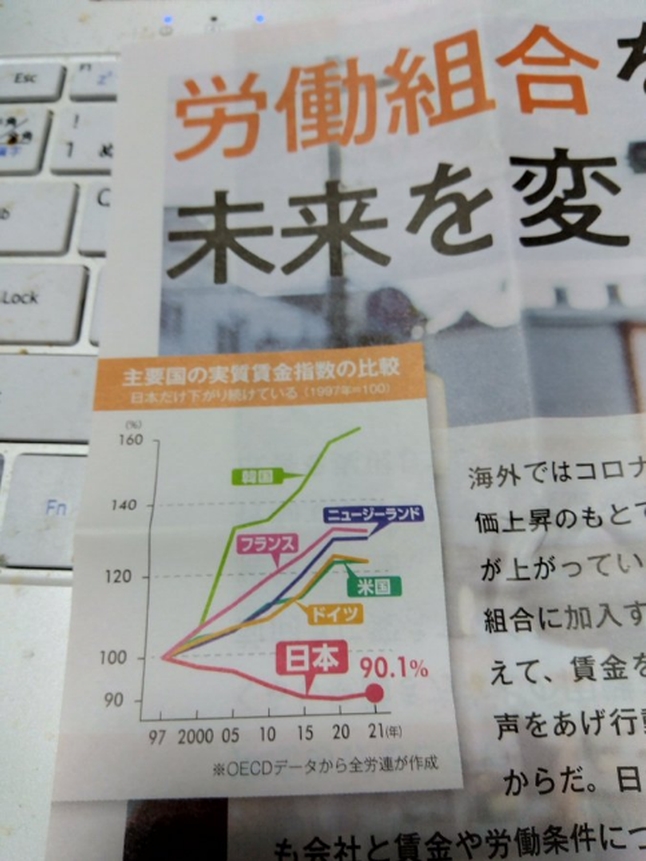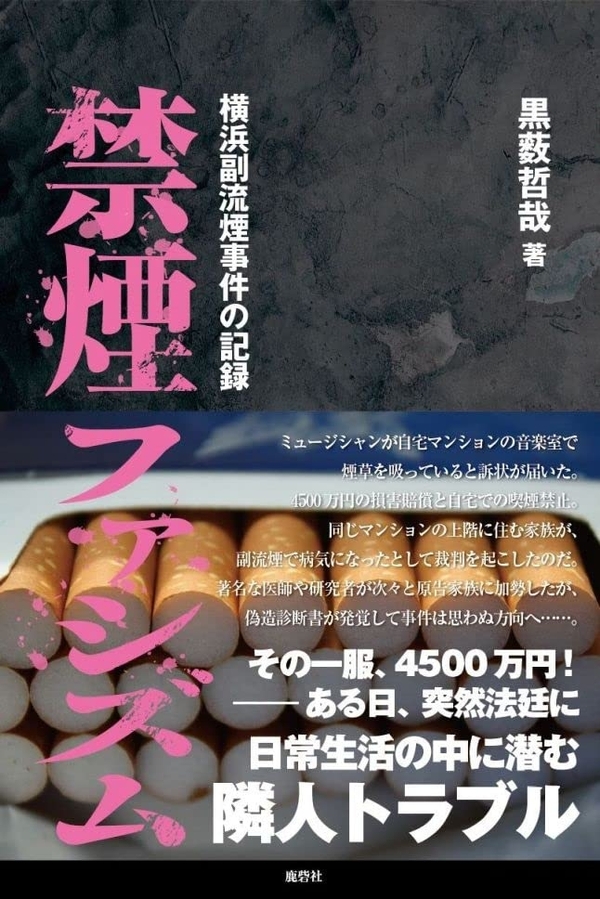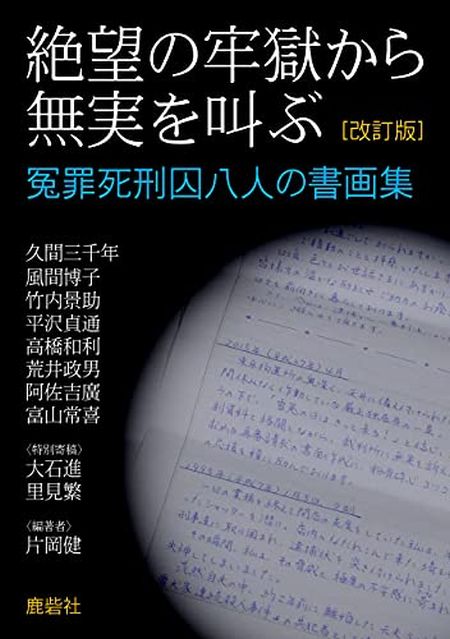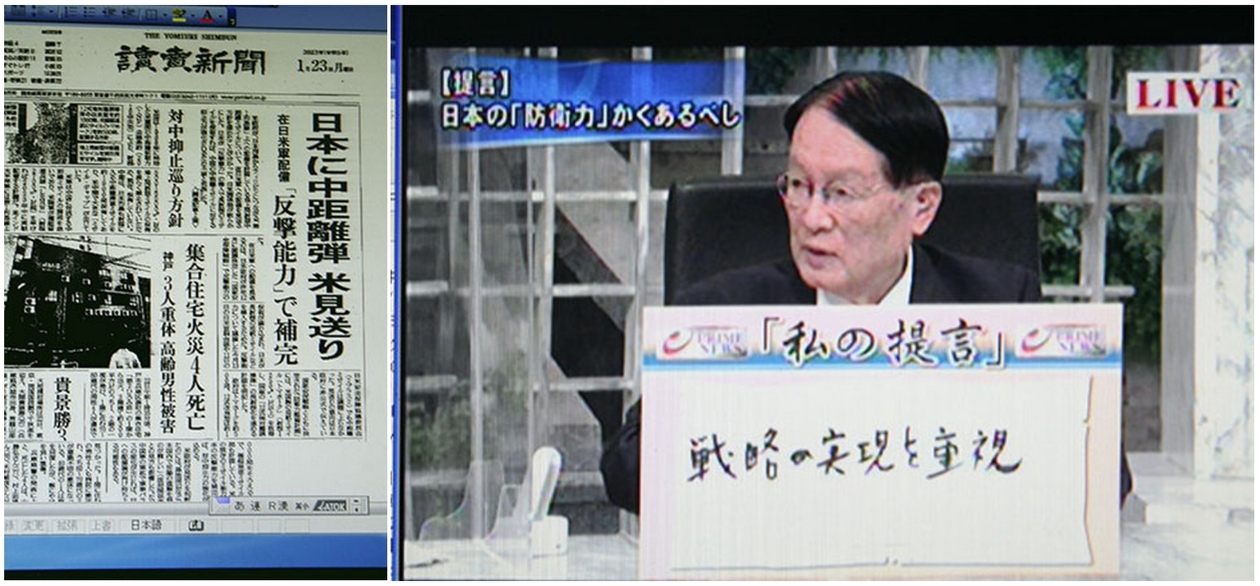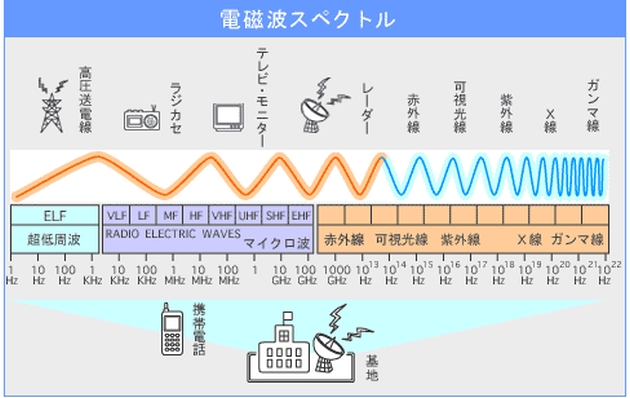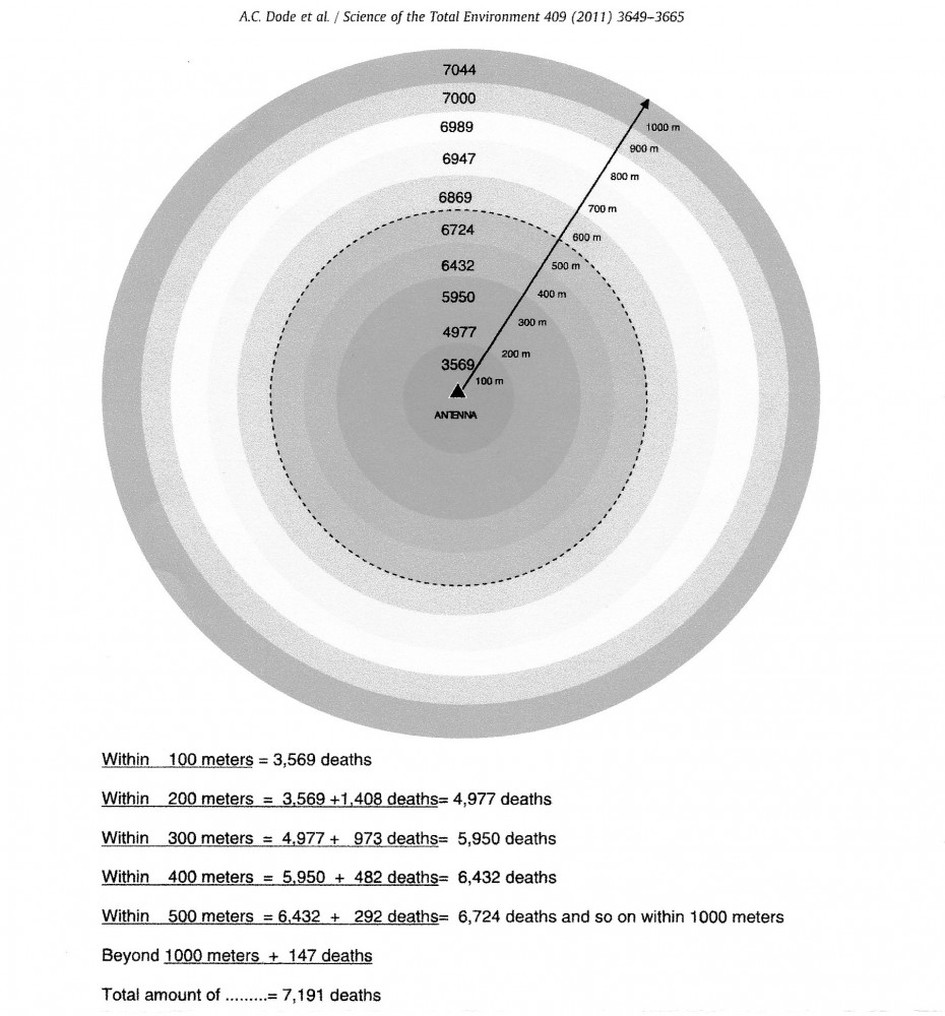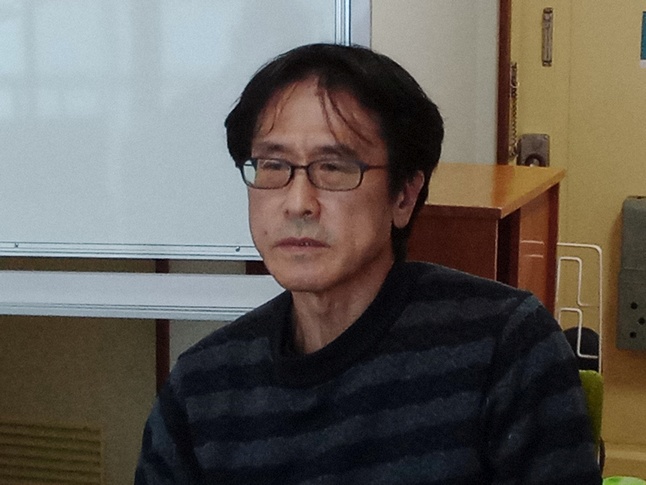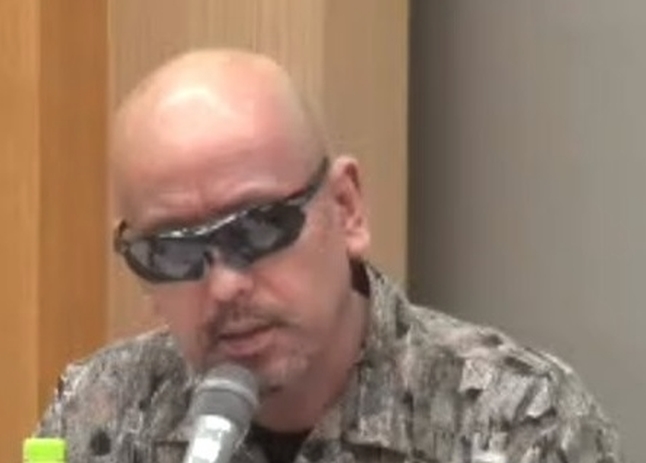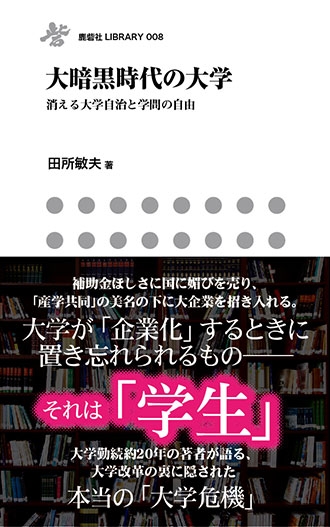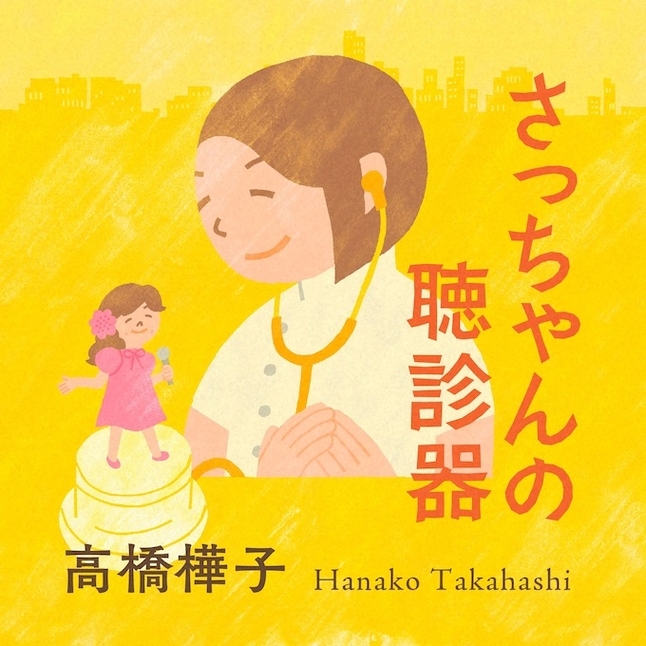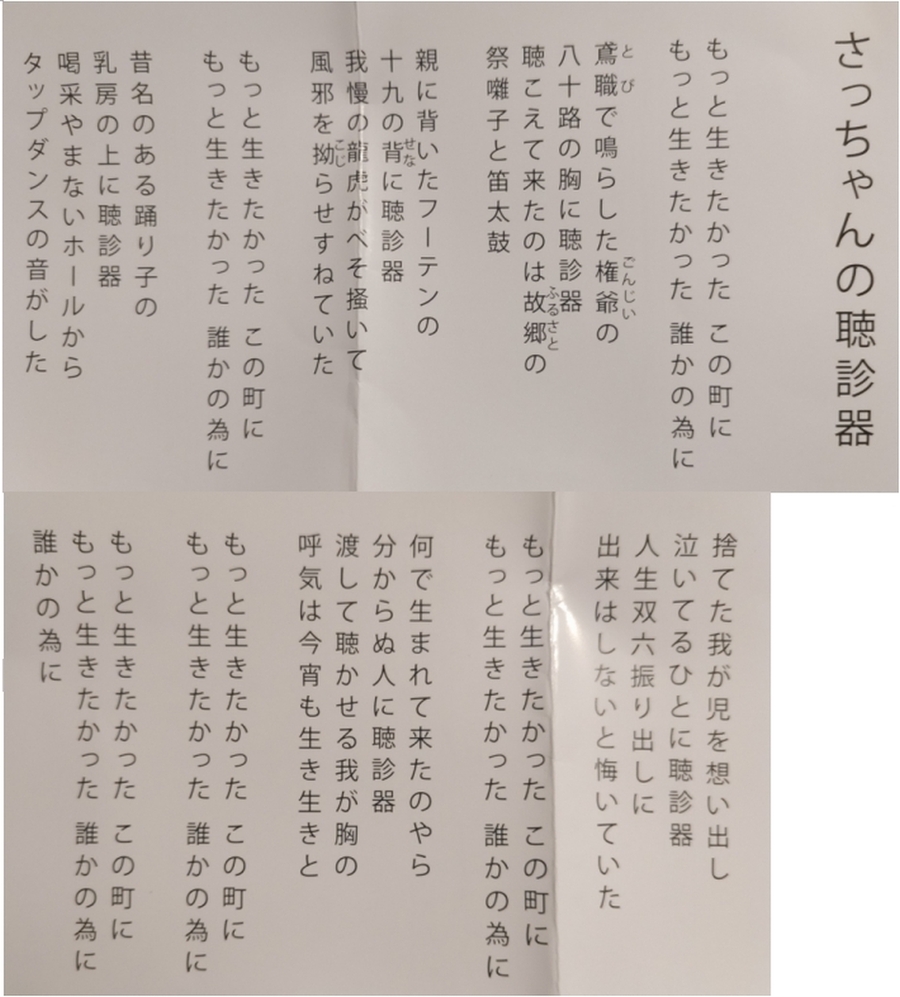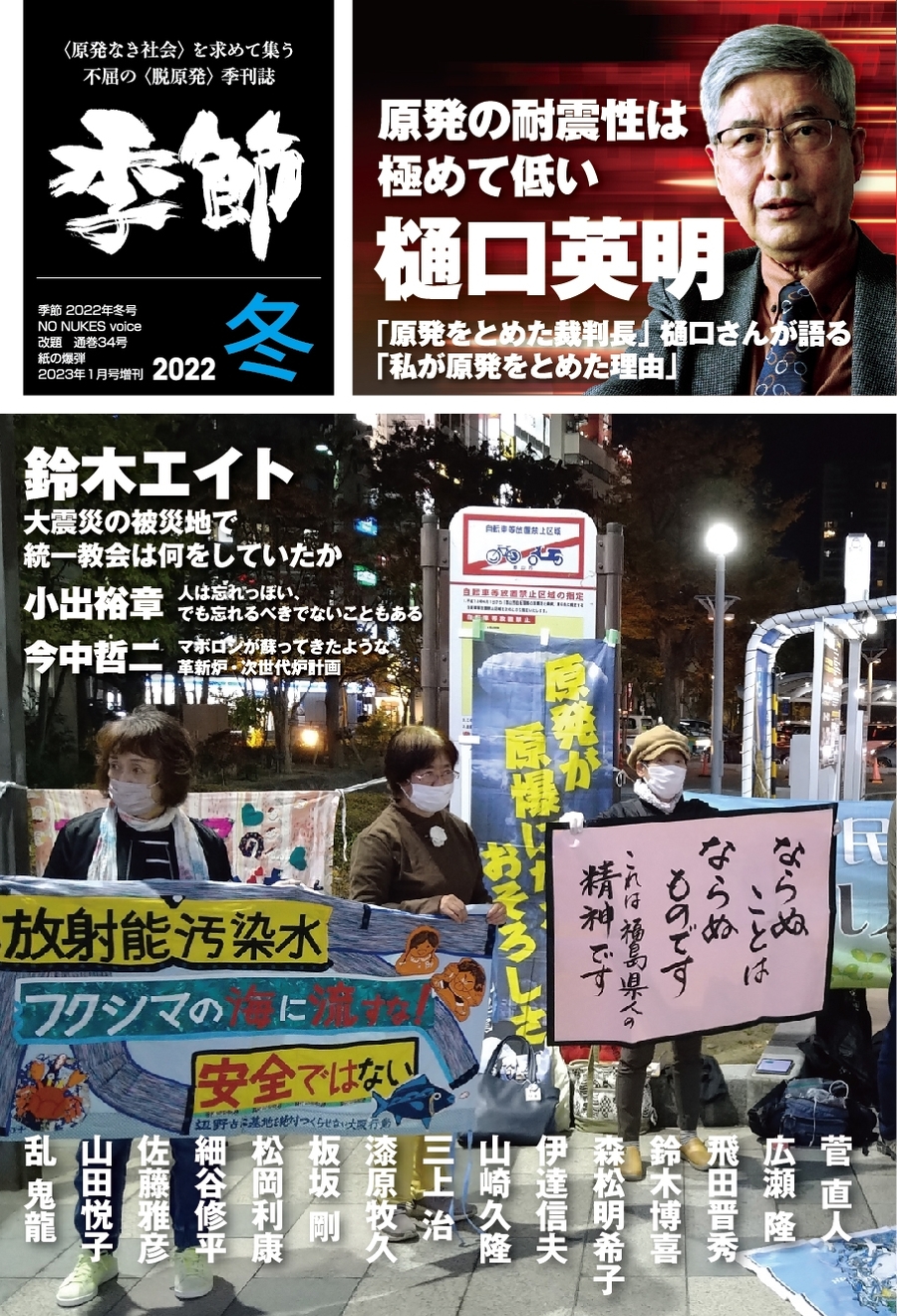サイト(2-6)は日本医療研究開発機構の報告です。いつものようにかなり専門的ではありますが、要するに、日本人21万人のゲノム解析により決定された、疾患発症に関わる遺伝的変異についての報告です。簡単にいえばゲノムと病気発症の相関関係を調べたということです。その結果、虚血性心疾患に関連する ATG16L2、肺がんに関連する POT1、ケロイドに関連する PHLDA3などの多くの疾患に関わる遺伝子が同定されました。その結果、多くの病気のなりたちが明らかになり、治療薬の開発、発症の予防、場合よっては遺伝子治療へと繋がっていくことが期待されています。
具体例を紹介します。BRCA1、BRCA2遺伝子は、それらが産生するタンパク質に、傷ついたDNAを修復する働きがあり、細胞の遺伝物質の安定性を確保する役割があります。すなわち、細胞のがん化抑制遺伝子です。この遺伝子が欠損していると、DNAの二本鎖切断の修復を十分に行えません。その結果、異常な配列が生じる可能性があり、がんになりやすいことが判りました。
遺伝子検査で、がん抑制遺伝子のBRCA1とBRCA2のどちらか、もしくは両方に変異が見つかった方で、血縁者に乳がんや婦人科がんになった方がいる場合、且つ乳がん検診で、いつも再検査を勧められる方ないしは、すでに一方の乳房が乳がんになった方に対しては、乳がんが発生していなくても、予防的乳房切除術が健康保険の適応の対象となりました。遺伝子科学の進歩により、上記の条件に該当する場合は、乳房にがんが認められなくとも発病可能性が極めて高いことから、このような予防的施術が保険適用されるに至ったわけです。
がん細胞には増殖の過程で、正常細胞と比較しても、より多くのDNAの損傷が生まれます。そして、多くは増殖を続けることが出来なくなり死滅します。しかし、がん細胞の一部は、さらに、間違った修復を受け悪性化していきます。がんが発症した方の中で、BRCA1/2遺伝子に欠損のある方は、BRCA1/2遺伝子による修復は出来ませんが、残されている別のシステムであるPARP(poly ADP-ribose polymerase)が働いて修復が行われてしまい、がん細胞が増殖してしまいます。 そこで、このPARPの阻害剤の一つであるオラパリブ(商品名:リムパーザ)を用いて、がん細胞のDNA修復を完全に阻止し、がん細胞を死滅させる方法が保険適用になり、がんの治療に使われています。オラバリブのように、病気の原因となっているタンパク質など、特定の分子にだけ作用するように設計された治療薬のことを「分子標的薬」と呼び、今日様々な新薬が続々と開発されています。分子標的薬がたんぱく質異常など病気の原因に合致すると、目覚ましい効果を上げることはよく知られています。このように、ゲノム解析は徐々にですが、人々の生活や医学に貢献してきています。
今ここまでに、述べました例は、沢山の方のゲノム解析をして、疾患に関わる遺伝子を特定して、その成果を利用しているものです。
つぎに最近のゲノム解析技術で、こんなことが出来るという例を紹介しましょう。前回、光と影(1)で、一卵性双生児でも、ゲノム配列が違うということを述べましたが、その違いは、任意の二人(他人)を比べた場合と異なり、極めて少ないものです。少ない違いでも正確に、デジタル技術を使って見つけることが重要です。そこで、我々は、そうした違いを見つけるためのプログラム(PED)を開発し論文として発表しました(文献2-7)。私が所長をつとめるつくば遺伝子研究所では、ある方から、「がん組織でゲノムDNA配列がどのように変異しているかを調べてほしい」と依頼を受けました。そこで、送付されたがん組織と対応する正常組織からDNAを抽出し、試料あたり、ヒトゲノム配列の50倍に相当する1500億塩基配列の分析結果を得ました。そして、正常組織の1500億塩基配列とがん組織の1500億塩基配列の相動性をPEDで解析しました。解析量が膨大であるため、オンボードメモリを768ギガ(市販のパソコンでは多くて16ギガ)搭載し、大容量記憶媒体のSSDを搭載したパソコンをつくば遺伝子研究所で自作しこれを用いました(つくば遺伝子研究所ではこのようにパソコンや検査機器も可能な限り自作し、それでありながら世界最先端の研究を実践しています)。この解析の結果、DNAポリメラーゼの遺伝子配列に変異が起こっていることが判りました。私は医者ではありませんので原因を特定しても、即座にその治療法を見つけることができるわけではありません。しかしこのように遺伝子配列に異変が起こっていることが判明すれば、医療界ではそれに対する治療法を検討することが可能でしょう。
今までは、ゲノム配列解析の進展とそれがヒトにどのように関わってきているかを概観してきましたが、これからのコラムでは、ヒト以外の生物種に対してどのように使われているかを紹介したいと思います。地球上でヒトの生存圏が構築されていますが、他の生物種でも同様に、それぞれの種でその生存圏が構築されています。その生存圏が交わるところで、共生があったり、問題(戦い)があったりします。それらについて、DNAの視点から興味深い観察と解析を行った例をご紹介します。具体的には、我々の住んでいるところに、クマ、イノシシなどが出没するといった事例です。
【文献】
2-5 Sequencing and analysis of Neanderthal genomic DNA James P Noonan 1, Graham Coop, Sridhar Kudaravalli, Doug Smith, Johannes Krause, Joe Alessi, Feng Chen, Darren Platt, Svante Paabo, Jonathan K Pritchard, Edward M Rubin Science. 2006 Nov 17;314(5802):1113-8.
2-6 https://www.amed.go.jp/news/release_20200609.html
2-7 Polymorphic edge detection (PED): two efficient methods of polymorphism detection from next-generation sequencing data. Akio Miyao 1, Jianyu Song Kiyomiya 2, Keiko Iida 2, Koji Doi 3, Hiroshi Yasue BMC Bioinformatics. 2019 Jun 28;20(1):362.
◎安江 博 わかりやすい!科学の最前線
〈01〉生き物の根幹にある核酸
〈02〉ヒトのゲノム解析分析の進歩
〈03〉DNAがもたらす光と影[1]
〈04〉DNAがもたらす光と影[2]
◎[過去稿リンク]わかりやすい!科学の最前線 http://www.rokusaisha.com/wp/?cat=112
▼安江 博(やすえ・ひろし)
1949年、大阪生まれ。大阪大学理学研究科博士課程修了(理学博士)。農林水産省・厚生労働省に技官として勤務、愛知県がんセンター主任研究員、農業生物資源研究所、成育医療センターへ出向。フランス(パリINRA)米国(ミネソタ州立大)駐在。筑波大学(農林学系)助教授、同大学(医療系一消化器外科)非常勤講師等を経て、現在(株)つくば遺伝子研究所所長。著書に『一流の前立腺がん患者になれ! 最適な治療を受けるために』(鹿砦社)等
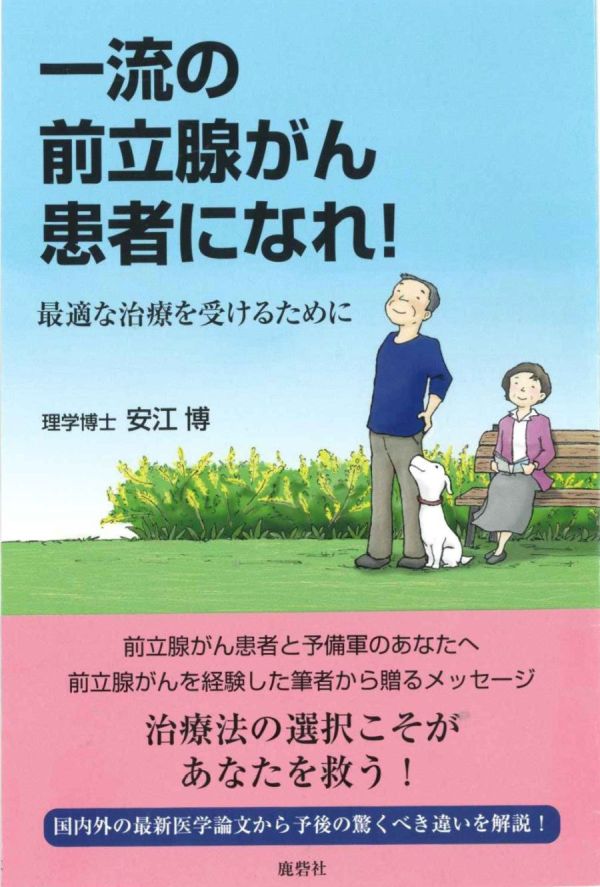
◎鹿砦社 http://www.rokusaisha.com/kikan.php?group=ichi&bookid=000686
四六判/カバー装 本文128ページ/オールカラー/定価1,650円(税込)