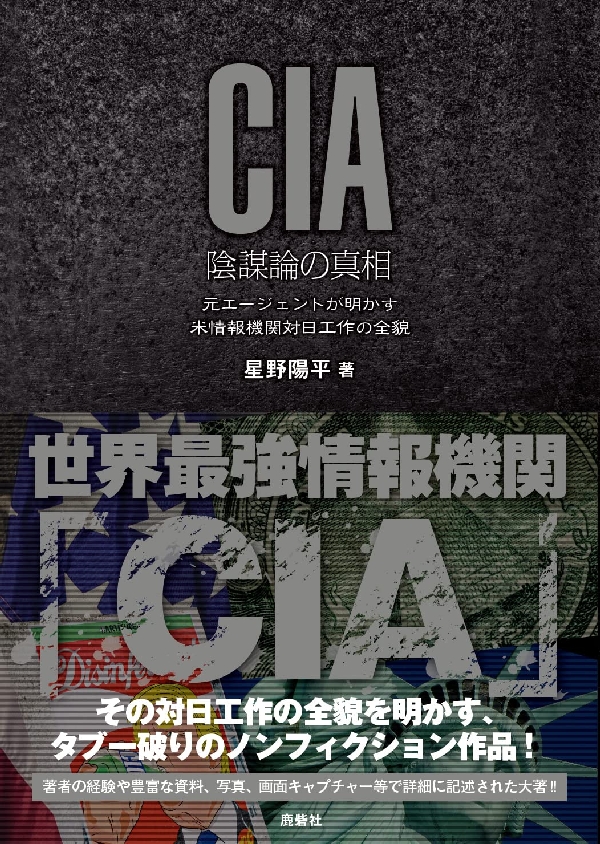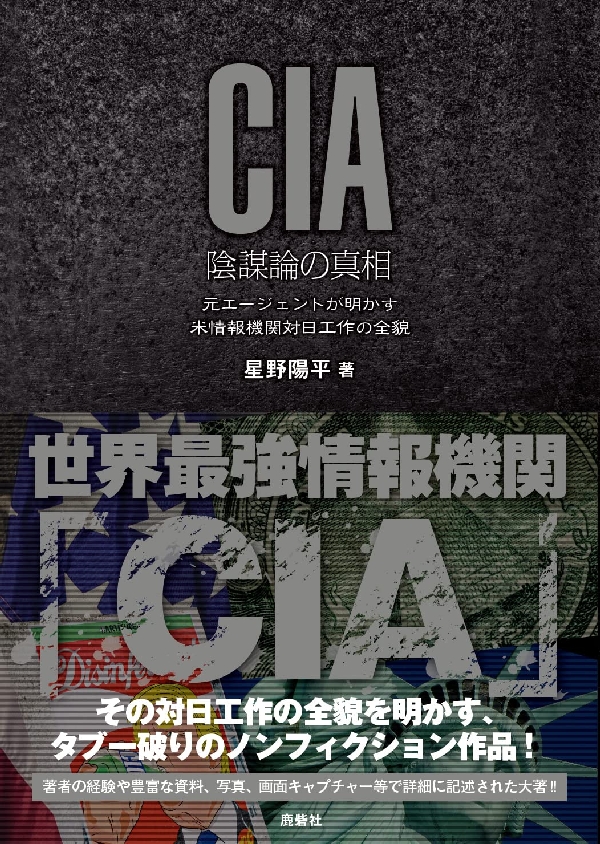
◆実体と関係の深い闇
表題にあげた星野陽平の労作を批評するまえに、実体(組織の存在)と相対(人間の諸関係)、および歴史観について前提的な議論を提起しよう。
いま評判の哲学書がある。かつて『恋愛論』で一世を風靡した竹田青嗣の『新・哲学入門』(講談社現代新書)である。冒頭から引用して、その問題意識をつかんでおこう。
「哲学の本義は普遍認識を目がける普遍洞察にある。だが、現代哲学では、稀な例外を除いて、哲学の根本方法を否定する相対主義哲学がその舞台を席巻してきた。」
「普遍認識の否定、これが相対主義哲学の旗印である。それは現代の流行しそうだったが、現代哲学の最大の病でもあった。」
「いまわれわれは、哲学の概念と像を根本的に刷新しなければならず、そのため、根本的に新しい哲学を必要としている。」「現代哲学には、独断論と相対主義の方法だけが残された。」
要するに普遍的存在をテーマにすべき哲学が、実体的な存在の解明を回避しているという、現代哲学への批判がその問題意識である。それでは、竹田が批判する「相対主義」とは何なのだろうか? われわれはデカルトの主体・客体という、近代的な図式への批判に立ち返って、相対主義を解き明かしておくべきであろう。
「われ、見るゆえにわれあり」がデカルトの存在論である。客体を見る「わたし」は、見るという行為において存在する。ここにすでに、近代的な相対主義がひそんでいる(客体によって存在が反証される)のを、われわれは感得する。しかしながら、それでは客体を認識する主体とは、何に由来するものなのか。絶対的な主体? そんなものは立証不可能である。
現代哲学の出発点は、じつにこれなのである。フッサールの共同主観性、メルロ・ポンティの間身体性、ハーバマスのコミュニケーション論、等々。
実体(モノ)と関係(コト)。絶対存在から相対的な関係性へ。これが現代哲学のテーマであった。典型的な論攷に、現代マルクス主義哲学の大家・廣松渉の哲学入門書を挙げておこう。奇しくも同じ版元の新書である。その煽りにはこうある。
「〈実体(モノ)〉的三項図式にかわり、現相世界を網のように織りなす〈関係(コト)〉的存立構制、その結節としてたち顕れる『私』とは、どのようなものか?量子論からイタリアの戯曲まで、多彩なモデルで素描する、現代哲学の真髄!」『哲学入門一歩前──モノからコトヘ』(講談社現代新書)。
実体と関係は、こうして概念として対立するようにみえる。少なくとも哲学者たちの世界では──。
実体論と関係論の相克はしかし、現実の社会関係(人間関係)を分析するうえで、相互に協力しあい、世界を認識する者(私)の中で、縦横に役立つはずだ。
なぜならば、われわれは現実存在としての実体(個別の存在)と関係性(社会的諸関係)に分裂させられながらも、ひとつの人格としてつねに統一されているからだ。それをどう評するかは、哲学者の恣意性であって、思想の趣味にすぎない。
◆個人的な体験であるところが凄い
哲学論の前置きが長くなった。いよいよ星野陽平の大著の分析に入ろう。
実体として、星野によればCIAの陰謀は現実に存在するが、その分析方法はじつに相対的である。なぜならば、方法論として星野が採用しているのが一般にジャーナリストが向き合う、自分の体験をもとにしているからだ。
自分の周囲の人間関係、それは星野の場合は芸能界をめぐる、さまざまな「動力(欲望)」を媒介にしているがゆえに、個人的でありながら「普遍」的である。たぶん彼でなくても体験できるが、彼においていっそう深刻な陰謀として立ち顕われるのだ。これはジャーナリストとしての星野の嗅覚・才能であろう。
星野がCIAの陰謀と向かい合うことになったのは、彼の『芸能人はなぜ干されるのか』であった。芸能界に張り巡らされた陰謀(干す)は、強大な芸能プロの存在がなさしめる陰謀であり、その背後には黒幕として暴力団の存在、それと争闘するCIAの存在が見え隠れする。
われわれを惹き込むのは、凡百の批評家や芸能評論家が外在的に論評するのではなく、すべて星野の実体験をもとにしていることだ。そこに「妄想」や「推論」があるのは言うまでもないが、ほかには代えがたい「実感」がある。時には相手と喧嘩をし、その修復にあたっては意図をさぐる。まさにドラマチックである。
しかも、その大半がSNSを媒介にしていることが、評者(横山)のような旧世代には目からウロコが落ちるというか、呆れるというか……。日々のSNSのメッセージを読み取る「能力」には、とてもついていけない。
◆陰謀史観の愉しみ
ロシア革命がユダヤ資本の陰謀であり、レーニンをはじめとするボリシェビキ幹部の大半はユダヤ人だった。この陰謀史観は事実でありながら、ロシアの労働者農民の歴史的偉業(革命的大衆行動)ゆえに、ロシア革命史研究から除外されてきた。
ユダヤの陰謀論はやがて、ディープステート論として「結実」する。すなわち、ユダヤ資本による連邦準備銀行の独占が歴代のアメリカ大統領(政権)をあやつり、世界支配の野望を計画に上せているというものだ。それもコミンテルン(死後)勢力と結びつき、国家外の国家が世界を支配していると。ほとんどは妄想だが、世界を解説する与件としては面白い。
星野のCIA陰謀論の源流は、占領下日本(東京租界)から出発する。渡辺プロ誕生の秘密、および国鉄下山・松川事件の謀略性。岸信介・佐藤栄作・安倍晋三にいたる政治家のCIA人脈。もちろんCIAコードを持つ正力松太郎まで、源流をさかのぼる。黒幕たちの戦後史をたどりながら、これは新しい世代によるひとつの戦後史だなと、松本清張いらいの謀略史観に酔う。
ところで、陰謀史観はその本質が陰謀であるがゆえに、陰謀の本当の実体には迫れない。関係性(人間関係・社会的諸関係)という実体をもとに、推論するしかないのである。それゆえに、歴史観の強靭さがもとめられる。それを妄想力というべきか、信念(妄念)というべきかは知らない。
◆歴史観の闇
ひとつだけ、特定の史観が強靭な構造をもっていることを、最後に述べておこう。マルクス主義的な「史的唯物論」は、歴史のすべてが「階級闘争の歴史である」(マルクス『党宣言』)から出発する。すべてが階級闘争の反映であるのだから、原因をそこにもとめれば説明がつく。
歴史観としてともかく、その「壮大な物語」(フランシス・フクヤマ)が歴史的には虚構だったことが、今日では明らかになっている。共産主義社会はおろか、その初期である社会主義すら実現できず、その多くが帝国主義的専制国家(独裁社会)となった。人間のはばひろい生活を包摂するには、政治革命論では無理があったともいえよう。
もうひとつ例に挙げておきたいのは、マルクス主義ほどは流行しなかったが、日本史における「先住・渡来」史観である。作家の矢切止夫が典型の歴史観で、日本史の戦乱・政変はすべて先住民系の氏族と渡来民の闘いであったというものだ。
日本史のどこを切り取っても、先住民系と渡来民系の争いがあり、その時々にどちらかが優勢であると。開国派(海外貿易派=蘇我氏・大和奈良王朝・平氏政権・室町幕府)と鎖国派(物部氏・平安政権・源氏政権・江戸幕府)という具合に、日本史はピッタリと合致するのだ。ある意味で、日本の外交史の本質を解いている。
これらを「争闘史観」と呼べば、マルクス主義の「階級闘争史観」との近似性がよくわかるが、もちろん別ものである。
世界史的な陰謀を成しているのは、ユダヤ資本やCIAだけではなく、アメリカだけでも全米民主化連盟など多数ある。ここから先は、星野陽平にCIAにとどまらない、世界史的陰謀組織の実態究明を期待したいものだ。
なお、筆者(横山)は星野が学生時代からライターを志していた時期に出会い、その後の歩みは知らなかったが、為替論や市場論をへて芸能取材に転じてきたこと。その旺盛な取材力と筆力(筆量)に感服している。本書の中にもその軌跡は触れられているが、フリーランスとしての苦闘やバイタリティに賛辞を贈りたい。
▼横山茂彦(よこやま・しげひこ)
編集者・著述業・歴史研究家。歴史関連の著書・共著に『合戦場の女たち』(情況新書)『軍師・官兵衛に学ぶ経営学』(宝島文庫)『闇の後醍醐銭』(叢文社)『真田丸のナゾ』(サイゾー)『日本史の新常識』(文春新書)『天皇125代全史』(スタンダーズ)『世にも奇妙な日本史』(宙出版)など。