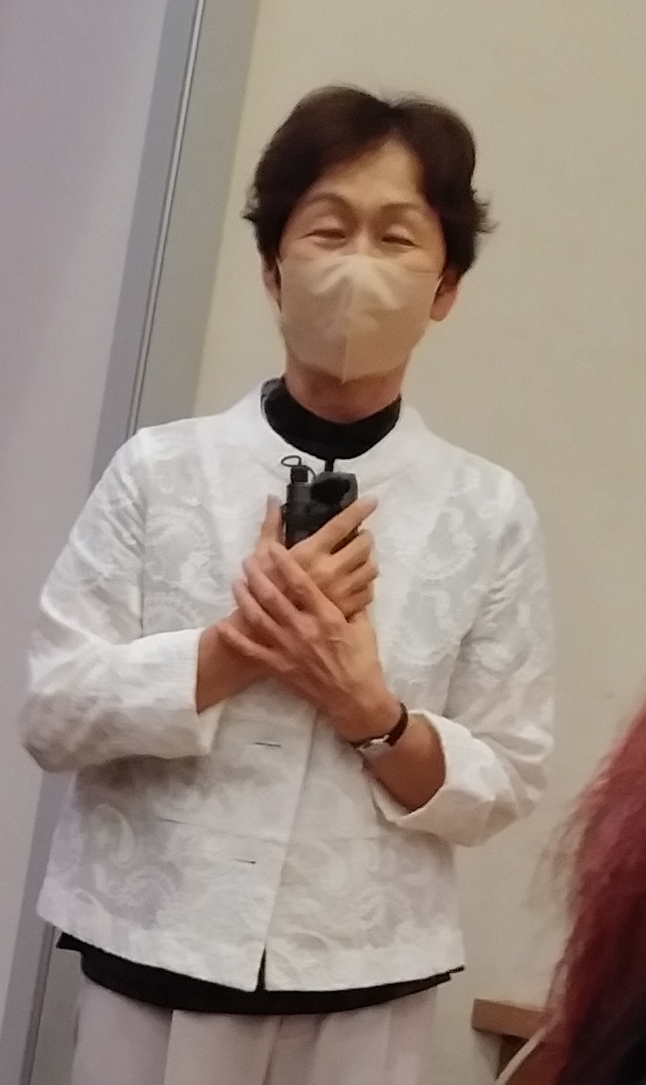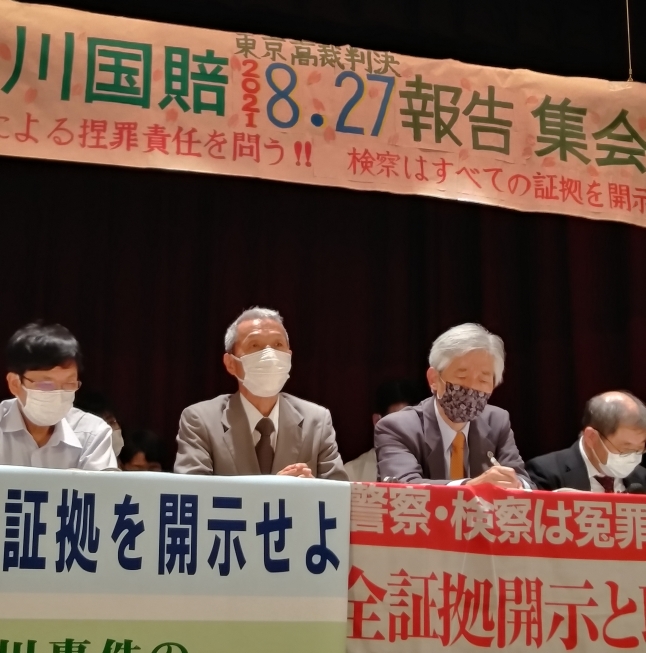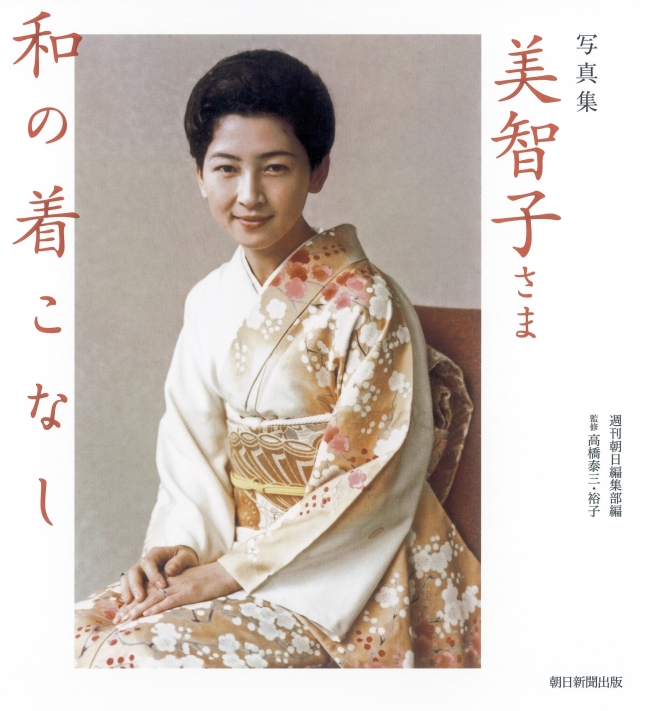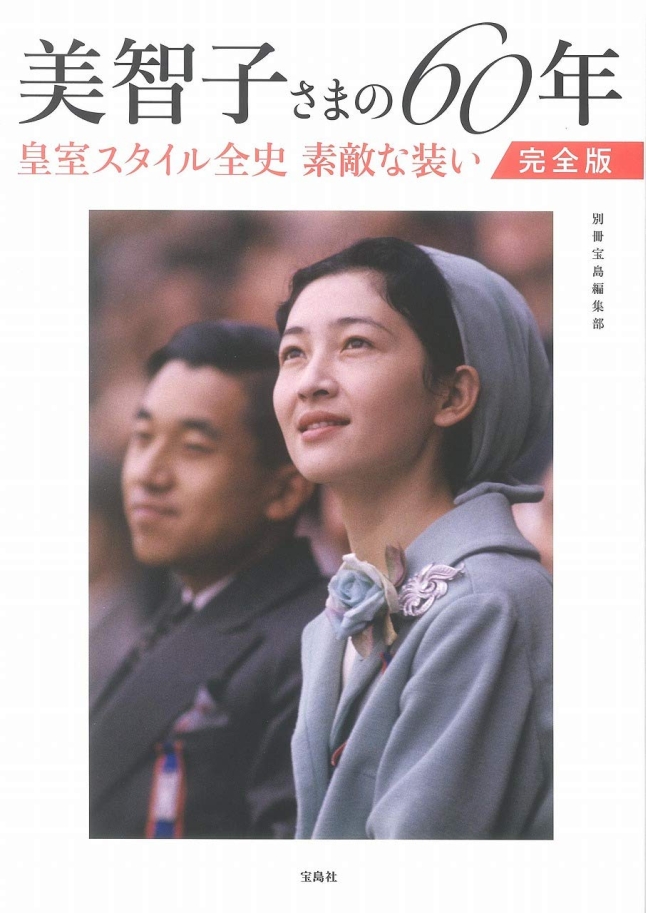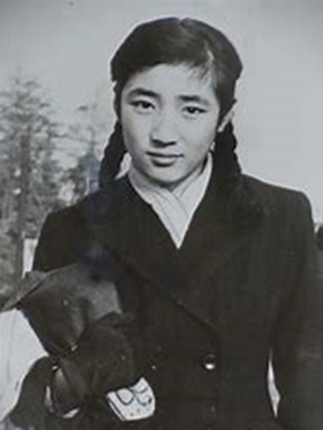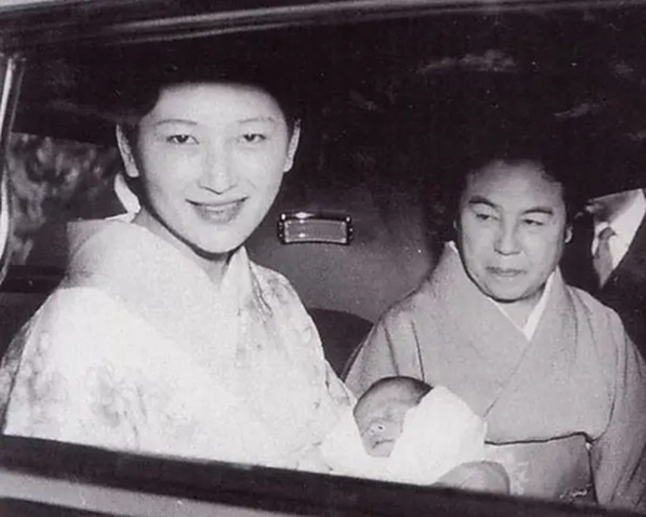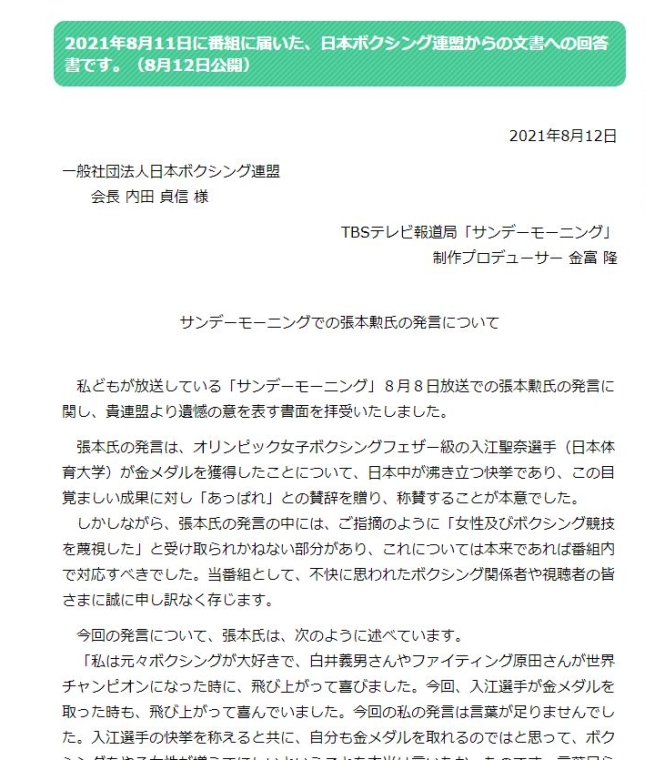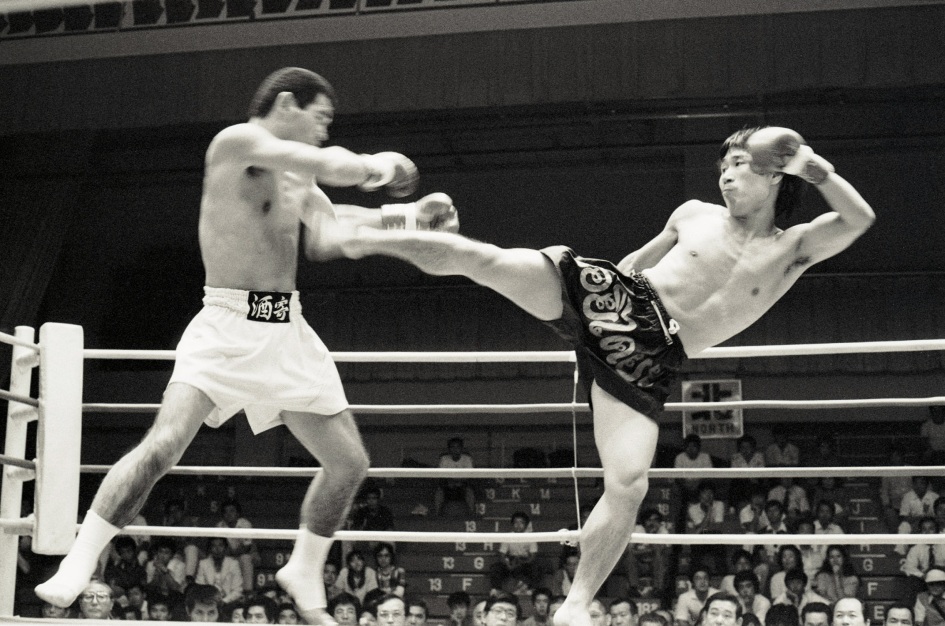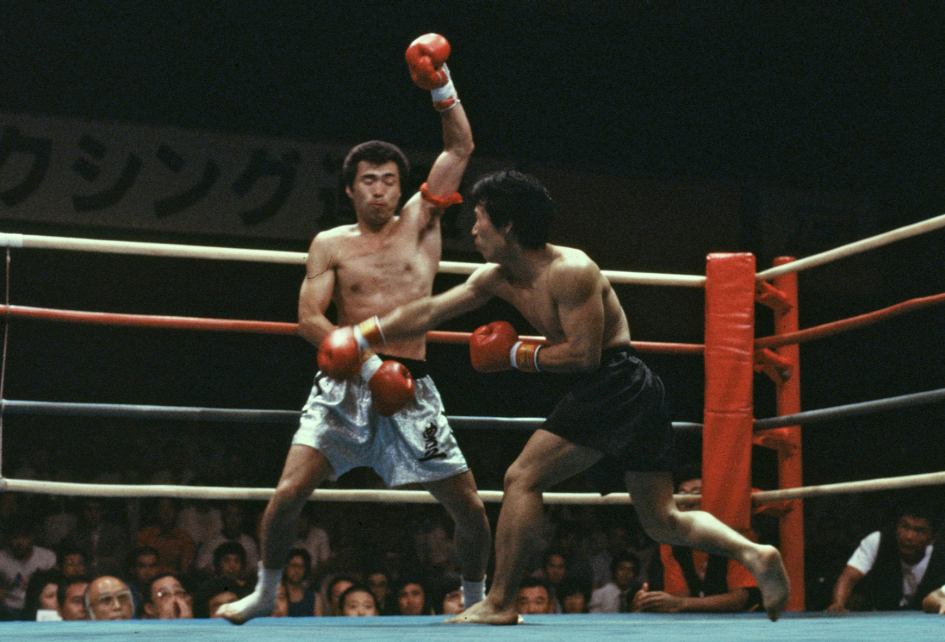菅辞任か解散強行か、と風評おびただしかった政治日程が決まった。自民党の総裁選挙9月17日告示、29日投開票である。
横浜市長選挙の敗北で死に体と見られていた菅総理が、開き直った再選出馬となった。25日には菅総理が党本部を訪れ、二階幹事長・林幹雄幹事長代理と約30分にわたって面会。公然と密談することで、自分たちが政局を仕切るのを行動でしめしたかたちだ。
◎[参考記事]「五輪強行開催後に始まる「ポスト菅」政局 ── 二階俊博が仕掛ける大連立政権」(2021年7月21日)
◆難航する野党共闘
総裁選挙を前に持ってきたことによって、総選挙(衆院選挙)の日程もかなり長いタームを含むことになる。社民党の関係者と懇談する機会があったので、以下に国会内の見通しをまとめておこう。
総裁選挙後の臨時国会で、首班指名となる。懸案のコロナ対策立法ののちに解散総選挙となり、その日程は最長でギリギリ11月までずれ込むものと考えられる。これは菅の再選、新総裁の場合も考えられる日程であろう。総裁選敗北で政権交代の危機も考えられる自民党にとって、失地回復の時間的猶予を確保したことになる。
もうひとつ、巷では台風の目になるかもしれない「小池新党」だが、国民民主との提携が現実的であるという。もともと、希望の党として一体化していた関係である。その国民民主の存在が、共産党との関係で野党共闘のネックになっている。社民党関係者によると、いまだ60か所以上の小選挙区で候補調整が遅れているというのだ。連合が嫌う原発反対、そして共産党への反発である。これに代わるかたちで、市民連合や文化人を看板にした選挙対策が練られているという。
このかんの選挙でわかるように、圧倒的な多数派である無党派層の選択肢になる野党共闘候補が実現しなければ、国民の20%に満たない自民党支持で一強政治が継続してしまうのだ。
◆あいかわらずの菅答弁
それにしても、わが菅総理のボロボロ、トホホな発言はあいかわらずだ。言い間違いをあげつらいたくはないが、一国の宰相の発言である。記者会見から拾ってみよう。
「タリバンの首都、カブール…」(※正しくは「アフガニスタンの首都」)。
「カニ政権は機能しなくなり……今後の情熱は、依然として不透明であります」
(※正しくは「ガニ―政権」)。
「感染拡大を最優先にしながら…」(※「感染拡大防止を、」のつもりであろう)。
◆総裁選展望
ふたたび自民党の派閥構成の概要である。(★は総裁選出馬)
派閥名 国会議員数 総理・総裁候補者
細田派(清話会) 96人 ★下村博文
麻生派(志公会) 55人 河野太郎
竹下派(平成研) 52人 加藤勝信、茂木敏充
岸田派(宏池会) 47人 ★岸田文雄
谷垣グループ 23人(重複含む)
二階派(志帥会) 47人 林幹雄、※党外[小池百合子]
菅派(ガネーシャ) 26人 ★菅義偉
石破派(水月会) 17人 石破茂※この時期の総裁選挙に批判的
石原派(未来研) 10人 石原伸晃※菅続投支持
無派閥 63人 ★高市早苗(細田派系)、野田聖子(二階派系)
現在のところ、★印が総裁選出馬宣言をしている。
このうち、有望株とみられていた河野太郎が出馬するのかどうか。出馬しないのはワクチン相ほかに抜擢してくれた菅への配慮ではないかとされているが、その動静が注目される。
去年から再出馬の岸田文雄は、じつはあとがない。参院から総選挙(山口三区で河村建夫と争う)で衆院に転じる林芳正が、宏池会の後継者となるからだ。今回を逃がせば、岸田が総理大臣になる可能性はなくなる。まさに背水の陣である。
昨年の総裁選で敗れたあとは、何となく一皮むけたような雰囲気もあり、出馬にあたっての政策では、経済再生のための「所得分配」問題にも発言がおよんでいた。よりましな選択としては、岸田の健闘に期待してもいいかもしれない。
そして下村博文の出馬である。よりにもよって、嫌いな人物が総裁選への出馬を宣言した。
◎[参考動画]総裁選に向け動き加速(テレ東BIZ 2021年8月27日)
じつは自民党の政治家だから嫌いだとか、そういうものはわたしの場合は、ないつもりだ。そしてこの通信で、個人的な好き嫌いや個人的な感情を顕わにするのを、なるべく避けてきた。
個人的な感情で論評・報道してしまうと、その批判の公共性が失われるからだ。さまざまな考え方があるし、個人エッセイ的に心情を吐露する人がいても悪くはないと思うが、ウエブマガジンも「社会的公器」である。そこを逸脱して、個人の感情で批評してしまえば、公共のネットを私物化することになる。したがって「わたしは」ではなく「われわれは」という視点を、ある意味では勝手に世論を代表するかたちで押し出すことにもなる。だがそこで、個人的感情を公的な視点によって抑制するのである。
だが、今回は感情的なものを抑えるのはむつかしい。嫌いなのである。下村博文という政治家が(苦笑)。
ほかにも、公明党代表の山口那津男の優等生的な風貌も嫌いだったが、実際には社民党の福島瑞穂なみの平和観の持主で高潔、非常に聡明な人物だと知って、その嫌悪感はなくなった。しかし、下村博文は安倍晋三以上の極右政治家である。この男だけは、総理大臣にしてはならないと思う。
もうひとり、高市早苗が先駆けて出馬宣言している。
「総裁選に出馬します!――力強く安定した内閣を作るには、自民党員と国民からの信任が必要だ。私の『日本経済強靭化計画』」(文藝春秋9月号)。
安倍元総理に再出馬をもとめたところ、拒否されたのでみずから出馬したという。じつは自民党内にも「女性宰相待望論」があり、単なる当て馬・咬ませ犬とするには惜しい。下村博文とちがって政策要領もあるので、彼女については稿をあたらめて批評したい。
◆戦況はどうか?
それでは、総裁選挙の戦況はどうなのだろう。というよりも、菅の再選はあるのか。今回は地方党員の投票が反映される、フルスペックの総裁選挙である。
2012年の総裁選では、石破茂・安倍晋三・石原伸晃・町村信孝・林芳正が出馬し、石破茂が199票で安倍晋三(141票)に差をつけるも、過半数の獲得にはいたらず国会議員による決選投票となった。
ここでは派閥の論理が優先し、安倍が108票、石破89票となり、地方党員の意志が封じられた格好になった。今回、地方の自民党で圧倒的な人気をほこる石破茂は出馬せず、二番手人気の河野太郎も不出馬の可能性が高い。
したがって、菅義偉と岸田文雄の事実上の一騎打ちは、地方票の獲得率によって流れが決まる。
問題なのは、もしも岸田が地方票で多数を獲得し、しかし2012年のように決選投票となって派閥力学で菅が再選された場合である。自民党は民意を反映しない、ひとにぎりの幹部たちの思わくで政治を動かす。国民の一部とはいえ、地方党員の意志を踏みにじった結果、総選挙がどのようなものになるか。もはや火を見るよりも明らかであろう。
▼横山茂彦(よこやま・しげひこ)
編集者・著述業・歴史研究家。歴史関連の著書・共著に『合戦場の女たち』(情況新書)『軍師・官兵衛に学ぶ経営学』(宝島文庫)『闇の後醍醐銭』(叢文社)『真田丸のナゾ』(サイゾー)『日本史の新常識』(文春新書)『天皇125代全史』(スタンダーズ)『世にも奇妙な日本史』(宙出版)など。