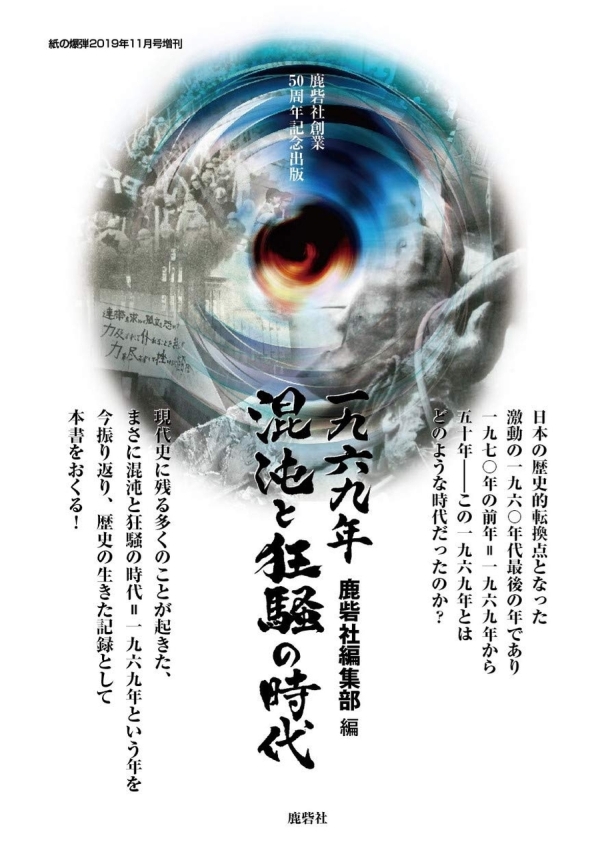ここまで呪術・神託などのシャーマンを媒介に、古代女性が祭司的な権力を握っていたことを探ってきた。その権力の基盤となっていたのは、日本が世界史的には稀な、母系社会だったことによる。われわれの祖先の社会全体が、母親を中心にした家族構成を認めていたからにほかならない。
万葉集の両親を詠った歌は、母親を主題にしたものがほとんどである。父親を詠ったものはきわめて少ない。そのいっぽうで、夫が来ないことを嘆く女性の歌は、おびただしい数にのぼる。ここに古代(明日香・奈良)から中世にかけて(平安期を中古ともいう)の、日本人の生活様式が明らかだ。
古代の日本は夫が妻のもとに通う、通い婚だったのである。庶民のあいだに家という単位はまだなく、集落で共同して労働に取り組んでいた。そして家族のわずかな財産は、母から娘へと受け継がれたのだ。女性が家にとどまり、男性は外に家族をもとめたからである。財産を継承するには、まだ男性の生産活動は乏しすぎた。母系社会とは集落の中の家を存続するためにはかられた、まさにこの意味である。
この婚姻形態は、平安時代にも引きつがれた。右大将藤原道綱の母による『蜻蛉日記』にはときおり、夫の藤原兼家が訪ねてくるくだりがある。彼女は『尊卑分脈』に本朝一の美女三人のうちの一人とされている。
のちに摂政関白・太政大臣に登りつめる兼家はしたがって、美人妻を放っておいたことになる。ちなみに他の美女二人は、文徳帝の女御・藤原明子(染殿后)、藤原安宿媛(光明皇后)であるという。光明皇后は前節でみた孝謙女帝の母だから、かの女帝も美人だったのだろう。
◆宮中文化も、もとは庶民の文化だった
それはともかく、平安の女性たちは奈良の都の女帝たちにくらべると、いかにも穏やかでおとなしい。彼女たちは実家にいて、夫が通ってくるのを待つのみだ。宮仕えをすれば、それなりに愉しいこともあったやに思えるが、道綱の母の姪にあたる菅原孝標の娘は「宮仕えは、つらいことが多い」(『更科日記』)と嘆いている。
この時代に、世界に冠たる女流文学『源氏物語』(紫式部)や名エッセイ『枕草子』(清少納言)が世を謳歌したけれども、女性の政治的な活躍は見あたらない。いや、それは政治の舞台に視線を定めているからであって、じつは詠歌こそが宮廷内の政治だったとすれば、平安の女性の活躍もめざましい。詠歌は今日も宮中歌会に引き継がれる、天皇制文化の根幹でもあるのだ。武家の花押が閣議の場に引き継がれ、和歌が宮中儀礼に引き継がれる。しかしいずれも、もとは庶民の文化であった。読み人知らずと呼ばれる庶民、もしくは名前を伏せられた詠歌は万葉集の圧倒的多数であって、君が代もまた読み人知らずなのである。天皇制を無力化するというのなら、庶民の対抗文化を創出・流行させないかぎり、擬制の「伝統」に勝てないのではないか。
◆平和とは何かを考える
三十六歌仙には小野小町、伊勢の御息所、その娘である中務、三条帝の女蔵人であった小大君、皇族では徽子女王(村上帝の女御)と、名だたる女流歌人たちがいる。和泉式部は『和泉式部日記』、赤染衛門は『栄華物語』の作者に擬せられる。
ほかに名前を挙げてみよう。佑子内親王家紀伊、選子内親王家宰相、待賢門院堀河、宜秋門院丹後、皇嘉門別当。しかし、いずれも仕えた権門の名、出身家の名前であって、彼女たちの本名がわからない。
そして、いずれもが下々の者だからわからないのだと言えるが、彼女たちが仕えた氏姓(うじかばね)も諱(いみな)もある女人たちは、これまたいずれも史料がなくてわからないのである。やんごとなき姫君たち、あるいは帝の后たちは、歌人としてはいまひとつだったようだ。
平安時代は江戸時代とともに、日本史史上きわめて平和な時代だった。死刑が廃された時代でもある。政治である以上は政争や暗殺もあったし、僧兵(学僧)の反乱はおびただしかったが、平和だからこその騒乱なのである。社会が安定しているからこその、あだ花の学生運動みたいなものだろう。防人の制度(徴兵制度と軍隊)も解散し、死刑もなく、戦争や紛争がなかったから女性の活躍があったはずなのに、それは歌道と小説・エッセイにかぎられていた。
▼横山茂彦(よこやま・しげひこ)
編集者・著述業・歴史研究家。歴史関連の著書・共著に『合戦場の女たち』(情況新書)『軍師・官兵衛に学ぶ経営学』(宝島文庫)『闇の後醍醐銭』(叢文社)『真田丸のナゾ』(サイゾー)『日本史の新常識』(文春新書)『天皇125代全史』(スタンダーズ)『世にも奇妙な日本史』(宙出版)など多数。