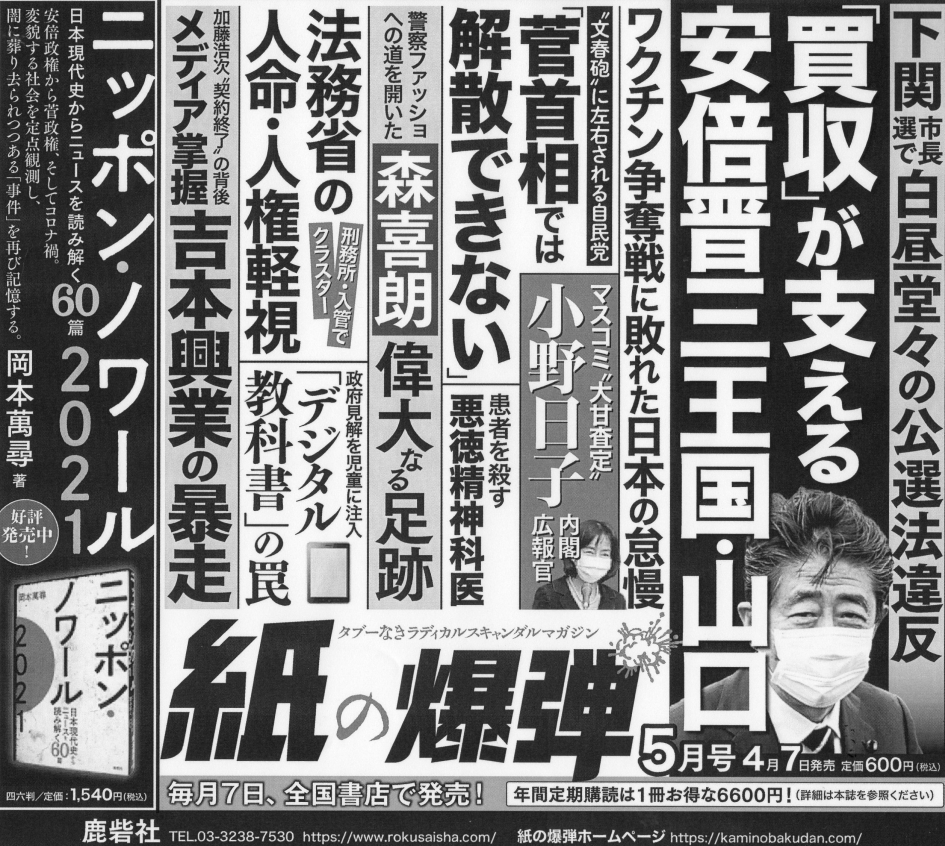前回、昭和天皇が近衛文麿の「講和促進の上奏文」を肯んぜず、「もう一度敵をたたき、日本に有利な条件を作ってから」と応えたことを記した。

じつはこのあと「戦果を挙げてでないと、なかなか話は難しいと思う」とある。
つまり、アメリカと対等とまではいかないが、講和交渉に応じざるを得ない戦局をつくらなければ、相手も応じないであろう。という戦略家としての判断だったことになる。
だが、前回指摘したとおり、天皇はある種のギャンブル症候群に陥っていたのではないか。いや、少なくとも個々の敗北を検証する観察眼を失っていた。大本営の幕僚たちもまた展望を描けないまま、精神論に陥っていたというべきであろう。精神論の物質的な象徴こそ、神風特別攻撃隊であった。天皇はこれにショックを受けながらも「よくやった」と称揚した。

戦前、近衛文麿に「是非やれと言われれば初めの半年や1年の間は随分暴れてご覧に入れる。しかしながら、2年3年となれば全く確信は持てぬ」と語り、外交交渉の継続を「三国条約が出来たのは致方ないが、かくなりし上は日米戦争を回避する様極極力御努力願ひたい」としていた山本五十六のような人物は、もはや海軍にも陸軍にもなかった。
「国大なりといえども戦好まば必ず滅ぶ 国安らかなりといえども戦忘れなば必ず危うし」(山本五十六)をもって瞑すべし。
◆なぜ「聖断」は遅れたのか
マリアナ海戦の敗北とサイパン失陥後、茫然自失になっていた昭和天皇は、台湾沖航空戦のまぼろしの「戦果」に浮かれ、ふたたび「皇国の興廃」をかけたレイテ海戦によって意気消沈する。にもかかわらず、もう「一度戦果を挙げたい」というのだ。
近衛は奏上の直後、天皇が「(陸海軍は」台湾に敵を誘導し得ればたたき得ると言っているし、その上で外交手段に訴えてもいいと思う」と語ったのを細川護貞に伝えている。
だが、アメリカ軍を台湾に誘導するには、台湾に強力な勢力がなければ応じるはずがない。すでに台湾には航空兵力はなく、敵の空爆に手をこまねいているしかなかった。台湾だけではない。たとえばニューブリテン島の海軍の拠点・ラバウルにも1年は籠城できる準備はあったが、航空兵力をうしない戦略的な意味もなくなった拠点を、アメリカ軍が攻撃する義理はなかった。

アメリカ軍がつぎの攻略目的にしたのは、日本の本国(沖縄)であった。大本営も本土決戦の準備のために時間稼ぎ、およびアメリカに出血を強いる「決戦」としてこれを位置づけた。生還を期さない神風特別攻撃隊が3900人にもおよぶ犠牲を出したのも、全軍が戦死・県民の4人に1人が犠牲(20万)になる沖縄戦の渦中であった。
いっぽう、本土も主要都市が焦土と化していた。昭和20年の3月10日には東京大空襲で10万人の死者がでている。そのころ、天皇はどういう生活をしていたのだろうか。
吹上にある御文庫と呼ばれる防空施設に、昭和天皇は起居していた。10トン爆弾にも耐えられるという鉄とコンクリートに覆われた場所で、皇室はその身の安全を護られていた。もっとも、アメリカ軍は占領時の必要を考慮して、のちに進駐軍の本部となる第一生命ビルほか、国会議事堂など主要な施設、皇居にも爆弾を落とすことはなかった。

◆沖縄戦での戦争指導
台湾ではなく沖縄が「決戦の地」になったことで、昭和天皇の「戦意」が衰えたわけではなかった。
「沖縄戦が不利になれば、陸海軍は国民の信頼を失い、今後の戦局に憂うべきものが出てくる。現地軍はなぜ攻勢に出ないのか、兵力が足らないのであれば逆上陸をやってはどうか?」と陸軍に督励している。
もともと、本土決戦の時間稼ぎとして持久戦をもとめられ、作戦は現地軍(第32軍)にまかされていた。だが、天皇の督促を電令された第32軍は、あたら中途半端な攻勢に出ることで、戦力を消耗してしまうのだった。
海軍に対しても、天皇は作戦を指導している。航空総攻撃の上奏のときに「航空部隊だけの総攻撃か?」と下問があり、それへの対応として、戦艦大和以下の水上特攻が準備されたのだ。
◆陛下に強いられた特攻
元来、特攻作戦は「志願制」であった。部隊長が「志願したい者」と隊員たちに告げ、それに全員が応じることで、形の上では「特攻隊に志願」という体裁がとられていた。

しかし、戦艦大和の場合は軍令部による「命令」となった。沖縄で国民が犠牲になっているのに、大和は生き残っているのか。と、詰め腹を切らされたのである。天皇の下問がその契機になったのは、いうまでもない。宇垣纏海軍中将は、その日記『戦藻録』に、その悲惨な無駄死にを「軍令部総長奏上の際、航空部隊だけの総攻撃なるやの御下問に対し、海軍全兵力を使用いたすと奉答でるにある」と記している。
戦艦大和の沈没(4月7日)、沖縄戦の敗北(6月23日)で、あとは本土決戦を待つのみとなった。そのかん、ドイツの降伏とムソリーニ処刑が4月30日に天皇に報告され、日本単独での戦争継続は不可能との奏上(東郷重徳外相)を受けている。このとき天皇は「早期終戦を希望する」と返答している(『実録』)。
木戸内大臣によると「従来は、全面的武装解除と責任者の処罰は絶対に譲れぬ。それをやるようなら最後迄戦うとの御言葉で、武装解除をやれば蘇聯(ソ連)が出てくるとの御意見であった」(『高木海軍少将覚え書』)。これはまだ、沖縄戦が渦中にあった時期のことだ。
◆混迷する和平の模索
木戸内府をはじめとする宮中首脳、海軍首脳の終戦派などのあいだで、ようやく天皇による「聖断」の準備が考慮されはじめていた。本土決戦で行けるところまでいき、あるタイミング(もう戦争は無理?)で天皇の聖断を仰ぐというものだ。
陸軍の主流派は本土決戦を合言葉に、国民もまた「一億玉砕」の空気だった。すでにラジオで「海ゆかば」が流れるときは「玉砕」の訃報、軍艦行進曲が流れるときは「戦果」がまがりなりにも報じられる国民生活である。もっぱら「玉砕」という言葉が、国民の将来を覆っていた。
3000機とも4000機ともいわれる残存航空部隊と海上特攻兵器など、陸軍および海軍の戦争継続派は、本土決戦の準備にこれつとめている。
天皇は「本土決戦準備」の現状を知りたくても、参謀総長の上奏がないので心配し、侍従武官の大半を九十九里方面に派遣して視察させている。その結果、軍部が言うほどの準備があるわけではないと、認識を深めていた(「実録」)。
いっぽう、最高戦争指導会議ではソ連を仲介とする和平工作が検討されていた。東郷外相の委嘱をうけた広田弘毅元首相が6月3日から、マリク駐日ソ連大使との会談を開始する。
このほか、中国人繆斌(みょうひん)を通じて、重慶の国民政府との和平交渉のルートを探ろうとした繆斌工作。45年4月シベリア経由で帰国した駐日スウェーデン公使バッゲを通じて、連合国側に和平条件の探りを入れようとしたバッゲ工作。スイス駐在海軍武官藤村義朗中佐らがアメリカの情報謀略機関のアレン・ダレスとの接触を図ったダレス工作などが終戦工作としてあげられるが、いずれも日本政府が正式に取り上げたものではなく、何の成果もあげなかった。
◆けっきょく、原子爆弾がすべてを決めた
これに対して、マリク大使との交渉は正規のものである。広田・マリク対談についで、佐藤尚武駐ソ大使にソ連側との交渉を命じたことから、日ソ両国の正式の交渉となった。
ソ連側からの質問に「和平の斡旋依頼だ」と答えて、近衛文麿を天皇の特派使節として派遣しようとした。しかるにソ連は回答を引き延ばし、交渉はなんら具体化しなかった。周知のとおり、1945年2月のヤルタ会談で、米英に対して対日参戦を約束していたのである。
7月には天皇も戦争継続をあきらめていたが、上記の日ソ交渉に期待がかかり、ポツダム宣言は無視した。そのかん、空襲による国民の犠牲はつづいた。
そして8月6日、人類史を画する蛮行が行なわれる。広島への原爆投下である。さらにソ連が参戦した9日、長崎にも原爆が投下される。ここに至って、ようやく政府首脳(鈴木貫太郎政権)は「聖断」を天皇に請う。
日清・日露・第一次大戦のように軍部だけで戦い、その延長に講和を展望する昭和天皇の戦争指導は、戦略・戦術の全面的な破綻ののちに、ついに国家の壊滅をもって終局したのである。敗戦ではなく、それは大日本帝国の崩壊だった。
それではなぜ、解体した国家の主権者たる天皇が戦争犯罪に問われず、戦後を生き延びたのであろうか。われわれの疑問は尽きない。(つづく)
◎[カテゴリー・リンク]天皇制はどこからやって来たのか
▼横山茂彦(よこやま・しげひこ)
編集者・著述業・歴史研究家。歴史関連の著書・共著に『合戦場の女たち』(情況新書)『軍師・官兵衛に学ぶ経営学』(宝島文庫)『闇の後醍醐銭』(叢文社)『真田丸のナゾ』(サイゾー)『日本史の新常識』(文春新書)『天皇125代全史』(スタンダーズ)『世にも奇妙な日本史』(宙出版)など。