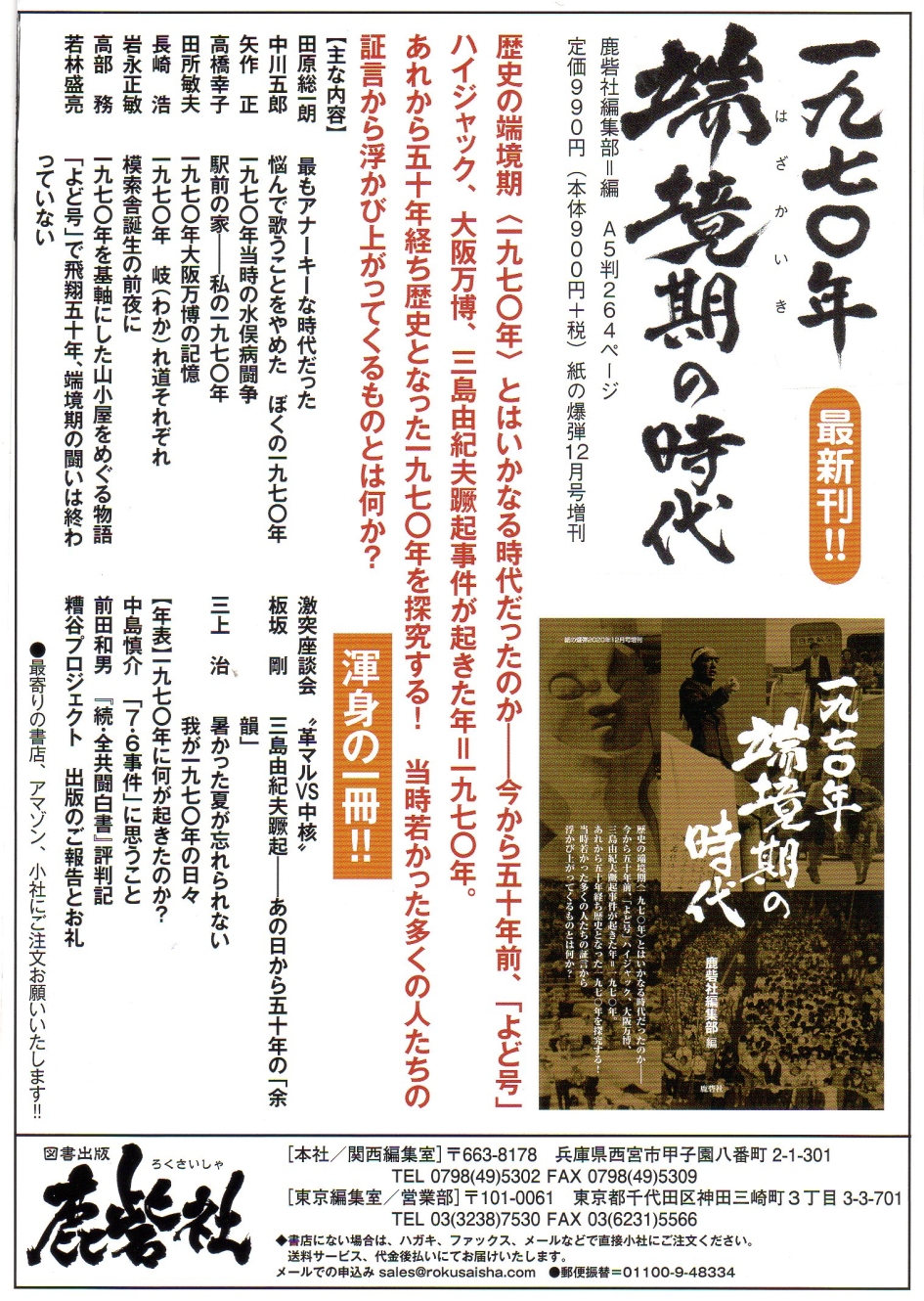◆どんな歌より若者の歌になった“インターナショナル”
私たちの「日本人村」では日本からの訪朝団をよく迎える。「村」の食堂や市内のレストランで歓迎宴、送別宴をやるが、当時の同世代が来るとき最後に締める歌が“インターナショナル”、これをあの頃のように皆で肩を組んで歌って「ああ~インタナショナ~ル 我~らがもの~」と終わって独特の拍子をつけた拍手で締める、あの頃のように。そうやって歌うと今も気持ちが高揚する。“インター”は我らが世代の歌なのだ。
集会やデモではインター、ワルシャワ労働歌、国際学連の歌、この三つが定番だった。
東大安田講堂死守戦の時、冬空の寒風下で機動隊の催涙弾と放水を浴びながら「砦の上に 我らが世界 築き固めよ 勇ましく」のワルシャワ労働歌の一節そのままに「砦の上に~」が実感を以て胸に迫ってきたものだ。
ロック一筋の私だったが、あの頃はもうボブ・ディランもジミ・ヘンドリックスやピンクフロイドも頭から消えていた。“インターナショナル”がどんな歌よりも若者の歌になった季節だった。いまの若い人には想像もできないことだろうと思うが……
◎[参考動画]「インターナショナル」
◎[参考動画]ワルシャワ労働歌(日本語版)
◎[参考動画]【ロシア語】国際学連の歌 (日本語字幕)
◆初めてのデモで心が震えた
ラリーズを去った後、私は集会やデモに参加するようになった。
初めてのデモはちょっと勇気が必要だった。
デモ前にやる同志社明徳館前集会でのアジテーションを遠巻きにする形で聞き入って、集会後のデモに移るとき「ノンポリ学生」が「遠巻き群衆」からデモ隊列に入るのには気恥ずかしさ、躊躇があった。でも思い切ってデモ隊列に飛び込んだ。渡された赤ヘルメットを被りタオルで覆面すれば「デモ隊一員」になった、それはとても不思議な感覚だった。
今出川通りから河原町交差点に差し掛かって京大からの隊列が合流、デモ隊はふくれあがり、突然、河原町通りを埋め尽くすフランス・デモに移った、立命付近で元のデモ隊列に戻るとき、突然、デモ指揮者は向かいの京都府立医大に逃げ込んだ。道路いっぱいに広がるフランス・デモは違法デモ、逮捕されるからだと後で知った。

規制に入った機動隊員は想像以上に暴力的だった。足を蹴る、横腹をこづく……女子学生を隊列の中に入れる理由がわかった、端っこの列は暴力を甘受する覚悟が要るのだということ、反抗すれば威力業務妨害で逮捕されることも。「国家権力」への怒りを身体が感じた。
腕組み皆で声を合わせ叫ぶシュプレッヒコール、「アンポ~ フンサイ」! これを何度も唱和するにつれ芽生える仲間感、一体感、そういうものがあることを初めて知った。「ならあっちに行ってやる」以来の私が初めて実感する「仲間」、「連帯」、「団結」に心も身体も熱くなるという感覚、そんな感情が私にあったことが不思議に思えたが、素直に私は嬉しかった。
初めてのデモで私は多くのことを学んだ。ようやく「おかしいと思う現実は変えるべき」「そのためには行動すべき」、社会革命に一歩、足を踏み入れたことを実感した。
初めて角材、ゲバ棒を持ったのは社学同が組織した6・28ASPAC(アジア太平洋閣僚会議)粉砕・御堂筋闘争だった。
この日、社学同拠点校の同志社から8台のバスを連ね約800名もの同志社大生が大阪市大に結集、拍手で迎えられ市大、関大など大阪の学生と合流、そこから大挙して地下鉄で御堂筋に出て広い大通りをゲバ棒と赤ヘルが埋めた。それは壮観だった。
先頭が交番を襲撃、ガラスを砕いた、突然、ワオーッと機動隊が襲いかかってきた。私はてっきり「これからぶつかるのだ」とゲバ棒を身構えた、が、なんと先頭が崩れみんなは逃げ出した、中にはゲバ棒を捨てるものもいる。これにはちょっとがっかりだったが、闘争は深夜まで裏通りでの市街戦になって、投石戦など機動隊との小競り合いが続き、旗を燃やしたり私たちは気炎を上げた。けっこう見物の市民も参戦したりで私は「大衆暴動」というようなものを体感した。けっして学生だけの孤立した闘いじゃないということも。

東大だけでなく「学生運動不毛の地」と言われていた日大でも全共闘が結成され、党派によらない新しい学生運動が生まれていた。パリではフランス5月革命が燃え盛っていた。
1968年の私は熱い政治の季節の闘いに自分が参加していることを実感できた。
8月に京都でべ平連主催のベトナム反戦国際会議があって、会議後の反戦デモが四条通りの祇園付近に来たとき何ものかが投げた硝酸瓶が私のヘルメットに当たって私の右頬と鼻先が硝酸で焼け、皮膚を焼く異臭と鋭い痛みがあった。付近にいたある学生は背中が焼けただれる重傷を負って病院に運ばれたと後で聞いた。ひりひりする痛みがあったけれど私はデモを続行した。初めてのデモ隊への右翼テロ、初めての負傷を経験した。
その後も秋に伊丹の軍事空港化阻止現地闘争、大阪での大規模な10・21国際反戦デー闘争、また東大闘争支援のため11・22-23安田講堂前全国学生総決起集会に参加、そして翌年1・18-19安田講堂死守戦参加に至る。これは後に触れる。
◆人生に 無駄な ものなど なにひとつない
17歳の無謀な決心「ならあっちに行ってやる」に始まり、二十歳の「跳んでみたいな共同行動」から「裸のラリーズ」結成へ、そして21歳の私がたどり着いたのは社会革命、学生運動。
それはロックと長髪による自分自身の革命、自分を知るための革命を経て「山﨑博昭の死-ジュッパチの衝撃」から社会革命へと連続する私の革命遍歴。それはまるでLike A-Rolling Stone、転がる石ころのような青春遍歴、ある意味「あっちに転がりこっちにぶつかり」の勢い任せ、暗中模索の人生、その当時は自分でもなぜこうなるのかよくわからなかった。
でもボブ・ディラン初恋の人スーズの言う「年齢を経て若い頃の感情や意味、その内容を穏やかに振り返ることができる」年齢になったいま、それは一本の赤い糸でつながるものがあったことがわかる。それは敗戦という急激な変化渦中の日本に生まれた戦後世代特有の体験に基づくものだと、そう思えるようになった
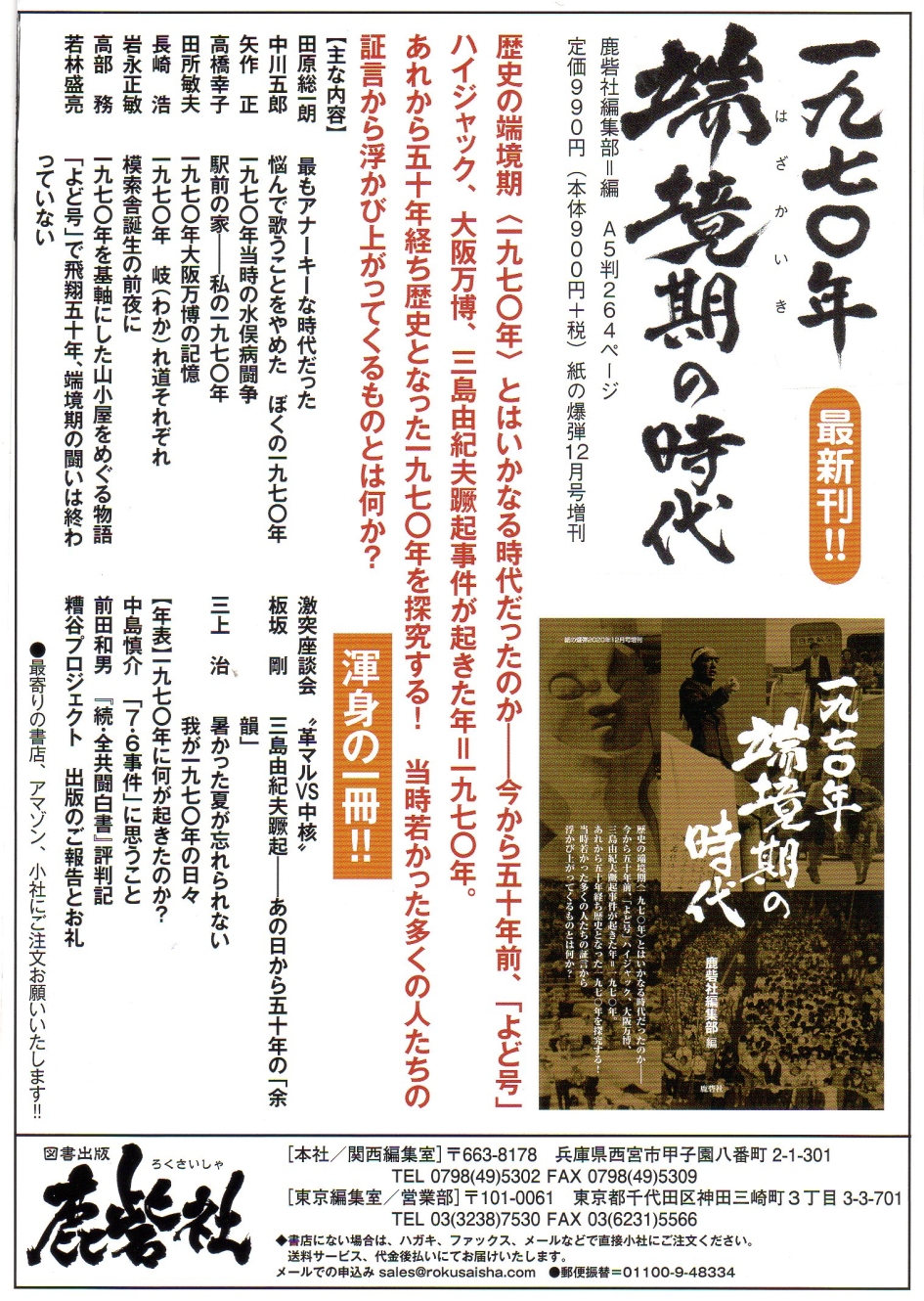
私たち「よど号グループ」はここ十年ほどの間に必要に迫られて様々な形で手記を書いてきた。動機は自分たちにかけられた「北朝鮮の工作員」「拉致」疑惑を解く必要性があったからだ。それは自分自身を知る過程でもあった。『拉致疑惑と帰国』(河出書房新社)、『追想にあらず』(講談社エディトリアル)、『一九七〇年-端境期の時代』(鹿砦社)がそれだ。これら手記を書く過程で、これまで記憶の引き出しにしまって置いた個々バラバラの様々な事象、「若い頃の感情や意味、その内容」が自分の人生の中で必然の糸でつながっている、そう思えるようになった。この連載手記、「京都の青春記」もそのようなもの。様々な出来事、出会いがあって今日の私がある、だから残りの人生を自分はどう生きるべきか? それを自己確認する作業でもある。
鹿砦社「今月の言葉」に「人生に 無駄な ものなど なにひとつない」と書に記した龍一郎さんの言葉にはうなづけるものがある。
生まれてこの方、順風満帆の人生だったという人はほぼいないだろう。人生には逸脱も曲折も失敗もある、けれどそれらに「無駄なものなど何ひとつない」、それらがあって現在の自分があるのだから。「失敗は成功の元」-むしろ曲折や失敗は自分の問題点がわかり教訓を得る絶好のチャンスだとさえ言える。もしもそれらが無駄なものと思えるようなら、それは何の更生力もないまま今も漫然と人生を無駄に過ごしていると自ら認めることではないだろうか? でも人間とはそんなもんじゃないと私は信じたい。

◆「人の目を欺いてはいけない」! 戦後日本は「おかしい」から革命すべき対象へ
森羅万象の生起、変化には必ず原因があり、人間の考えや行動、その生起、変化発展には動機、契機、理由が必ずある。
「時空を越える“黒”」で有名なファッション・デザイナー山本耀司、彼の“黒”へのこだわりの原点は、彼の5歳の頃の強烈な体験にあったという。
山本耀司の父親は戦争中、出征途上の輸送船が米軍に撃沈されて戦場に着く前に「戦死」、遺骨も遺品も残らなかった。敗戦後、「元司令官」が「父の戦死」を彼の母親に伝えに来たという。この時、「ケッ!」と5歳の耀司は心の中でツバを吐いた。この時から大人への強烈な怒り、不信感が芽生えたという。戦後、洋裁店経営で家計を支える母を手伝う中、山本耀司はファッション・デザイナーを志した。戦後の日本には欧米から華やかなファッションが流入してきた。そんな時代にデザイナーを志した自分の心構えを彼はこう語った。
「飾り立てるのがファッションかもしれないが、人の目を欺いてはいけない」
軍国主義日本から民主主義日本へと華やかな「転換」を遂げた戦後日本、でも「人の目を欺いてはいけない」-これが“黒”へのこだわり、「時空を越える“黒”」ファッション、山本耀司の立ち位置なのだろう。
◎[参考動画]YOHJI YAMAMOTO pour homme S/S2023
私には山本耀司のような強烈な体験はないが、「人の目を欺いてはいけない」という彼の言葉は、同じ戦後世代としてストンと胸に落ちる。
日本の敗戦から2年、1947年2月生まれの私は、米軍占領下で軍国主義日本から民主主義日本に急転換する混沌とした時期に生まれ少年期を過ごした世代だ。大人たちの頭も時勢の急激な変化についていけなかった時代だった。
私が物心のついた頃、いまも鮮明な記憶に残っている出来事があった。たしか小学5年の頃だ。
授業の合間にある教師が自分の軍隊体験を語り出した。それは中国人捕虜を使って刺殺訓練をやった話だった。
「いいか、刺した銃剣を抜くときはくるっと回転させて抜くんだ」とその教師は「銃剣刺殺要領」を私たち小学生に何の悪気もなく語った。
子供心にも何か違和感を覚えた。でも小学5年生にそれが何かはわかるはずもなかった。いまも鮮明に覚えているということはかなり「衝撃的な体験」だったのだろう。
その教師はといえば、自主的に壁新聞を作るように生徒たちを指導した「戦後民主主義教育のリーダー」的存在だった人だ。私もクラスの壁新聞に家で購読していた毎日小学生新聞を参考にソ連のライカ犬搭載の人工衛星、ガガーリン少佐の有人衛星の世界初成功などの記事を書いた。生徒任せの壁新聞作りは自由でとても面白かった。私にとって「いい先生」だった教師だけに、あの日の授業中に覚えた違和感はいつまでも心に残る衝撃的な体験だったのだと思う。
教師にしてみれば、当時の中国人捕虜は「反日分子=犯罪者」であり、「刺殺」対象として何の呵責も感じない「日本の敵」、刺殺は日本軍兵士として当然の行為だったのだろう。だから生徒たちにも悪びれもせず話せたのだと思う。
中学の社会科で日本史を教えた教師はただただ黒板に年表を書き連ねるだけ、そんな授業をやった。いま思えば、おそらく皇国史観から戦後民主主義史観への激変についていけなかったのだろう、あるいはそれへの「抵抗運動」? おかげで日本史は私のつまらない、嫌いな科目になった。
大人達の頭の中でも軍国主義の脱却も民主主義の消化も不十分なまま両者が何の矛盾もなく混在していた。
私の父は実直な勤王家で軍服姿の昭和天皇夫妻の写真が戦後も客間に飾ってあったし、戦後すぐの昭和天皇の全国行幸時も「お召し列車」が通過するというので幼い私を連れて線路脇で最敬礼をした。明治生まれの父は戦争末期に徴兵検査を受け丙種不合格、それで徴用工としてコンデンサー工場に動員されあの戦争を生き延びた。戦場から帰れなかった同世代へのひけめ、罪悪感のようなものがあったのだろう。父は息子に何も語らなかった。
一方、母は私に「日本はアメリカに負けてよかったんだよ」と話した。母の兄、醤油醸造業の実家の跡取り息子はビルマ(現在のミュンマー)で戦死、結果として母は自分の長女、私の姉を「将来、婿養子をとって家業を継ぐ」養女として母の実家に差し出さざるをえなかった。そんな母の二重の悲しみがそんな言葉を吐き出させたのだろう。
一家庭の中にも軍国主義日本と民主主義日本が混在、併存する、これが戦後日本のおかしな実相だった。
私自身も記録映画に出てくる特攻隊出撃シーンに「海ゆかば」のメロディが流れると感動で涙がにじんだ。他方で私は姉の聴いていたアメリカン・ポップスの世界に惹かれていた。戦後世代の私の頭の中も混沌としていた。
60年代に入ると世は高度経済成長時代、東京オリンピックで高速道路や新幹線ができ、次は大阪万博へ、テレビ+洗濯機+冷蔵庫の「三種の神器」が家庭の夢となり、一戸建てマイホームを持つことがサラリーマンの夢になった。昼間の日本は「アメリカに追いつき追い越せ」に浮かれていた。
小学校のすぐ横に「忠魂碑」という出征兵士を祀る石塔を囲む小さな森があった。でもそこはアベックが変なことをやるところだから子供は近寄ってはいけないと言われた。「忠魂碑+男女アベック=近寄ってはいけない忠魂碑」-みんな敗戦など忘れてしまったかのような「明るい日本」の象徴??
高校生の頃、ケネディ暗殺があってその暗殺犯がまた警察署内でピストル射殺されて大統領暗殺事件は闇の中に。米国南部の黒人は白人専用の食堂やバスは利用できず、その掟を破れば暴力を受けたたき出されていた。黒人公民権運動の活動家が南部で殺される事件もあった。
少年期に憧れたアメリカは「追いつき追い越す」ほどのものじゃなくなった。
羨ましかったアメリカ中産階級のホームドラマや甘いアメリカンポップ音楽は色あせて、英国の港町リヴァプール労働者階級の息子たちの不良っぽいロックバンド、ビートルズへと私の関心は移った。
ベトナム戦争の激化は「戦後日本はおかしい」をさらに深く考えさせるものだった。憲法9条平和国家の日本は戦争をしない国になったと学校で教わった、でも在日米軍基地はこの戦争の基地になっている、日本は戦争加担国家になった、日米安保のために……。
「ならあっちに行ってやる」と進学校、受験勉強からドロップアウトを決めた17歳の無謀な決心、それは昼間の日本への違和感、「戦後日本はどこかおかしい」── 私の無意識の意識の爆発だったのだろうと思う。
そして「ジュッパチの衝撃」で「戦後日本」は革命すべき対象になった、漠然とだがそう私に意識されたのは確かだ。
◆“True Colors”── あなたの色はきっと輝く
熱い政治の季節の渦中に飛び込んだ私ではあるが、1968年の私はまだ五里霧中にあった。
集会やデモもいつも個人参加、まだ政治を知らず組織に属さない人間が政治活動を続けるのはやはり不自然なことだった。政治を議論する仲間、政治活動を教え、次の集会やデモの意義を教えてくれる組織を持たない人間は「野次馬」以上にはなれない。『朝日ジャーナル』や『現代の眼』といった政治雑誌を読むくらいの私はそんなものだった。
4回生にもなった学生は活動家の政治オルグの対象にならない、ましてやヒッピー風の長髪人間は対象外だろう。かといって自分で訪ねていくことも気が引けた、社学同に入る理由も話せない、まだ「敷居は高い」まま。
ある時、前日のデモで使用したヘルメットを返しに学友会・自治会室を訪ねたことがある。活動家たちはあっけにとられたことだろう。ぽかんとした顔を向けただけ、ヘルメットを返しに自治会室を訪ねる学生なんてやはり「変な奴」なのだ。たぶん私は「声をかけられる」ことを内心、期待したのかもしれない。
当時の私は中途半端な位置にいる自分に焦れていた。一言でいって志と孤独の間を揺れていた。どうしようもない非力さを痛感する日々、依拠すべき同志も組織もないというのは致命的だった。
そんな苦闘中のある日、バイト帰りの河原町正面・市電停留所で「あら~Bちゃん! 久しぶり~」と声をかけられた。見ると以前、私の常連バイト先で事務員をやっていた菫(すみれ)ちゃん(仮名)だった。
「Bちゃん」というのは「ビートルズ」を略した愛称、バイト職場で職人のおっちゃんたちが親愛を込めて呼んだ私のニックネーム、菫ちゃんは昼食時間にバイトの私にもお茶を煎れてくれたりしてた、たった一輪の「職場の花」だった子。一緒に市電に乗ってお互いの近況を話した。一年ほど前に職場を辞めた菫ちゃん、いまは木屋町にある喫茶店で働いているのだとかで「一度来てみて~」と私に言った。
それからはデモ帰りなどに彼女の喫茶店に立ち寄るようになった。デモが終われば所属組織毎に集まって総括したり集団で帰路に就いたりしたが、私には行くところがなかった。そんな孤独を抱える私には恰好の「帰る所」になった彼女の喫茶店、顔馴染みがいるというだけで癒された。
仕事中のウェートレス、菫ちゃんとはそれほど話はできなかったが、ある時、彼女が演劇をやっていることを知った。
京都のある劇団に所属し、いまは若手研究生の菫ちゃんは演劇女優をめざす「俳優の卵」。劇団に通う時間を得るために喫茶店のバイトに切り替え事務員定職を捨てた菫ちゃん、いまは厳しいけど絶対、舞台女優になるんだと楽しそうに意気込みを語ってくれた。地味な事務員服姿からはうかがい知れなかった彼女のアナザーサイド、「へ~え、そうなんや」! ちょっとした驚き、彼女がまぶしく見えた。
菫ちゃんにそんな大きな夢があったんや! なんか感動した。
年末には大きな演劇イベントがあってその舞台でいい役に抜擢されることがいまの彼女の目標らしかった。彼女は「俳優の卵」、なら私はさしずめ「革命家の卵」、なにか急に二人の距離感がぐっと縮まった。まだ何ものでもない「卵」たち、けれど懸命に孵化をめざす「卵」同士、お互い頑張ろうね! そんな感じの二つの魂の接近。
「Bちゃんはアホやなあ」!
これは菫ちゃんのお言葉。
4回生にもなって就職活動もしない長髪大学生、組織にも属さないのにデモや集会に参加するという私を菫ちゃんは、「Bちゃんはアホやなあ」と言った。同志社大卒男子なら就職先は選り取りみどり、高卒女子の彼女からすれば羨ましい身分、でもそれに背を向けて自分がどうなるかもわからない政治活動をやってる私は「ほんまアホやなあ」ということ。
でもそれは菫ちゃん式の誉め言葉。
長髪人間の私だが、遊び人だとかいい加減な大学生でないことは職場での私の働きぶりで彼女は知っている。彼女もいた私のバイト先は矢野洋行、「貸し物屋」という京都特有のイベント業者、京都三大祭り行事準備や和装展示会、生け花展示会ほか様々なイベント用資材を貸し出し設営もする仕事、私は古都独特のそんな仕事が好きだった。だから学生バイトとはいえ仕事は真面目にやって一応精通した。だから社長の父親、会長の爺ちゃんからは「いつでも来てエエで」と重宝がられ、会社は準社員並みに扱ってくれた。職場での「Bちゃん」の愛称はその賜物、会長も私をそう呼んだ、そのことを菫ちゃんは知っている。
そして「俳優の卵」苦闘中の彼女は夢や志に向かう青春がなめる苦も味わう楽も知っている菫ちゃん。
“TRUE COLORS”というシンディ・ローパーのヒット曲がある。
悲しそうな目ね
弱気にならないでほしいの
難しいよね
自分らしく生きるって
…………
true colors /あなたの本当の色は
are beautiful /美しい
like a rainbow / 虹のよう
まるで菫ちゃんが歌ってくれてるような言葉の並ぶ“TRUE COLORS”!
彼女の「アホやなあ」、それは「あなたの本当の色は美しい」-“that’s why I love you”「私の大好きな色」という有り難いお言葉。
もしおかしくなって 耐えられなかったら 私を呼んで すぐ行くから
おかしくなりそうなとき、“you call me up”-いつでも“私を呼んで”、Bちゃんがいつでも訪ねられる人、”because you know I’ll be there”-“すぐ行くから”と私に安心、自信をくれる菫ちゃん。
「アホやなあ」と言いながら、いつしかデモで破れたジーンズを繕ってくれたりするようになった。私は菫ちゃんが次の大舞台でいい役がとれますようにと祈った。
「革命家の卵」と「俳優の卵」、まだ何ものでもない孵化を競い合う「卵」同士、その大きな夢と志はこの先どうなるのかはわからない。でもかまわない、とにかく前に進もう!
「あなたの色はきっと輝く」、そのことを互いに信じて……(つづく)
◎[参考動画]Cyndi Lauper – True Colors (from Live…At Last)
〈01〉ビートルズ「抱きしめたい」17歳の革命
〈02〉「しあんくれ~る」-ニーナ・シモンの取り持つ奇妙な出会い
〈03〉仁奈(にな)詩手帖 ─「跳んでみたいな」共同行動
〈04〉10・8羽田闘争「山﨑博昭の死」の衝撃
〈05〉裸のラリーズ、それは「ジュッパチの衝撃」の化学融合
〈06〉裸のラリーズ ”yodo-go-a-go-go”── 愛することと信じることは……
〈07〉“インターナショナル“+”True Colors”= あなたの色はきっと輝く

▼若林盛亮(わかばやし・もりあき)さん
1947年2月滋賀県生れ、長髪問題契機に進学校ドロップアウト、同志社大入学後「裸のラリーズ」結成を経て東大安田講堂で逮捕、1970年によど号赤軍として渡朝、現在「かりの会」「アジアの内の日本の会」会員。HP「ようこそ、よど号日本人村」で情報発信中。