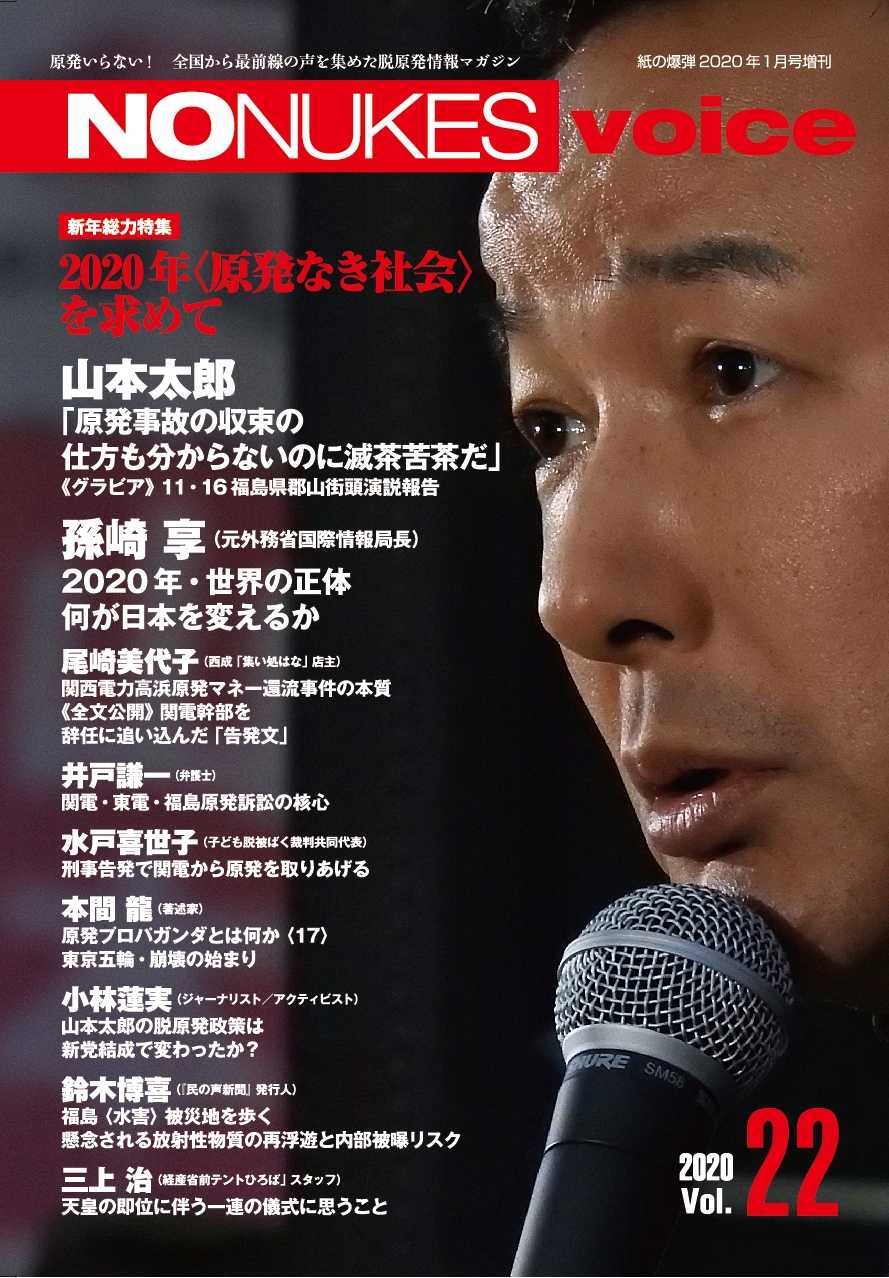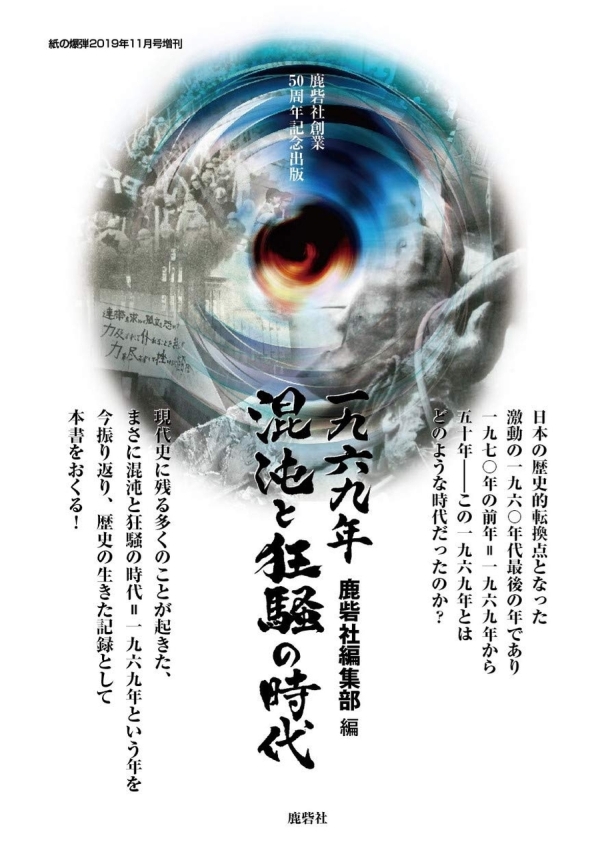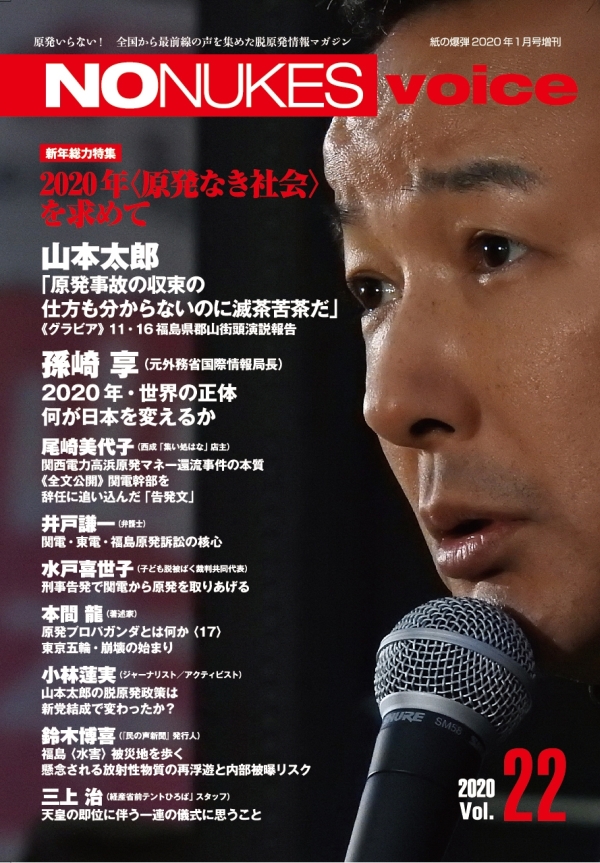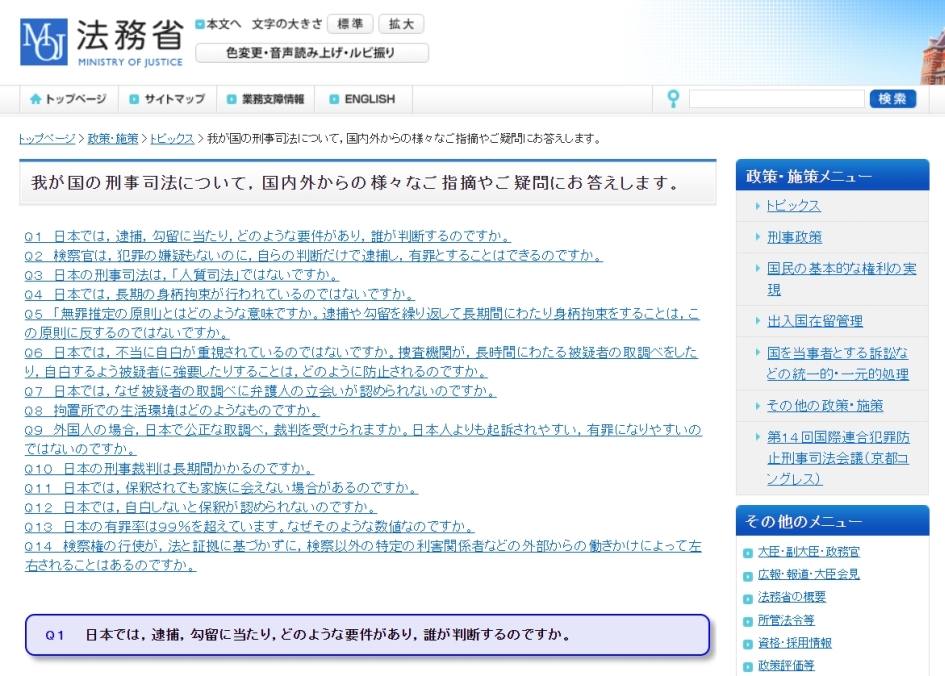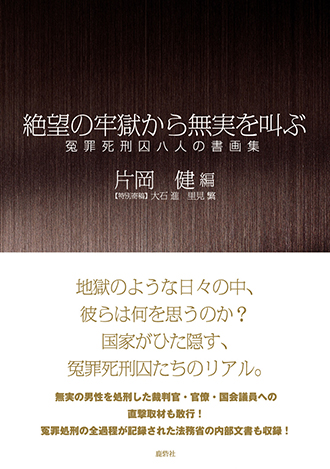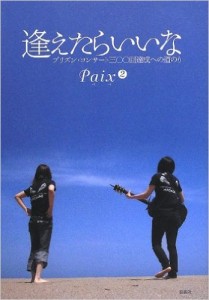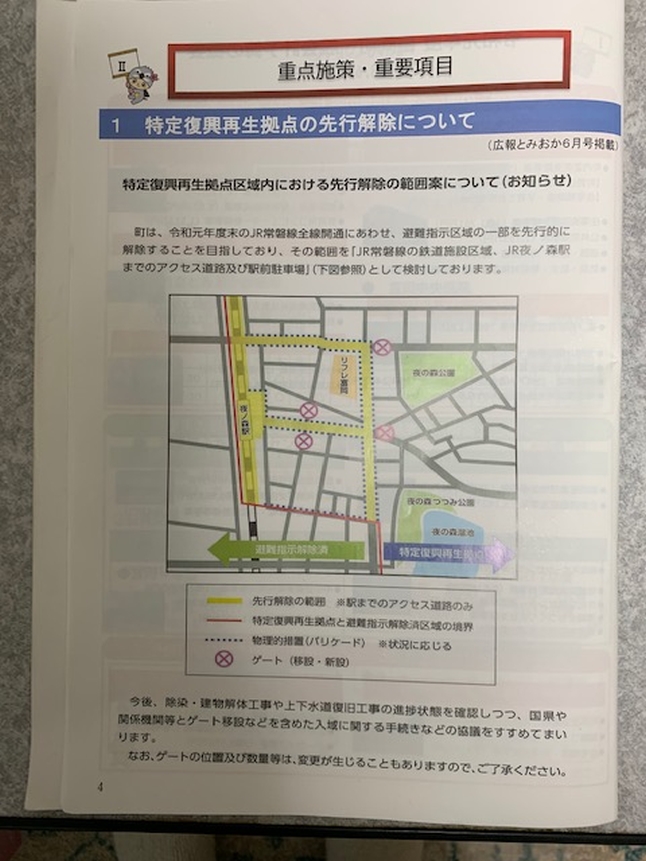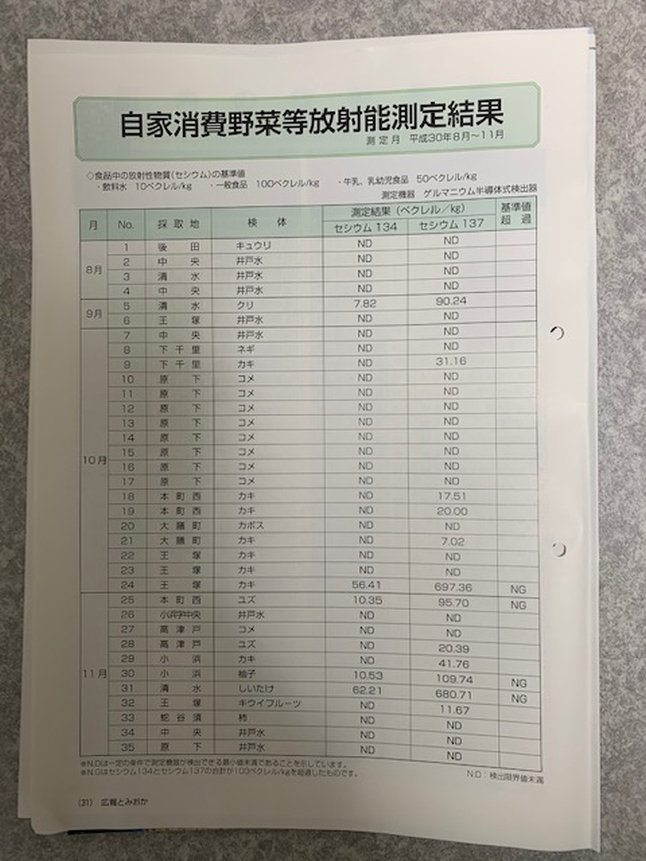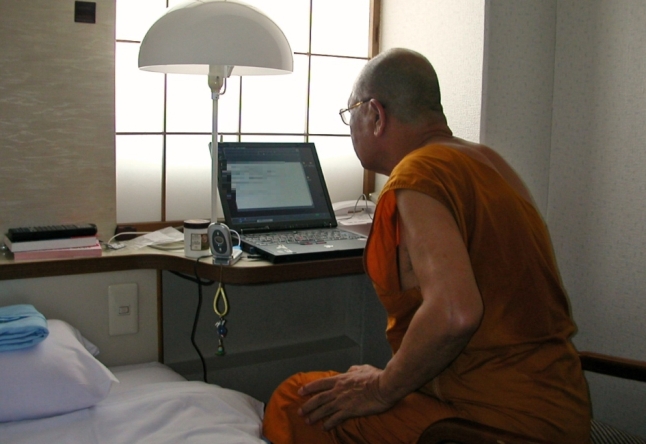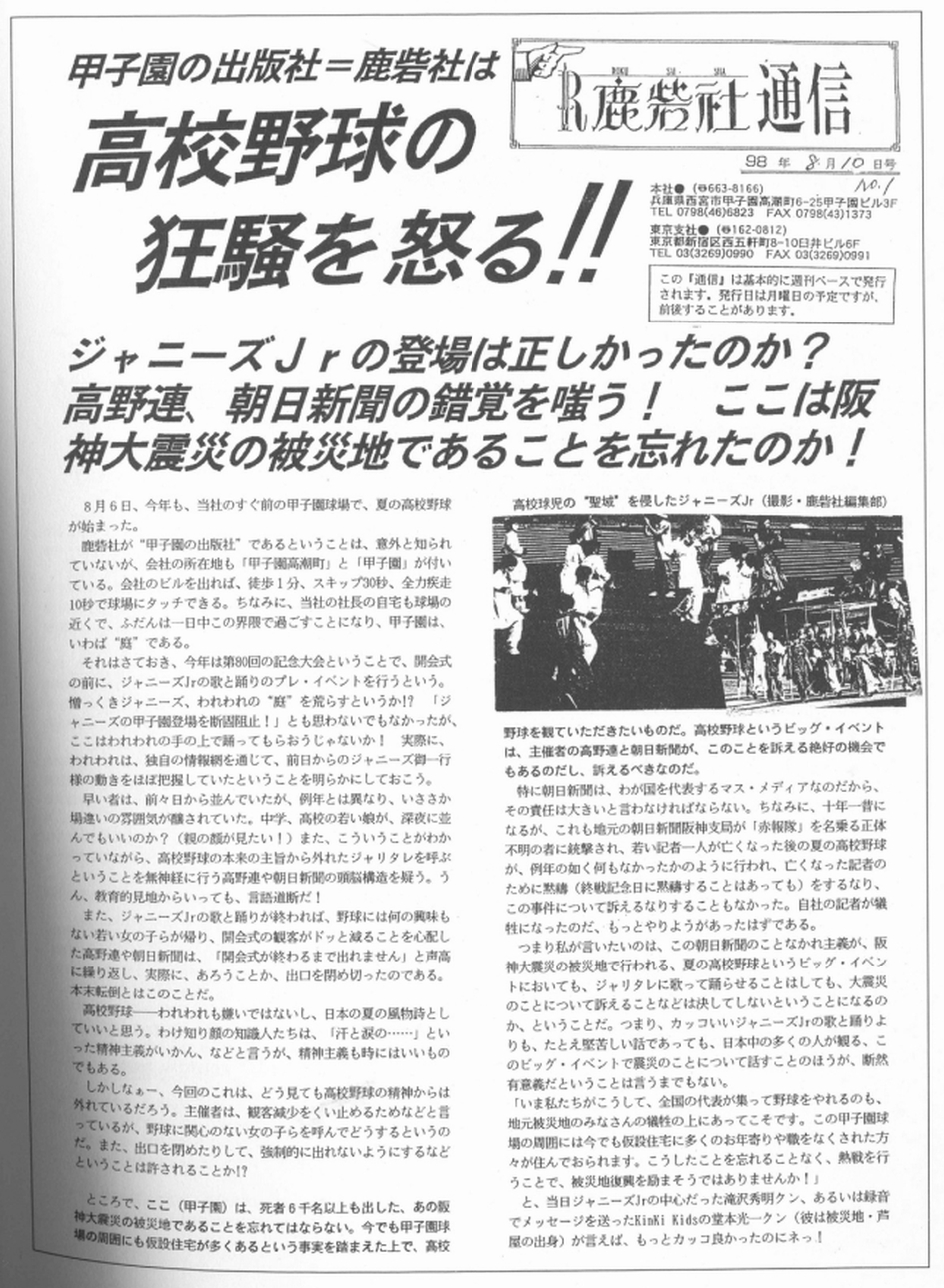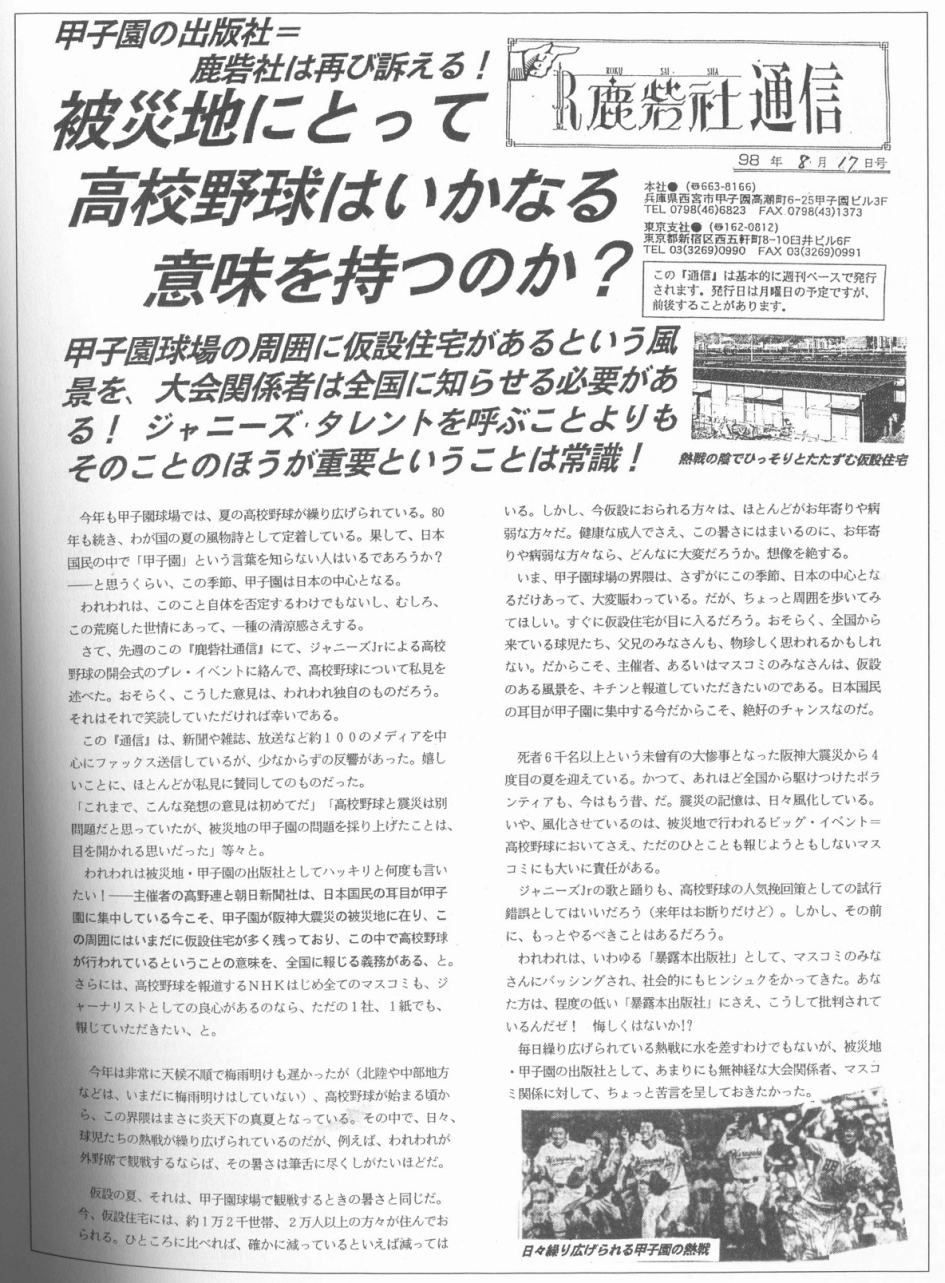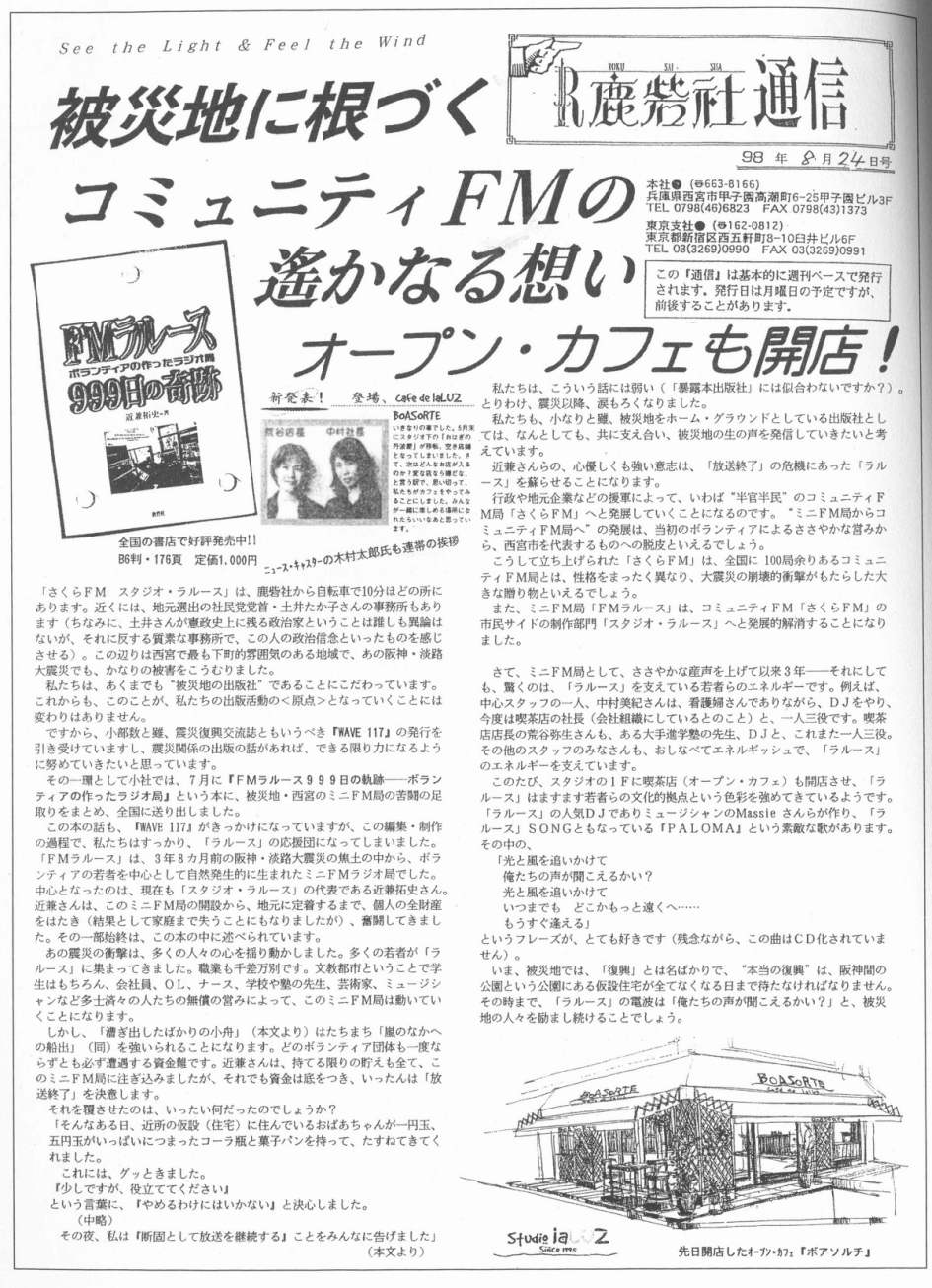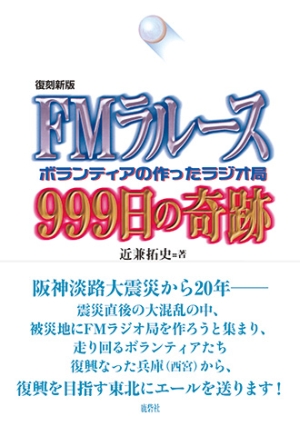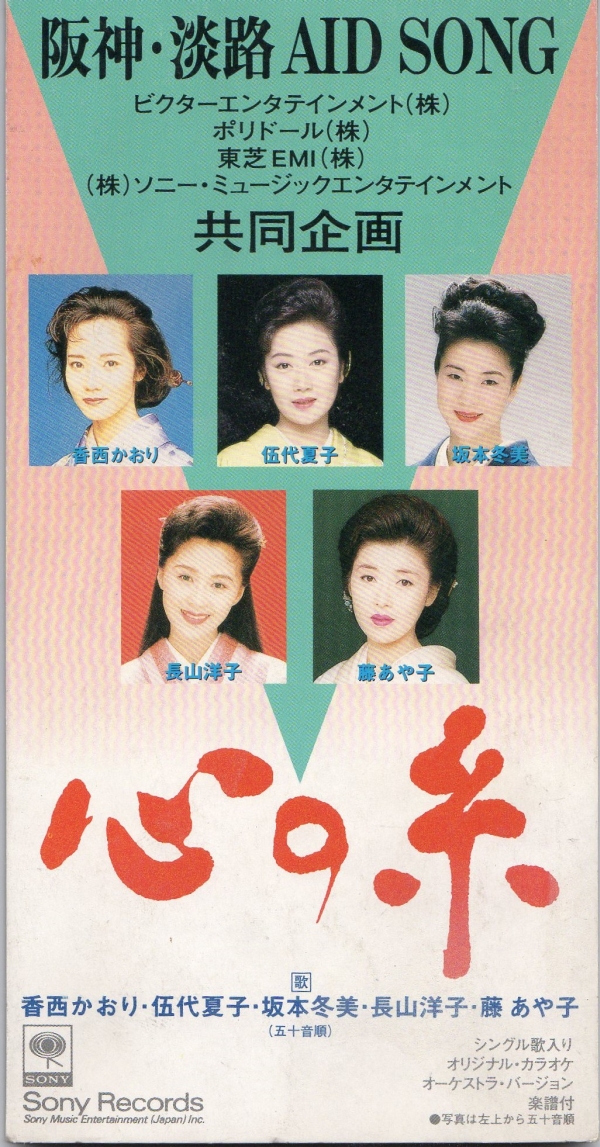江戸期いらいの博徒が戦後にいたって一変したのは、そのまま戦後社会の変容を映し出しているといえよう。
最初に戦後の闇市を取り仕切ったのは、伝統的な極道の流れではなかった。愚連隊とか特攻隊崩れとかの血気盛んな連中が、無秩序な闇市を取り仕切ることで警察組織の代用をはたしたのである。盗みやかっさらいの横行するアンダーグラウンドの市場には警察力が必要だったが、その警察は闇市を取り締まり、取り締まった戦果を自分の懐に入れることはあっても、飢えた民衆の必要を満たしてくれるわけではなかった。そこで私設の警察組織が、闇市の庇護者として設立されたのである。
どんな商売も市場がある以上は、需要がなければ存立しえない。
遠く農村から列車に乗って闇市に米を売りにきた女性が、乱暴者から商品たる米を奪われたとしよう。警察に届けても面倒をみてくれないどころか、闇米はすべて没収されて、へたをすれば彼女自身も逮捕されてしまうのである。そこで市場を取り仕切る愚連隊の親分にすがって、米を取り戻してもらうことになるのだが、そのついでに少しばかり上納金を差し出すことに何の不思議もない。必要経費ともいうべき、当然の手間賃である。
ときには愚連隊同士の縄張りやイザコザで拳銃を乱射されたり、取り締まりの警察隊との銃撃戦もある異常な時代だったが、日常的なトラブルは彼女がしたように必要経費で処理され、それで食いぶちが満たされれば何の問題もないのである。商売のトラブルが市を成り立たせなくなったのでは、人々は飢えて死ぬしかない。当時の日本人の食料は、そのほとんどが闇市の食料で賄われていたのだから。
こうして闇市を支配していた愚連隊を、やがて伝統的な博徒組織が吸収していく。
実力を持った若い集団が、いろいろと能書きやしきたりなど伝統文化を持つ集団に合流して、本格的に極道の代紋を背負うことになったのである。戦争で国家とともに滅びかけていた博徒集団にしてみれば、これで新しい職域への進出と若々しい血を入れることになった。
◆田岡一雄がつくった戦後ヤクザ
人々の飢えがみたされて闇市が終焉すると、戦後復興の時代である。日本最大の広域暴力団とされる山口組の勢力を飛躍的に拡大したのは、一九五九年に勃発した朝鮮戦争だった。
港に入った船に一番乗りしたグループが積み荷の運搬を請け負うという、荒っぽい沖仲士の荷受け業界に初代のころから参入していた山口組は、斬新な組織論において他の組織の追随を許さなかった。旧来の極道組織の子分が子分をもうけて分立していく組織作りの方法を避け、山口組は表向きは会社組織として分社し、裏組織を一元的に統括した。表向きは近代的な企業でありながら、しかも普通の企業にはできない義理の親子の拘束性がある。この立役者が三代目山口組の袖主田岡一雄だった。
朝鮮戦争の拡大とともに港湾荷役は需要が増大し、規制緩和の機会を得た山口組は二次下請けの立場から一次下請けへの参入に成功する。海運局に掛け合って、下請けの枠組みを取り払わせてしまうのである。さらには、左翼の労働組合に対抗する労働組合を結成し、この力を背景に、彼の組織は左翼のみならず他の業者を圧倒したという。
事故が起これば船会社と交渉するのも山口組の労働組合なら、海運会社の仕事を最大業者として受けるのも山口組傘下の企業という具合に、彼らは神戸港の支配をテコに全国の港湾を掌握していく。
さらに、当時のエネルギー産業の基幹である炭鉱労働者の組織化に着手する。いわば職能組合とか産別労組の全国展開とまるで同じ組織づくりで、高度経済成長をもたらす労働力を支配し、今日の隆盛の礎になる全国組織の最初の骨格を作ったのである。
膨大な労働力(人集め)を必要とする大資本にしてみれば、労働者が左翼に牛耳られて革命騒動を起こされるよりは、山口組のほうがずっといいに決まっている。事実、あとでみるように共産党は朝鮮戦争に乗じて武装闘争の方針で動いていたし、革命前夜のような暴動が各地に生起していた。
それでなくても、沖仲士や炭鉱労働者は普通の社員では扱いにくいし、荒っぽい連中の喧嘩騒ぎや揉め事には困っているのだから、旧財閥系の御大も、ここはひとつ山口さんとこの力でなんとか、ということになったのは想像にかたくない。
組織が拡大していくためには、荒っぽい暴力も必要である。ここでは柳川組という武闘派組織が山口組の組織拡大を牽引したのだった。ちなみに柳川組は在日朝鮮人を主体とする組織で、のちにみる共産党の極左戦術を先頭でになったのが在日朝鮮人たちだったのを考えると、異郷に強制連行された彼らこそが、混乱期にたくましい生き方をしめしたことになるかもしれない。
◎[参考動画]「山口組三代目」(1973年08月11日公開)予告篇
つぎに三代目山口組組長田岡一雄が取り組んだのは、これも有名な話だが力道三のプロレス興行や美空ひばりのステージを取り仕切る芸能興行だった。朝鮮戦争の軍事特需をへて、戦後復興なった日本には、大衆消費社会の波がすぐそこまで来ていた。
隙間産業のような職域が時代の需要になったときに、正業を持たない極道組織が持てる組織力と荒っぽいが面倒な仕事に乗り出すのである。利権と暴力が衣の下から透けて見えるような、あやうい職域を仕切ることができるのは、目先の銭金よりも厳しく統制された組織であり、それを可能とする伝統的な作法と形式の力にほかならない。生き方の中に極道としてのプロフェッショナルの気風が充満していれば、もはや怖いものは何もない。組織に生きることが、彼らの正義であり世の中をみる尺度なのである。
これが通常の会社組織であれば、仕事の成否も労働者の去就も賃金をめぐる一点にしかない。業績がはかばかしくない企業からは、沈みかけた難破船から鼠が逃げ出すがごとく優秀な社員はいなくなってしまうし、有力な企業には有為な人材が集まるのが労働市場の原理である。
ところが極道の社会は利益集団でありながら、そこに擬制の血縁関係をつくり出すことによって成立している。破門か絶縁の処分をされないかぎり、親子の縁は切っても切れない。これが極道組織をプロフェッショナルの集団たらしめる原理である。
親が殺せといえば子は殺人犯になるのが正義であり、親が死ねといえば、まあこればかりはゴメンと逃げ出すかもしれないが、破門や絶縁の処分をされないかぎり子分であることに変わりがない。このようにして保存された親子の縁と義理、兄弟の絆が、戦後の保守政治にマッチしていた。自民党とその政府はヤクザを手の内に取り入れることで、選挙のみならず政争を生きのびることになるのだ。次回は自民党のヤクザへの接近と裏切りを、国家という原理から解説していこう。
◎[参考動画] プロレスリング日本選手権 “昭和の巌流島”(1954年12月22日)
「反社会勢力」という虚構
▼横山茂彦(よこやま しげひこ)
著述業、雑誌編集者。近著に『ガンになりにくい食生活』(鹿砦社ライブラリー)『男組の時代――番長たちが元気だった季節』(明月堂書店)など。