第二次世界大戦後の戦争を象徴した朝鮮戦争は休戦後70年、いまだ継続している。同じく冷戦のさなかに戦われたベトナム戦争は15年、新冷戦のなかで行われたソ連のアフガニスタン侵攻は10年。パレスチナ紛争も、イスラエル建国(1948年)によるシオニストの侵略を発端とするならば、じつに74年間におよぶ。
そしていま、ウクライナ戦争も一時的な紛争にとまらず、長期にわる本格的な戦争となった。ロシアのクリミア併合以降の紛争を数えれば、すでに9年目ということになる。
その長期にわたる災禍の中で、本通信でも指摘してきた反戦運動の理論的な混乱は、いまなお続いている。ロシアも悪いが、アメリカ(NATO)とゼレンスキー政権も悪い、というものだ。どっちもどっちなのだから、ウクライナとその人民を支援する必要もないと。何と冷淡なことだろうか。
かつてベトナム戦争において、日本の反戦運動はアメリカの軍事介入・北爆に反対してきた。南ベトナム民族解放戦線と北ベトナムがたとえ、中国やソ連(当時はスターリン主義と呼ばれた)に支援されていたとしても、帝国主義の植民地主義に反対するべきであると、闘うベトナム革命勢力を支援してきた。
それゆえに、多少の温度差はあれ、75年4月30日の解放勢力の勝利(アメリカの敗退)を、誰もが祝福したのだった。
ところが、そのベトナムがカンボジアに侵攻したとき、これを批判する反戦運動は数少なかった。さらに中国がベトナムを懲罰(国境侵犯)したときも、中国を批判する反戦運動はさらに少なかった。ソ連のアフガニスタン侵攻を批判した反戦運動は、中国派とされる一部の左翼だけだった。
こうしてみると、かつて世界の警察官を自認したアメリカ帝国主義は批判しても、元社会主義国のロシアや中国の覇権主義には、何となく批判の矛先が向きにくいということになるようだ。
とくにわが国においては、アメリカ・NATOの世界支配に反対し、アメリカに追随する日本政府の軍事大国化を批判する、ここに視点が置かれがちなのがわかる。けだし当然である。わが国が米軍の駐留下(沖縄米軍基地)におかれ、日米安保体制においてアメリカの戦争に加担することが、憲法9条をはじめとする反戦平和主義に反するからにほかならない。
だが、アメリカを批判するあまり、プーチンの戦争を免罪する。あるいは習近平の中国帝国主義を批判しない傾向もまた顕著である。これはきわめて危険だと思う。その結果、第二次大戦時のヒトラー政権にも匹敵するプーチン独裁、習近平独裁にも批判が向かない。やがて国論が戦争挑発国家の擁護となるのだ。
旧ソ連派の一部には、アメリカよりも民主主義がなくても、ロシアのほうがましだ。たとい中国や北朝鮮が独裁国であっても、日本はかつて侵略国だったのだから、それを反省して中国や北朝鮮を尊重すべき、などと。結果的に、歴史的事実(侵略)と現状の国家(個人独裁)を混同してしまう傾向も顕著である。
あるいはアメリカ帝国主義を批判するあまり、プーチンの侵略戦争を免罪する。その典型的な例を、このかん私が批判してきた共産同首都圏委員会を例に、できるだけわかりやすく解説しよう。
新左翼内の論争という、いまやニッチなジャンルに興味のある方は、ぜひどうぞ。
◆改ざんの釈明・誤記の訂正拒否を「組織的に決定」した(?)首都圏委
わたしは『情況』誌、および本通信において、共産同首都圏委のウクライナ戦争への見解を批判し、なおかつ「反批判」における論旨改ざん(論文不正)と誤記(出典文献の誤記・版元名間違い)を指摘してきた。
◎『情況』第5期終刊と鹿砦社への謝辞 ── 第6期創刊にご期待ください〈後編〉(横山茂彦2022年10月26日)
ところが、ある人を介して聞いたところによると、首都圏委は「横山の批判には反論しない」「論争はしない」と「組織的に決定した」のだという。
『情況』(2022年夏号)でほぼ完全に論破されているのだから、論争に応じたくないのは勝手だが、誤りはきちんと訂正しなければならない。彼らの機関紙の最新号「radical chic」(47号=12月末日発行・1月末配送)には、論旨改ざんの釈明はおろか、引用文の誤記(引用の誤読・誤植・版元名の間違い)についても訂正がないのだ。これはダメだろう。
にわかには信じがたいことだが、もしも組織的に「論旨改ざん、誤記の訂正もしない」と決定したのならば、「radical chic」は、ただちに廃刊されてしかるべきである。
論文不正や誤記を訂正できないのであれば、およそ報道や主張を発信する資格はない。単に倫理的なことを言っているのではない。デマや誤報が読み手をまどわし、思想表現の自由を阻害するからである。歴史的な記録としても、後世の読者を欺くことになるのだ。
ロシアや中国、北朝鮮といった専制独裁国家においては、報道の自由や思想表現の自由はない。フェイクと言論弾圧、そして事実の捏造、誤報の放置である。
その意味で、いかに政権に腐敗や堕落があるとはいえ、日本には民主主義的基礎として報道の自由が健在である。その報道の自由とは、事実の報道・誤報を訂正できる情報発信者の原則、絶え間ない努力に担保され、支えられているのだ。首都圏委の誤記の訂正放棄という行為は、これらを掘り崩すものにほかならない。
この件について、首都圏委が何ら対応できないのであれば、上記の批判と警告をくり返さざるを得ない。ジャーナリストとして、あるいは出版人として、首都圏委の諸君の厳正な反省と善処をもとめたい。
◆政治論文の基本を教えよう
さて、その首都圏委の主張を検証してみよう。
その前にそもそも政治主張になっているのかどうかを、吟味する必要があるだろう。およそ政治論文というものは、「主張」が明確でなければならないからだ。主張が明確であるためには何をしなければならないのか、論文作法の基本に立ち返って解説しておこう。
まずは、論文の初歩から教示する。論文であれば、他の研究者の主張・論脈と自分の主張を明確に区分する必要がある(正確な引用・引用した文責の明確化)。そのうえで、研究論文には独自の「考察」「研究」が求められる。この考察・研究がない論文は、査読段階で引っかかる。論文の要件を満たしていないからだ。
その考察・研究の要件とは、どのようなものか。単に仮説を主張するだけではなく、それを裏打ちする論証がなければならない。この論証のために、他の研究者の研究や見解が引用(援用)されるわけだが、そのさいにも自分の評価や見解を述べる必要がある(先行研究のレビューをふくむ)。独自性が必要なのだ。引用についても独自の研究のない論文、論証を欠いた論文はしたがって、落第点ということになる。
いっぽう政治論文には、研究論文以上に求められる重大な要件がある。まず第一に必要なのは、政治主張が明確であることだ。ここが鮮明であればあるほど、すぐれた訴求力が求められる政治論文の要件となる(例文は後掲)。逆に言えば、いかに情勢分析や情報量にすぐれようと、主張のない政治論文は落第点なのである。
情勢分析において「全面的な政治暴露」をすると同時に、政治主張として「宣伝・煽動」すること。すなわち打倒すべき対象、連帯・支援すべき相手が明確にされなくてはならないのだ。以上が政治論文の要件である。
※「」内の引用はレーニン『何をなすべきか』(全国的政治新聞の計画について)。
そしてその政治主張はかならず、行動(任務)方針に結実されなければならない。具体的なスローガン、行動方針を欠いた政治論文は、ただのお喋りである。評論家の単なる批評ではない、国家と革命に責任を持つ革命党派の政治主張とは、そういうものだ。
それでは「radical chic」(47号)の「幾瀬仁弘論文」を、以上の観点からみていこう。
◆幾瀬論文はウクライナの敗戦と自治領化を主張している
幾瀬論文は資本主義の崩壊の危機が、中心部から周辺へのさらなる搾取と収奪による利潤で延命され、その究極の現われが戦争であるとする。これ自体は誤りではないが、ウクライナ戦争にはまったく当てはまらない。
ウクライナ戦争は19世紀的な帝国主義の顕現であって、プーチンが目指すものは資本主義の延命ではなく、絶対主義帝国(絶対的君主=皇帝による、複数の地域民族の独裁的支配)の復活なのである。したがって論文の基本骨格から、論軸をはずしたものになってしまっていると指摘しておこう。
そして幾瀬は、戦争の基本動因が軍事産業およびエネルギー資源であると云う。それもロシアのではなく、アメリカの目論見であると明言するのだ。残念ながら、その論証は何もない。いや、そもそも論証できるはずがないのだ。
軍需産業のために、バイデンが兵器供与で戦争を継続させていると云うのなら、なぜバイデンは「F16は供与しない」と断言したのか。エイブラムス戦車1輌が対価9億円に対して、F16戦闘機1機は20億円以上である。自衛隊も次期主力としている最新式のF35が125億円、中国の気球を撃墜して名をはせたF22ステルス機は、じつに350億円以上である。軍需産業のためなら、なぜこれらの高額兵器を供与しないのか。この事実を取材したうえで論証してみるといい。
エネルギー戦略がもたらした戦争だと云うのであれば、今回の戦争にセブンシスターズをはじめとする石油メジャーがどのような動きをして、戦争を画策したのか。これにも論証がない。すべての「政治暴露」が、幾瀬という人物の脳内世界の出来事なのである。その脳内世界を支配している陰謀論(ディープステート)については、稿を改めたい。
そして肝心の政治主張なのだが、ほとんどそれらしきものはない。この点でも、幾瀬論文には落第点を付けざるを得ない。
わずかに「われわれに課せられた任務は、日本における若者たちの決起を促し物質化することである」と、組織方針らしきものが書かれているが、具体的ではない。
そもそも首都圏委自身がウクライナ戦争反対に「決起」していないのに、どうやって「若者たちの決起を促し物質化する」というのだろうか。任務方針もまた、幾瀬の脳内世界の産物なのだ。
幾瀬論文の中から「政治主張」らしきものを抽出するとしたら、以下のくだりから主張の一端が得られないこともない。今回の戦争に対する態度である。
「戦争が続く(続けられる)のは、米国をはじめNATO諸国がウクライナに兵器を供与するからだ」(幾瀬論文)というものだ。
つまり米国とNATOが兵器の供与をやめれば、戦争は終わると幾瀬は主張しているのだ。すなわちロシアの侵略がウクライナ全土におよび、ゼレンスキー政権の崩壊によって、ロシアがウクライナを自治領化すること。プーチンの勝利にこそ、戦争終結の展望があるというのだ。
幾瀬論文はつまり、ウクライナに敗戦をもたらすために、アメリカの兵器供与反対を主張しているのだ。その結果、プーチンの移民奴隷化政策や戦争犯罪は不問にすることまで、考えをおよばしていない(無自覚な)のは明白である。
この無自覚な主張においてもなお、最初にわたしが問いかけた「この戦争が(首都圏委の主張する)帝国主義観戦争であれば、ゼレンスキー政権は傀儡政権として打倒対象になるのではないか?」という設問には、答えられないであろう。本当に自分の主張に自信があるのなら、ゼレンスキー政権打倒というスローガンを掲げてみてはどうなのか。
このように首都圏委は、ある種の自家撞着に陥っているにもかかわらず、ウクライナの敗北とロシアへの隷属化にしか、平和の展望はないと云うのだ。
幾瀬は「radical chic」(45号)論文においても「(ゼレンスキーが)ミンスク合意を無視しながら、NATO加盟をちらつかせてロシアを刺激したことがこの戦争の原因であった」とし、ブチャでのロシア軍の虐殺も「その原因をつくり出したのはゼレンスキーである」と主張していた。
この主張を維持するのであれば、幾瀬はプーチンのほぼ完全な代弁者であると指摘しておこう。ちなみに、わが国で幾瀬と同じ主張をしているのは、鈴木宗男や森喜朗ら親ロシア派の政治家だけである。
早川礼二も「radical chic」(46号)の「【補論】グローバル化時代の民族問題と戦争論」(これが改ざんと誤記誤植論文である)において、中井和夫(ウクライナ史)の著書を論拠にしながら、こう述べている。
「民族自決に基づく『国家の急増』が国際社会に与えている負荷・コストの大きさ」に触れ、「民族自決」を「民族自治」にかえていくこと「他(ママ)民族の平和的統合の政治システムとしての連邦制の可能性」を論じている。我々の時代認識が問われている。
と、ウクライナの「民族自決」を否定し、ロシア連邦内「自治領化」の必要を主張しているのだ。
これが首都圏委の政治主張であるのならば、在日ウクライナ大使館に「ウクライナはロシアに降伏せよ」「米帝の支援を断り、ロシアの自治領になれ」とデモをかけてみてはどうか。
もちろん、かれらにはそんなことも出来ないであろう。政治的な実践とはかけ離れた、客観主義的な批評家集団に陥っているからだ。そうなった理由も、つまびらかにしておこう。
◆「次世代共産主義者の輩出」に失敗した共産同首都圏委
「若者たちの決起を促し物質化する」のが任務だとする共産同首都圏委員会は、2000年を前後するころから「次世代共産主義者の輩出」を組織的なスローガンにしてきた。
60年代・70年代を闘ってきた先行世代の党員が高齢化し、組織の維持に危機感をもった、何となく情けないスローガンだったと記憶する。
ここ10年ほどで、相次いで指導的な党員が逝去したことから、しかしこのショボい組織拡大のスローガンは現実的だったと振り返ることができる。サロン的にではあれ、組織を維持してきたことには敬意を表したい。
しかしながら、70・80年代の苛烈な闘争(狭山・三里塚・沖縄・学園をめぐる党派闘争)を経験した世代の厳しさが失われ、穏和的な環境の中で継承された「次世代共産主義者の輩出」は、ほとんど失敗したと考えざるを得ない。
このかんの首都圏委との「論争」でわかったのは、まがりなりにも革命党派の構成員であれば必要な初歩的な知識、マルクス・レーニンの基本文献、国際共産主義運動の総括といった、70・80年代の学生活動家なら常識の範疇だった理論的な基礎がない、ということだった。
幾瀬仁弘がコミューン原則(常備軍に代わる全人民武装)を理解していないとか、早川礼二がひたすら「戦争国家」を批判することで、戦争と革命における政治論文の論軸、すなわち打倒対象と連帯の相手を定められないなど、彼らがまともな政治論文を書けなかったのも、それなりの理由がある。これが私の感想だ。
現代思想の脈絡でガタリやドゥルーズ、ネグリやジジェクをいかに語ろうとも、そこにマルクス哲学の基礎やレーニンの実践を媒介にした理論的な地平、社会運動の歴史的知識を検証させる体験がなければ、死んだ学習にすぎないのだ。
とりわけ理論が実践において検証されることもなくなった時代に、狭山闘争や三里塚といった党の立脚点だった大衆運動から召還し、現実に対して客観主義的な批評家集団にしてしまった、前世代の責任は大きいと指摘しておこう。
◆簡潔で方針が鮮明な、政治論文の好例がこれだ!
このままではあまりにも悲しいので、市民運動に埋没し「あらゆる戦争国家に反対する」(早川礼二論文)などと、小ブル的な反戦運動のスローガンに収束する首都圏委が思いもよらない、プロレタリア階級と共産主義者の戦争に対する原則的な態度を引用しておきたい。
以下は、同じ共産同(ブント)系の党派で簡潔にまとめられた、ウクライナ戦争に関する政治論文の引用である。まっとうな政治論文である証左として、具体的な行動方針が盛り込まれているのに注目されたい。
【ロシアのウクライナ侵略において、左派は被侵略民衆と政府の抗戦を徹底支援すべきである】
埴生満 ※共産主義者同盟(火花)『火花』461 号(2023年2月)所収
「今般のプーチン=ロシアのウクライナ侵略と労働者・民衆虐殺は人権、民主主義および階級闘争の観点から一切許せる余地はなく、怒りとともにこれを弾劾する。我々共産主義者はプーチン=ロシアの侵略と虐殺に反対し、米国・NATO 諸国を含む世界各国の民衆と政府にウクライナ民衆・政府への全力での支援を求め、また自身でも実践する必要があり、それに向けた行動を呼びかける。この際、西側帝国主義国政府の過去の愚行・蛮行を理由にしてそのウクライナ支援を阻害しようとすべきではない。
(中略)
全世界の共産主義者に対し、各自の活動条件に合わせて以下のような種々の行動に参加し、あるいは自らそのような行動を組織して、周囲の労働者・民衆に働きかけそれを拡大していくことを呼びかける。■自国政府に対し、ウクライナの労働者・民衆およびそれを代表する民主主義的政府への全面的(人道的か軍事的かを問わない)かつ最大限の支援を要求する。その一部として、ウクライナとロシアからの難民・亡命者を最大限受け入れることを求める。
■ウクライナ現地での活動、自国社会での募金・街頭行動、インターネット上の活動などあらゆる手段で、ウクライナの労働者・民衆、あるいはそれを代表する政府への直接的支援を行い、現地と国際社会におけるその力と立場の強化を図る。
■ユニセフなど国連の人道機関、「国境なき医師団」などを含む国際NGOのウクライナや周辺諸国での活動を支援する。
■インターネット上かリアルの現場かを問わず、プーチン政権およびその出先諸機関や追随者によるディスインフォメーション(虚偽情報)を含めたプロパガンダの欺瞞を徹底的に暴露し、それらを無効化していく。
■左派内部を含め存在している「プーチンの侵略は悪いが NATO・ウクライナも悪い」といった、事実経過を無視した日和見主義的な「どっちもどっち」論を批判し克服していく(以下略)。※(引用文責・横山)
いずれ「台湾有事」「米日帝の中国侵略反革命戦争」にさいして、米帝の戦争には反対だが、台湾人民の反帝(反中国)独立闘争に、いかなる態度を取るのか、が問われる。その意味で、ウクライナ戦争は左派の理論闘争が不可欠なのだ。
※なお、ウクライナ戦争論争については2月20日発売の『情況』(第6期創刊号)において、渋谷要の寄稿ほかで扱っているので参照されたい。
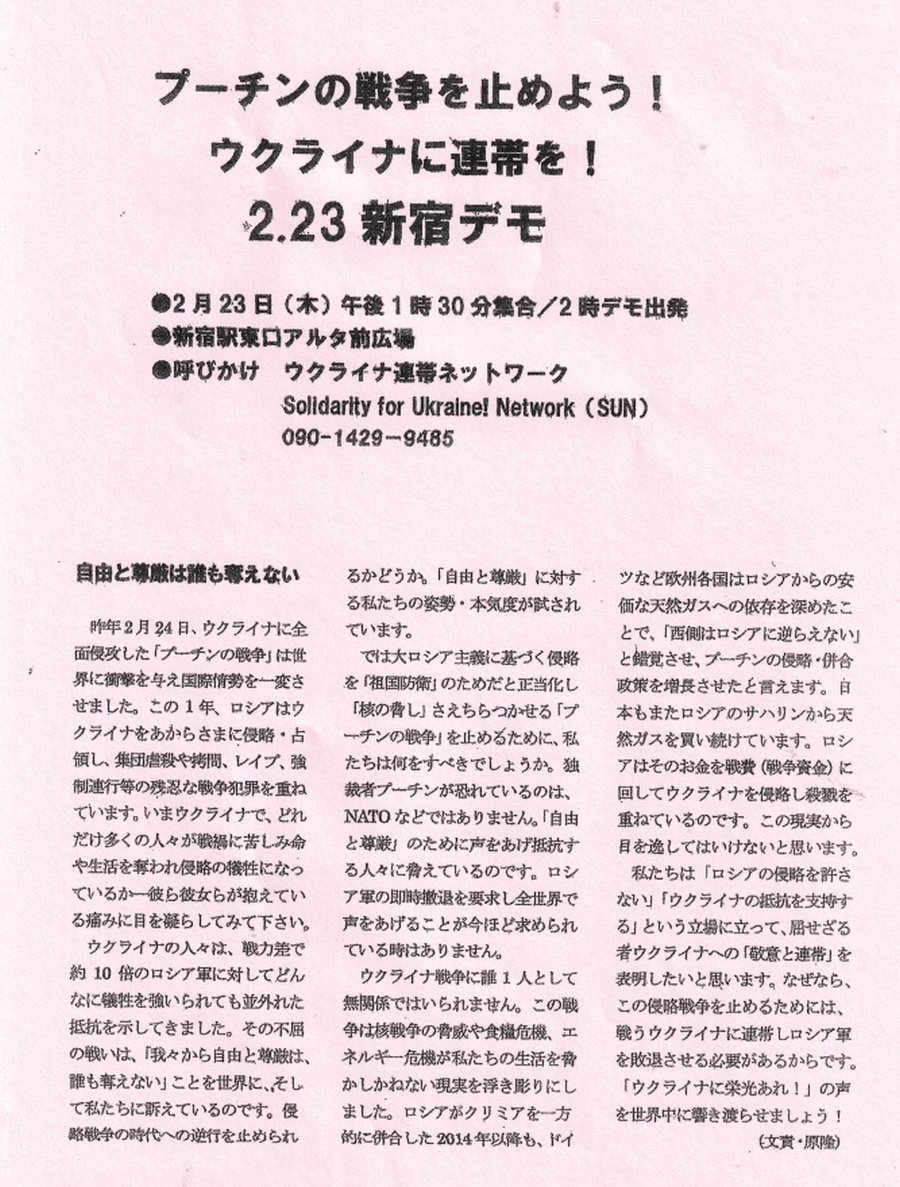
▼横山茂彦(よこやま・しげひこ)
編集者・著述業・歴史研究家。歴史関連の著書・共著に『合戦場の女たち』(情況新書)『軍師・官兵衛に学ぶ経営学』(宝島文庫)『闇の後醍醐銭』(叢文社)『真田丸のナゾ』(サイゾー)『日本史の新常識』(文春新書)『天皇125代全史』(スタンダーズ)『世にも奇妙な日本史』(宙出版)など。
