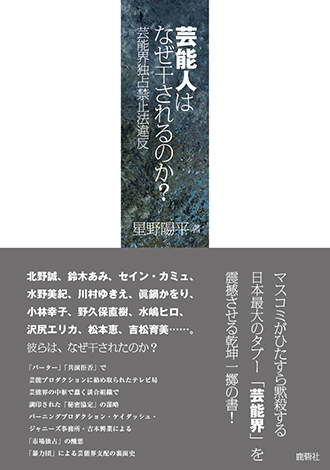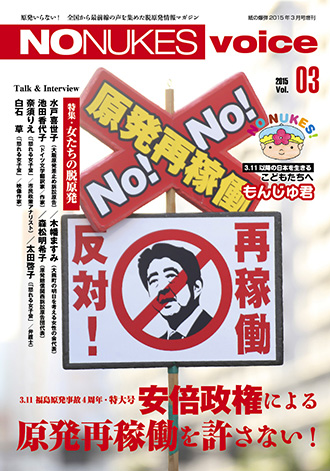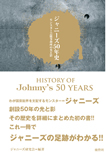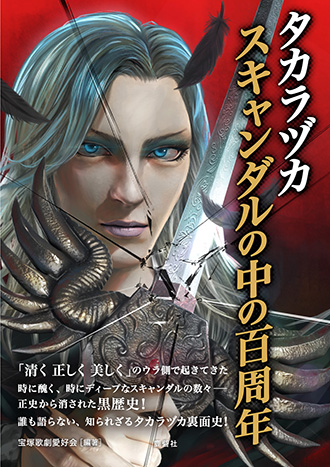5月10日に「プリズム」が製作した舞台公演「心のプリズムvol.Ⅵ~闇をときなす音色~」を観劇した。場所は新宿のシアター・ミラクル。満員だった。
実は、この安奈音々氏がプロディースする劇は、「ダンス」のパフォーマンスが優れているといい意味で評判だったので、気になっていたが、日程が合わず、ようやく5月に観劇できた。
◆実力のある劇団俳優たちの舞台迫力
「演劇」については、もはや実力のある俳優だらけで疑う余地がない。劇団の俳優たちは、厳しい演出家のもと、実に拷問のような訓練を受けている。だからしばしば、劇団の公演のあとにテレビドラマを見ると「こんな学芸会みたいなドラマを本気で流しているのか」と唖然としてしまうことになる。
ちなみに、ストーリーとしては、リーダーが死んで、劇団が存続するか否かの時期に、女優のひとりがガンになるという暗い設定ながら、それを吹き飛ばすがごとく緻密に構成されたミュージカルで、その闇に覆われそうなストーリーの舞台を、音楽や踊りで明転させている。
また、ひとつ見所をあげれば、全員がマイケル・ジャクソンの曲で踊るシーンも、大智そあが社交ダンスを展開するシーンも捨てがたいが、やはり剣舞の迫力だろう。こういってはなんだが、まだ剣舞を楽しめる空間があったのか、というより、「まだ剣舞をしたがる若者がいたのか」というのが正直な感想だ。

◆劇団には若者たちの熱いエネルギーが満ちている
劇団といえば、「貧しい生活」が代名詞だ。僕は日活芸術学院にいて、シナリオの勉強に明け暮れていた。撮影所の連中とよく一緒に飲食したがとにかく彼ら劇団員は、肉体労働に明け暮れていた。
しかしながら「夢を食べる」がごとく将来に成功するためには、「いつかきっと」ががんばるエネルゲンだ。今もなお劇団員を見るとドキドキする。
劇団員が「果たして…俺はものになるのだろうか」と揺れる心を描いた秀逸な作品は、ドラマでは中村雅俊の『俺たちの祭』で、何回も深夜の再放送で見たが、そう、あれこそが劇団の生活で、飲食すらままならず、友だちの家に転がり込んで「ご飯にしょうゆをかけて食べる」などというのはザラだ。
「若者は我慢が足りない」と言われる。「ゆとり世代」「さとり世代」とも言う。だがこと劇団に限っては、今もなお、若者たちには熱いエネルギーに満ちていると思う。
残念ながら、自分が青春をすごした「日活芸術学院」は、すでに2013年廃校となり、映像コースは城西国際大学に引き継がれることになったようだ。なんと城西大学! 僕は高校が城西大学附属川越高校だから、とても不思議な縁を感じる。
高校時代にも、授業を抜けだして、さまざまな演劇を観にでかけた。そんなことばかりやっているから、成績がいいわけがないのだが、実に楽しい思い出だ。
宇崎竜堂が音楽を担当し、町田義人が歌った「ロックオペラ・サロメ」や坂本龍一が演出した劇も観たが、やはり劇団四季や宝塚は別格で、一度は観てみるべきだと思う。また、実は「オズの魔法使い」も榊原郁恵や早見優や、本田美奈子などが演じてきたが、一度は観るべきだろう。今は宮本亜門が演出しているようだが。
◆筒井康隆や江戸川乱歩の作品は今こそ演劇化すべき
今、昔の演劇の脚本が見直されているという。シェイクスピアや、オスカー・ワイルドや、日本では寺山修二、つかこうへいなども見直されている。「今更なにを言っているんだ、そんなの基礎知識じゃないか」と嘆くなかれ。若者は黒沢明も、小津安二郎も木下恵介も知らない。
今、自分が演劇化すべきと思う作品はたくさんあると思うが、筒井康隆や江戸川乱歩などはどうだろうか。江戸川乱歩などは逝去50年という節目で、タイムリーだ。さまざまなイベントが行われており、旬だと思う。
話をもとに戻せば、どうしてテレビドラマは、演劇のようにリハーサルを重視しないのだろうか。自分もテレビの制作にいたので、ドラマの現場を知っているが、多忙なタレントや歌手も集まっているので簡単に本読みをして、立ち位置を確認して、あとはよろしく、うまく撮ってねというスタイルだ。こんなものが世界に通用していくわけがない。もしも演劇というものを真剣に考えるなら、政府よ! 劇団に補助金を申請させよ。フランスなど優秀な映画監督や舞台監督がいるとなれば「作品に使ってください」と惜しみなく金を投資するではないか。
まあでも、今の若者の演劇を観ていれば、しっかりしているので安心する。自分もいつか、ブロードウェイの芝居を観てみたい。明日の生活すらも保証されない。厳しい競争原理から生まれた演出と演技。そこにはびこるのは日本ならではの「なあなあの芸能界」の風習とかけ離れた、「磨かれた実力」によるスキルが演技に反映された芸術空間にちがいないのだから。
(小林俊之)
◎アイドル撮影会は「先物買い」──1対1の激写体験で「至福の境地」!
◎自粛しない、潰されない──『紙の爆弾』創刊10周年記念の集い報告
◎「書籍のPDF化」を拒み、本作りを殺す──経産省の「電子書籍化」国策利権